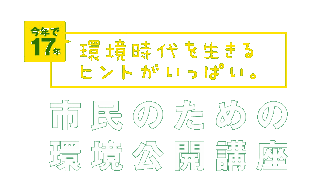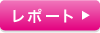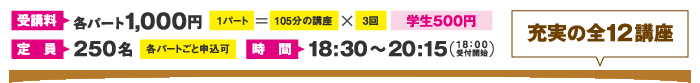
パート1・危機をのりきる逆転の発想
-
世界が気候変動の危機に対し、喫緊の対応を迫られている一方で、これは世界が持続可能なグリーンエコノミーへと発展するための機会だとも言えます。
世界が気候変動の危機に対し、喫緊の対応を迫られている一方で、これは世界が持続可能なグリーンエコノミーへと発展するための機会だとも言えます。アメリカ合衆国は、クリーンエネルギーによる雇用を創出するための緊急経済対策で6,00億ドル、クリーンエネルギー経済への移行のための研究と開発のために、10年で1,500億ドルを費やすことを考えています。これらの投資は、エネルギーの効率化だけでなく、環境の改善、予防措置にもつながり、米国及び周辺諸国の人々にさらなる繁栄と幸福をもたらすでしょう。我が国は、今年11月の気候変動枠組み条約締約国会議において、気候変動に対応するための新しく、野心的で、効果的な枠組への合意を目指し、他の国々と協力していくつもりです。
-
世界で最もきびしい排気ガス規則であるUSAのマスキー法を世界で初めてクリヤーした低公害車CVCCの開発を例に「危機をチャンスに変えるチャレンジ」の速やかな始動を提案する。
世界で最もきびしい排気ガス規則であるUSAのマスキー法を世界で初めてクリヤーした低公害車CVCCの開発を例に「危機をチャンスに変えるチャレンジ」の速やかな始動を提案する。
・危機克服→企業基盤確立(事例研究)
・企業がとるべき危機克服の為の必須行動
・迅速・確実な目的・目標達成に有力な研究・開発のシステム化
・マネージメントの役割 -
環境劣化と資源枯渇に象徴される環境問題を克服し、地球環境の保全と人間社会の永続化を図っていくことは、現在、喫緊の課題となっています。そのために科学技術的対応や政策的対応が進められていますが根本的には...
環境劣化と資源枯渇に象徴される環境問題を克服し、地球環境の保全と人間社会の永続化を図っていくことは、現在、喫緊の課題となっています。そのために科学技術的対応や政策的対応が進められていますが、根本的には従来の価値観と生活様式を改めていくことが不可欠です。環境思想史学はそのためのヒントを過去に求めます。講義では、金子みすゞ(1903〜1930)の詩を取り上げ、環境思想をどのように育んでいけばよいのか考えます。

パート2・世界の環境最新事情
-
スウェーデンの首都ストックホルム郊外にあるハンマービー地区は、世界が注目する環境モデル都市。品格のある街並みを写真で見ながら、廃棄物処理で発生するエネルギーや自然エネルギーを...
スウェーデンの首都ストックホルム郊外にあるハンマービー地区は、世界が注目する環境モデル都市。品格のある街並みを写真で見ながら、廃棄物処理で発生するエネルギーや自然エネルギーを、都市設計に取り入れた街のくらしを紹介します。さらに、スウェーデンが世界モデルになっているのが、原子力廃棄物の地層処分の取り組みです。スウェーデンのエネルギー政策とその基本となる考えを、取材を通して、動画(5分)と共にお伝えします。
-
温暖化と闘う時代では、世界の政策協調、交渉における各国の主導権争い、グリーン市場の獲得競争が同時に起きる。
温暖化と闘う時代では、世界の政策協調、交渉における各国の主導権争い、グリーン市場の獲得競争が同時に起きる。業界への配慮から大胆な政策変更ができない日本、背伸びするような目標を掲げるEU、国内政策を変えて一気に交渉の主導権を握ろうとする米国。日本は生き残れるか?
-
9月29日(火)
持続可能な発展とマルチ・ステイクホルダー・ガバナンス
- 谷本 寛治氏
- 一橋大学大学院商学研究科 教授 特定非営利活動法人ソーシャル・イノベーション・ジャパン 代表理事
ダイジェスト版は
掲載いたしません。私たちの生活は、経済面のみならず社会面・環境面においても、持続可能でなければ成り立ちません。持続可能なシステムをつくっていくためには...
私たちの生活は、経済面のみならず社会面・環境面においても、持続可能でなければ成り立ちません。持続可能なシステムをつくっていくためには、政府や企業のみならず、私たち一人一人が(勤労者、消費者、地域住民、地球市民などとして)、国内外の経済・社会・環境問題に関心を持ちかかわっていく必要があります。本講座では、(1)改めて持続可能な発展とは何かを考え、(2)今私たちに求められることは何か、そして(3)多様なステイクホルダーがかかわるこの課題をどのように取りまとめていけばいいのか、を考えていきます。

パート3・くらしと環境
-
築地市場で30年以上、すし種を取り扱う仲卸業者として働いている。市場を取り巻く環境の変化は激しく、この30年間だけ見ても、取扱量だけでなく、魚介類の種類、流通方法などが大きく変わってきている。
築地市場で30年以上、すし種を取り扱う仲卸業者として働いている。市場を取り巻く環境の変化は激しく、この30年間だけ見ても、取扱量だけでなく、魚介類の種類、流通方法などが大きく変わってきている。築地市場ではすしの人気が相変わらず高く、毎日のように大行列ができるが、すし屋で扱うすし種も、時代とともに大きく変化してきた。このすし種の変化は、環境問題とも密接な関係があったのである。
1.築地市場とは何か(自己紹介を兼ねて)
(1)東京中央卸売市場築地市場
(2)取り扱っている魚介類
2.「すし」から見える環境問題
(1)「すし」の歴史
1)歴史を探る
2)江戸前ずしとは何か
(2)時代とともに移り変わるすし種
1)江戸時代〜明治時代
2)昭和
3)平成
(3)すし種から考える環境問題
1)東京湾で絶滅した魚
2)フードマイレージ、環境を考える
3.築地市場の仲卸として・・・現在、未来 -
既存の貿易や流通のあり方は、しばしば南の生産者や環境に知らずのうちに多くのしわ寄せをしてきました。どうやってモノを作ったのか、どうやってここまで届いたのか。
既存の貿易や流通のあり方は、しばしば南の生産者や環境に知らずのうちに多くのしわ寄せをしてきました。どうやってモノを作ったのか、どうやってここまで届いたのか。作り手と使い手がお互いに思いを馳せあう意識が、「買い物」という選択をより深いものにし、自分自身のライフスタイルを見直す視点を与えてくれます。買う人の選択責任が問われる時代の買い物の、一つの価値軸を提案します。
-
「最高の製品を作り、環境に与える不必要な悪影響を最小限に抑える」これがアウトドア・ブランド、パタゴニアの存在意義です。一方で、ビジネスを行なうことで何らかの形で地球の健康に影響を与えているのも事実です。
「最高の製品を作り、環境に与える不必要な悪影響を最小限に抑える」これがアウトドア・ブランド、パタゴニアの存在意義です。一方で、ビジネスを行なうことで何らかの形で地球の健康に影響を与えているのも事実です。パタゴニア製品が地球に残す足跡(フットプリント)に目を向けながら、安全、公正、適法かつ人道的な労働環境で製造されるために、日々の業務に疑問を投げかけて実践してきた取り組みや課題をお話しします。

パート4・生物多様性
-
野生動物による農作物の被害が増えています。しかし、被害というのはあくまでも人間の都合。野生動物が畑を荒らす。悪いのは動物。捕獲や柵で防ぐしか方法はない。といった短絡的な思いでは...
野生動物による農作物の被害が増えています。しかし、被害というのはあくまでも人間の都合。野生動物が畑を荒らす。悪いのは動物。捕獲や柵で防ぐしか方法はない。といった短絡的な思いでは、ムダな経費と報われぬ労力がかさむばかり。まわり道のようでも、ちょっと立ち止まって、人間側だけでなく動物の都合も考えながら山や里で、今、何が起きているのか見直してみると様々な新しい対策が見えて来ました。
-
父は「佐渡と言う風土があり、そこに人がおり、トキがいた」が口癖でした。かつて、動物や自然との共生の環境が長く育まれてきた日本ですが、便利で豊かな生活の追求によって急激な環境変化が起こり、大切なものを失いました。
父は「佐渡と言う風土があり、そこに人がおり、トキがいた」が口癖でした。かつて、動物や自然との共生の環境が長く育まれてきた日本ですが、便利で豊かな生活の追求によって急激な環境変化が起こり、大切なものを失いました。
トキへの思いや共生の願いから続けてきたトキの保護、野生復帰にまつわる活動や、トキ保護関連の団体の連携、また、子ども達への環境教育活動についてご紹介します。 -
道路や線路などにより森が分断・細分化されると、そこに生息するヤマネやリスなどの樹上動物に様々な影響が及びます。
道路や線路などにより森が分断・細分化されると、そこに生息するヤマネやリスなどの樹上動物に様々な影響が及びます。そこで、この分断された森と森を渡れるようにするための橋として「アニマルパスウェイ」を開発・設置しました。この取組の成果、課題、展望などをお話しながら、環境保全活動の具体化を紹介します。

お申込方法
-
受講料
各パート1,000円(学生500円)
1パート=105分の講座×3回※(社)日本環境教育フォーラム会員の方で受講を希望される方は、
お電話で同フォーラム(TEL 03-3350-6770)へ直接お申込ください。
※ご入金後のキャンセルは致しかねますのでご了承ください。 -
定 員
250名
各パートごと申込可・定員になり次第締め切りといたします。
-
時 間
18:30〜20:15(18:00受付開始)
-
申込先・
お問い合わせ先〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
(株)損害保険ジャパン CSR・環境推進室内
「市民のための環境公開講座」事務局
TEL 03-3349-9598 FAX 03-3349-3304 -
場 所
損保ジャパン本社ビル 2F大会議室
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
(新宿駅西口より徒歩7分)温室効果ガス削減のため、「チーム・マイナス6%」に賛同し、室温を調整しております。
本講座はグリーン電力(太陽光発電)を利用して運営する予定です。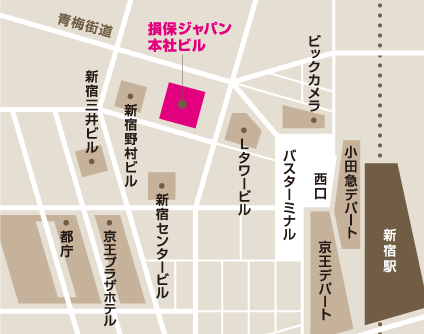
-
個人情報の
取扱いについて申込書に記載いただいた個人情報は、本講座の受講のご案内等、講座の運営に必要な範囲で、事務局である、(社)日本環境教育フォーラム、(財)SOMPO環境財団、(株)損害保険ジャパン、の3者が取得、利用させていただきます。
-
主 催
-
後 援
協 力