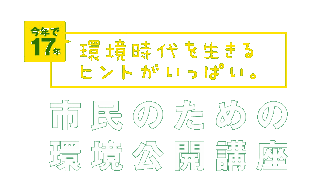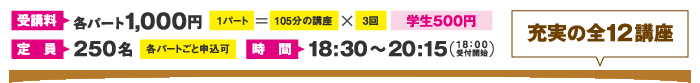
パート4・生物多様性
獣害・なぜ増える・どう防ぐ ―わるいのは野生動物なのか?―
- 井上 雅央氏
- (独)農研機構 近畿中国四国農業研究センター 鳥獣害研究チーム長
 昨今、野生動物によって畑を荒らされるなど、いわゆる「獣害」が増加しています。一体なぜこうした被害が激化するのでしょうか?
昨今、野生動物によって畑を荒らされるなど、いわゆる「獣害」が増加しています。一体なぜこうした被害が激化するのでしょうか?
奈良県でサルによる被害の研究をしていた時、私は全ての被害現場を見て回り、農家の人々に聞き取りをしました。その時、どこの集落でもよく耳にしたのは「昔からあの山にサルがいるという言い伝えはあったが、実際に見たことはなかった。しかし、いつの頃からか年に一回姿を見るようになり、それが段々回数が増え、次第にサルの数も増え始めた」ということです。実は、この「段々増えた」というところに、大きなヒントが隠されています。獣害増加の原因として、温暖化、人工林の増加、過疎高齢化、狩猟者減少等が一般的に挙げられますが、動物からすれば、恐くなくなったから出てくる、出てきたら食べられる、住んでみたらもっと食べられる…というのが真相です。動物は学習します。つまり、我々は「餌付け」に成功してしまったということなのです。
 餌付けは2つの条件で成功します。1つは、人間や車は恐くないということを動物に教えてあげること、もう1つは、1年中豊かな餌を準備してあげることです。人間の集落の中に、動物たちにとっての餌は2種類あります。「動物が出てきて食べたら人間が怒る餌」と「いくら食べても人間が怒らない餌」…この2つで実は人間が餌付けをしてしまっているのです。例えば、誰も住んでいない廃屋の庭に柿の木が生えているとします。これは収穫しない柿なので、サルがそれを食べていても、人々はそれを見物しながら通り過ぎます。サルはその度に、人間は恐くないことを学習します。一方、畑で収穫用に栽培している柿を食べると人々は怒ってサルを追いかけますが、サルの足には追いつけません。するとサルは、人間からは逃げ切れることを学習します。こうして、餌付けが成立してしまうのです。同様に、稲刈り前の米を食べれば人は怒りますが、稲刈り後に生えたヒコバエを食べても誰も怒りません。この他にも、人間が無意識にやってしまっている餌付けがたくさんあります。例えば秋に畦や堤防の草刈をすれば、その後に生えてくる雑草類が冬場の餌となってしまいます。台所で切捨てた野菜クズが堆肥になるからと目の前の畑に捨て、規格外だから収穫後に実ったからと野菜や果実を収穫せずに放置する等の行為も同じです。このような状況で、動物の側がこれらの食料と、食べたら人が怒る作物とを区別することができるでしょうか。
餌付けは2つの条件で成功します。1つは、人間や車は恐くないということを動物に教えてあげること、もう1つは、1年中豊かな餌を準備してあげることです。人間の集落の中に、動物たちにとっての餌は2種類あります。「動物が出てきて食べたら人間が怒る餌」と「いくら食べても人間が怒らない餌」…この2つで実は人間が餌付けをしてしまっているのです。例えば、誰も住んでいない廃屋の庭に柿の木が生えているとします。これは収穫しない柿なので、サルがそれを食べていても、人々はそれを見物しながら通り過ぎます。サルはその度に、人間は恐くないことを学習します。一方、畑で収穫用に栽培している柿を食べると人々は怒ってサルを追いかけますが、サルの足には追いつけません。するとサルは、人間からは逃げ切れることを学習します。こうして、餌付けが成立してしまうのです。同様に、稲刈り前の米を食べれば人は怒りますが、稲刈り後に生えたヒコバエを食べても誰も怒りません。この他にも、人間が無意識にやってしまっている餌付けがたくさんあります。例えば秋に畦や堤防の草刈をすれば、その後に生えてくる雑草類が冬場の餌となってしまいます。台所で切捨てた野菜クズが堆肥になるからと目の前の畑に捨て、規格外だから収穫後に実ったからと野菜や果実を収穫せずに放置する等の行為も同じです。このような状況で、動物の側がこれらの食料と、食べたら人が怒る作物とを区別することができるでしょうか。
 「被害」とは人間の都合だけの言葉です。動物が悪いのではなく、餌付けしてしまった自分たちが悪いのだということを自覚し、何が原因となったのかを考えなければなりません。役所に駆け込んで、柵を作って貰うとか、撃退チームを結成して追い払って貰っても、それは「やって貰う」だけで根本的な解決にはなりません。例えば、台所でハエが増えてしまった時、私たちはハエを何匹駆除すれば解決するかではなく、ハエを増やしてしまった環境を直そうと考えるものではないでしょうか。餌になっているものを取り除き、村人全員が目を光らせて撃退のための行動をとることが必要なのです。逃げ足が速いのであれば、向こうで追いかける人、こっちで待ち構える人など、地域全体で合意と連携をとって対応するべきなのです。自分達でやれば知恵や工夫が蓄積され、動物たちにとっては村へ行っても餌なんて食べられないという状況が出来上がっていくのです。
「被害」とは人間の都合だけの言葉です。動物が悪いのではなく、餌付けしてしまった自分たちが悪いのだということを自覚し、何が原因となったのかを考えなければなりません。役所に駆け込んで、柵を作って貰うとか、撃退チームを結成して追い払って貰っても、それは「やって貰う」だけで根本的な解決にはなりません。例えば、台所でハエが増えてしまった時、私たちはハエを何匹駆除すれば解決するかではなく、ハエを増やしてしまった環境を直そうと考えるものではないでしょうか。餌になっているものを取り除き、村人全員が目を光らせて撃退のための行動をとることが必要なのです。逃げ足が速いのであれば、向こうで追いかける人、こっちで待ち構える人など、地域全体で合意と連携をとって対応するべきなのです。自分達でやれば知恵や工夫が蓄積され、動物たちにとっては村へ行っても餌なんて食べられないという状況が出来上がっていくのです。 また、現在のような獣害にあい続ける状況は、動物たちにとっては「山で食生活を営む」という動物本来の食文化を、我々人間が崩しているということにもなっているのです。動物とのいい関係を築くためには、動物のことだけを理解するのではなく、その周囲で何が起こっているのかということに目を向けるようにすることです。こうすることで、人間と野生動物との関係はもっといい方向に向かっていくのではないでしょうか。
また、現在のような獣害にあい続ける状況は、動物たちにとっては「山で食生活を営む」という動物本来の食文化を、我々人間が崩しているということにもなっているのです。動物とのいい関係を築くためには、動物のことだけを理解するのではなく、その周囲で何が起こっているのかということに目を向けるようにすることです。こうすることで、人間と野生動物との関係はもっといい方向に向かっていくのではないでしょうか。
構成・文:宮崎伸勝/写真:黒須一彦(エコロジーオンライン)