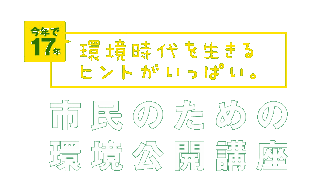パート2・世界の環境最新事情
こんなまちに住みたい -環境先進国スウェーデンの取り組み
- 松田 美夜子氏
- 内閣府原子力委員、元富士常葉大学教授
 スウェーデンのハンマビーは、ストックホルムから電車で20分ほどのところにあり、バイオマスエネルギーを中心にして街づくりを行っている人口約2万人の美しい環境都市です。1970年代は、いわゆる産業廃棄物の捨て場で、汚泥が港に溜まり、空気も悪く、著しく環境汚染をしている区域でした。ちょうど当時の日本の公害問題と似たものでした。1980年代、この街を環境都市として再生しようという一大プロジェクトが、国、県、市、銀行、住宅会社、建築家、都市設計デザイナー等によっておこりました。2010年の完成を目指し、現在も進行中です。バイオマスエネルギーを基本にした都市設計で、清掃工場、生ごみの堆肥化工場、木質バイオマス工場、下水処理場をまちのエネルギー源とし、全ての有機物をリサイクルし、エネルギー供給を支えています。あわせて、交通システムの低炭素化、ごみの発生抑制、市民によるごみの分別やリサイクルも高いレベルで行われています。これらの環境リサイクルモデルは「ハンマビーモデル」として、スウェーデン国内の各地で地域の実情に合わせて取り入れられています。
スウェーデンのハンマビーは、ストックホルムから電車で20分ほどのところにあり、バイオマスエネルギーを中心にして街づくりを行っている人口約2万人の美しい環境都市です。1970年代は、いわゆる産業廃棄物の捨て場で、汚泥が港に溜まり、空気も悪く、著しく環境汚染をしている区域でした。ちょうど当時の日本の公害問題と似たものでした。1980年代、この街を環境都市として再生しようという一大プロジェクトが、国、県、市、銀行、住宅会社、建築家、都市設計デザイナー等によっておこりました。2010年の完成を目指し、現在も進行中です。バイオマスエネルギーを基本にした都市設計で、清掃工場、生ごみの堆肥化工場、木質バイオマス工場、下水処理場をまちのエネルギー源とし、全ての有機物をリサイクルし、エネルギー供給を支えています。あわせて、交通システムの低炭素化、ごみの発生抑制、市民によるごみの分別やリサイクルも高いレベルで行われています。これらの環境リサイクルモデルは「ハンマビーモデル」として、スウェーデン国内の各地で地域の実情に合わせて取り入れられています。
またスウェーデンでは、エネルギー資源がないため、原子力発電をエネルギー供給の中心として据えており、2005年のデータでは国内電力供給構成の46%を原子力発電が占めています。スウェーデンのエネルギー政策は、再生可能エネルギーの普及にこのように力を注いでいますが、まだ全体の5%です。つまり、原子力発電による安定供給に支えられて、様々な再生可能エネルギーを増やしていく取組みが可能となっているのです。
 ところでスウェーデンは、2009年6月に、電気のごみである放射性廃棄物すなわち使用済燃料の最終保管場所を決定しました。現在これが決まっている国は、世界中でフィンランドとスウェーデンのみで、フランスが間もなく3つの候補地を決定しそうだという状況です。しかし、スウェーデンでも、実はこの問題では一度手痛い失敗をしています。国が何もかもを先に決めてしまった後で、国民を納得させようとして反発を受け、1980年以来10年間スウェーデンは地層処分の政策を進めることができなくなったのです。政府はこの間に、地下500mの最終保管場所の実物大モデルを建設して国民に公開するなどの努力を進めてきました。日本もすでに30年以上原子力発電を行っているのですから、その使用済燃料を安全に深い地層(300m以深)に保管できるようにしなくてはいけません。この問題から逃げて回っているばかりでは、将来にツケを残すことになってしまうのではないでしょうか。日本では30年ほど前、清掃工場建設の反対運動が盛んでした。しかし、結局反対運動では人々はついて来ませんでした。そして、問題を解決するためには参加型でなければならないのだと気づいたのです。国や自治体が解決に困っているのなら、私たちも一緒に知恵を出す、そして行政側も情報を公開して欲しいと求めました。この当時の生活ごみの運動と同じ状況に、現在の放射性廃棄物は置かれているのではないかと思います。
ところでスウェーデンは、2009年6月に、電気のごみである放射性廃棄物すなわち使用済燃料の最終保管場所を決定しました。現在これが決まっている国は、世界中でフィンランドとスウェーデンのみで、フランスが間もなく3つの候補地を決定しそうだという状況です。しかし、スウェーデンでも、実はこの問題では一度手痛い失敗をしています。国が何もかもを先に決めてしまった後で、国民を納得させようとして反発を受け、1980年以来10年間スウェーデンは地層処分の政策を進めることができなくなったのです。政府はこの間に、地下500mの最終保管場所の実物大モデルを建設して国民に公開するなどの努力を進めてきました。日本もすでに30年以上原子力発電を行っているのですから、その使用済燃料を安全に深い地層(300m以深)に保管できるようにしなくてはいけません。この問題から逃げて回っているばかりでは、将来にツケを残すことになってしまうのではないでしょうか。日本では30年ほど前、清掃工場建設の反対運動が盛んでした。しかし、結局反対運動では人々はついて来ませんでした。そして、問題を解決するためには参加型でなければならないのだと気づいたのです。国や自治体が解決に困っているのなら、私たちも一緒に知恵を出す、そして行政側も情報を公開して欲しいと求めました。この当時の生活ごみの運動と同じ状況に、現在の放射性廃棄物は置かれているのではないかと思います。
 それでは、もう一度、日本の生活ごみの問題に立ち返ってみましょう。現在ではごみの分別が全国でかなり進みましたが、それでごみは減ったのでしょうか。逆に、私は大量消費がさらに進展したと感じています。例えば、減っていないごみの代表は、飲料缶と小型ペットボトルですが、これらのリサイクル回収率は90%以上です。回収費用は自治体の負担、つまり私たちの税金で賄われているのです。たくさん作ってたくさん回収するのをよしとするのはどう考えてもおかしなことです。
それでは、もう一度、日本の生活ごみの問題に立ち返ってみましょう。現在ではごみの分別が全国でかなり進みましたが、それでごみは減ったのでしょうか。逆に、私は大量消費がさらに進展したと感じています。例えば、減っていないごみの代表は、飲料缶と小型ペットボトルですが、これらのリサイクル回収率は90%以上です。回収費用は自治体の負担、つまり私たちの税金で賄われているのです。たくさん作ってたくさん回収するのをよしとするのはどう考えてもおかしなことです。
日本で1年間にかかる廃棄物処理費は約2兆円です。国民全員がごみを1割減らすだけで2000億円が節約できます。ちなみに、レジ袋は一人年間330枚を使用しており、全国では400億枚になります。これは原油換算すると60万トンで、ペットボトルの年間生産量63万トンとほぼ同じ量に相当します。それだけのレジ袋を私たちは、毎日一瞬持ち歩くためだけに使っているのです。
 私たちが目指すのは、大量リサイクル社会ではなく資源消費量の少ない循環型社会です。近年は国が一方的に決めたことを押し付ける方法ではなく、各市町村で市民参加により、ごみの出し方を決める審議会を開くところも増えています。スウェーデンと日本ではもちろん歴史も違いますが、どちらが成熟した社会と言えるでしょうか。スウェーデンを真似る必要はありませんが、自分たちの住んでいる街をよりよくするために提案をしていく姿勢について、私たちはスウェーデンから学べるのではないでしょうか。
私たちが目指すのは、大量リサイクル社会ではなく資源消費量の少ない循環型社会です。近年は国が一方的に決めたことを押し付ける方法ではなく、各市町村で市民参加により、ごみの出し方を決める審議会を開くところも増えています。スウェーデンと日本ではもちろん歴史も違いますが、どちらが成熟した社会と言えるでしょうか。スウェーデンを真似る必要はありませんが、自分たちの住んでいる街をよりよくするために提案をしていく姿勢について、私たちはスウェーデンから学べるのではないでしょうか。
構成・文:宮崎伸勝/写真:黒須一彦(エコロジーオンライン)