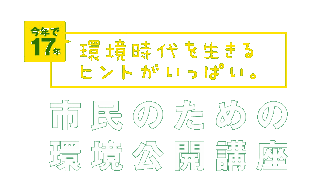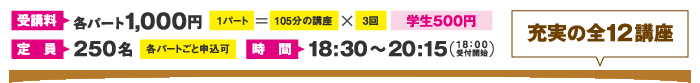
パート1・危機をのりきる逆転の発想
危機をチャンスに! ―CVCCエンジン開発秘話―
- 石津谷 彰氏
- 元本田技研工業株式会社常務取締役
(1)危機克服の事例紹介
私が入社致しました昭和30年頃から今日に至る約50年間にホンダには少なくとも4つの危機がありました。
1番目の危機は29年頃であります。業界初の樹脂ボデーを採用したスクーターのジュノーをはじめ、カブ・ドリーム・ベンリーに相次いで問題が発生し、更に当時の業界全体の労働問題がこれに加わり、販売不振に陥りました。危機状態の中、本田宗一郎は「英国マン島T・Tレースに出場し、全種目優勝を目指すこと」を宣言し、社員・協力部品メーカーさんのモチベーションを高め、団結が強まりました。36年の同レースで目標通り、全種目で1~5位を独占し、二輪世界一の地位を確立することが出来ました。
2番目の危機は36年に、日本政府が米国から貿易の自由化を突きつけられ、自動車の国際競争力を高めるため、トヨタ、日産の既存メーカーを優遇し、異種企業の新規参入を抑制する「特定産業振興臨時措置法」の準備を始めました。ホンダはこの法案成立までに四輪自動車メーカーという既成事実をつくる必要に迫られました。37年のモーターショーに軽3種を出展し人気を博しましたが、販売には寄与出来ませんでした。この失敗の反省に立ち、本格四輪企業への参入を目指し、ホンダは37年からF-1エンジンの研究に着手しました(RA270)。「レースをやらなければ車は良くならない」走る実験室の役割をもたせたマシンで39年1月、F-1グランプリに参戦を宣言しました(RA271)。そして40年メキシコグランプリで初優勝を遂げました。また、量産車では41年、軽のN360を開発し、42年軽自動車発売NO.1を達成して、軽自動車メーカーの地位を確立しました。
3番目の危機は45年、米国で公害対策法が制定されたことに始まります。当時の排ガスレベルをそれまでの1/10に削減しろという大変厳しい規制が各メーカーに突きつけられました。ちょうどそんなとき、軽トップセラー車N360に欠陥車の疑いがかけられ販売は激減してしまいます。また米国市場に上市したばかりのCIVICがこの規制をクリア出来ないと販売が出来なくなります。このとき、「世界に先駆けて、マスキー法をクリア出来る信頼性の高い公害対策システムを確立せよ、後処理は使うな」という研究命令が出されました。不眠不休のチャレンジの結果、47年にCIVICのCVCCエンジンがマスキー法を世界で初めてクリアし、49年から4年連続で米国において燃費NO.1評価を獲得し米国での販売基盤の確立に貢献しました。
4番目の危機が、100年に一度といわれる現在の大不況です。かつてはレースに参戦することで企業の基盤確立に成功して来ました。しかし、平成21年、今回はF-1撤退という苦汁の決断がなされ、経営資源を脱化石資源化研究に集中し、市販車の次世代、次々世代の技術の確立を目指す旨宣言がなされました。大いに期待しております。必ずやってくれると信じています。
(2)危機克服の実践(CVCC開発を例に)
危機の起こりは米国において「5年以内に、排気ガスレベルを当時の1/10に削減しろ」というマスキー法が昭和45年に制定されたことからです。当時はまだ世界のどこでもこのレベルの対応技術は確立されておりませんでした。わずか米国において、エンジンと排気管の間に、後処理装置をつけて、排ガス中の汚染成分を再燃焼させる方式が実験されておりました。当初ホンダも同様のアプローチをしておったところ、或る日宗一郎が研究室に来て、現状を一応聞いたあと、大雷を落としました。「汚染物質がエンジン内部で発生するなら、お前達は何故エンジン内部でクリーンにする研究をしないのか?後処理方式など止めてしまえ!!」。更に「お前達は承知で毒を喰って、薬を探しているに等しい。源で対策しろ!!」と追いうちをかけ、本当に試作品まで引き上げられてしまいました。我々は「そんなことをおっしゃられても、マスキー法は燃焼の改善位で達成出来るレベルとは思えない」と考えておりました。
しかし、この宗一郎の決断、命令がのちの燃焼改革ともいえるCVCCの技術の発明につながり、ホンダの飛躍につながりました。47年3月、公害対策部門のメンバーが5人突然召集をかけられました。「今からマスキー法クリアの作戦の立案をして欲しい」という命令でした。3日間缶詰状態の検討結果、研究目的、研究目標、目標要件等が具体的に定められました。目的は「世界メーカーにさきがけ、マスキー法をクリア出来る信頼性の高い、後処理に頼らない公害対策システムを開発すること」でした。「目標は、7月17日までに2台のCIVICにCVCCシステムを適用し、第三者(ホンダ関連以外の人)評価に耐え得るシステムを作り上げること」「評価は、実車を観る(エンジンルームをみる)、乗る、(排ガスレベルを)計る、について行われること」「レベルは、マスキー法×0.8以下にすること」「燃料経済性は、42マイル/ガロンを下らないこと(約20km/ℓ)」等が詳細に定められました。召集を受けた私達メンバーがそれぞれの得意分野に応じ、リーダーに指名されました。不眠不休のチャレンジが始まりました。我々チームリーダーの間でのKEY WARDは「さあ殺せといえるまで全力をつくすこと」と定めました。エンジンの諸元を色々と変えてテストを行っていた6月のむし暑い夜のことでした。実験室の外側の計測室で、刻々と流れて来るデータチャートを凝視していると、突然汚染成分を示す記録計の針が殆どゼロになってしまう現象が発生しました。それと同時にテスト室内から「大変です!車の床下(排気管が取り付けられている)が真っ赤です」という報告が入りました。私は「しめた!わかった!」と大声を発してしまいました。「そのまま計測を続けて!」と指示しました。日頃考えていたクリーン化の仮説理論が証明されたからです。
この時世界で初めてマスキー法をクリア出来るシステムが完成出来たと確信しました。計測結果はマスキー法×0.8を下回りました。この感動は今でも忘れられません。技術屋として、この機会にめぐり会えたことを大変幸せに思いました。目標の第三者評価も大成功裏に終わり、47年12月、米国環境庁の証明も得られ、49年にモデルとしての認可を得て、米国で上市されCIVIC CVCCの名で以後4年間燃費NO.1を獲得することが出来ました。これによって念願の四輪の米国における販売基盤の確立に大きく貢献したと考えます。この車は20世紀を代表する名車として評価をいただき、日本車ではただ1台名車殿堂入りを果たすことが出来ました。クリーン&エコ車としていささかでも社会貢献出来たことを誇りに思います。
ホンダが「危機をチャンスに変えられた」大きな要素は以下の通りだと考えます。
- 原点に立ち戻り、チャレンジテーマを明確にし、トップダウンで目的、目標を設定する。
- 改善改革は源で行う。
- プロジェクト制を活用し、責任体制を明確に定める。
- 時間的制約を定め集中力を高める。
- 目標達成に至るまでに4~5の節目を設け、ステップごとにマネジメント参加の評価会を必ず行う。
- この場でマネジメントはチームが成功するために必要な助言、経営資源(人・物・金・時間)の調整を行う。
- これらによって、確実・迅速な無駄のない問題解決を可能にする。
・・・等が挙げられます。
「ものづくり」は今や少品種大量生産は過去のものとなり、多品種少量生産から更に変種・変量生産の時代へと突入致しました。この新しい変化に速やかに対応出来る生産技術、製品技術の改革が急務と考えます。危機の有無に拘らずチャレンジし続けましょう。
構成・文:宮崎伸勝/写真:黒須一彦(エコロジーオンライン)