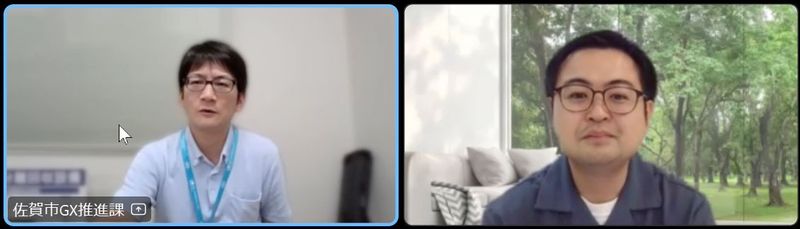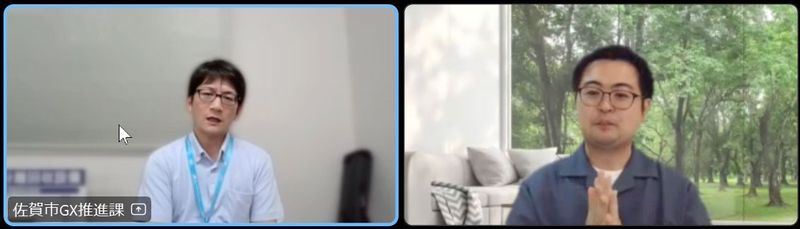日本初の脱炭素・資源循環のまちづくり
佐賀市清掃工場では、立地住民に喜ばれる施設へと変えていくために、廃棄物系バイオマスを資源化し、誘致企業で利活用する取り組みを進めています。その中で、2016年からスタートした排ガス中の二酸化炭素を分離回収し、高度施設園芸や藻類培養に光合成の原料として利用する取り組みは、地域の産業を活性化し、かつ、脱炭素の課題解決にも貢献する特徴的な取り組みです。
講座ダイジェスト

CCU事業のきっかけ
佐賀市の二酸化炭素の利活用事業は、世界で唯一商業化できているプラントです。一般的にはCCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)などと呼ばれ、環境省や経産省が中心になって進められています。佐賀市が二酸化炭素の分離回収に着目した背景は、2005年と2007年に1市6町1村の合併が実施された後に、各地域の焼却炉を統合する計画が持ち上がったことでした。
「NIMBY(ニンビー)」という言葉があります。「必要なのはわかっているけれども、自分の近くにあるのは嫌」という気持ちを表す単語です。焼却炉もそのような環境インフラですが、嫌われ者であり続けるのは非常にまずいと考えました。また、地域のわだかまりのようなものを残しておくと、地域の持続可能性が損なわれるとも考えました。そこで「NIMBY」から、資源やエネルギーが集まってきて、地域に歓迎される施設への転換を目指したのです。
「NIMBY」克服の先駆けとなった下水処理施設
CCUに先立つ15年ほど前、下水処理水を活用した海苔の養殖に取り組みました。海苔は人の生活から排出される窒素やリンを資源にしています。その海苔を大量に生産する冬場に、窒素やリンの濃度を一時的に上げる季別運転を行うことで、海苔の養殖を持続可能にしたのです。当時の海苔漁師は下水利用を非常に嫌がりましたが、さまざまなデータを示して理解を得ました。現在は海苔の漁場である有明海のうち、下水処理場の流域でたくさん捕れるということで、漁師から非常に好感を持たれています。
また、下水処理後に出る汚泥利用も進めました。汚泥を消化反応するとメタンガスが発生します。そのガスから電力をつくり、場内電力と消化反応の熱源(消化槽熱源)に利用しています。消化ガスを得た後に発生する消化汚泥も高温発酵し、肥料成分の分析結果を公表しながら、安い肥料として市民に販売しています。ちなみに毎年沖縄県以外では全量完売しているこの事業を、いち早く達成したのが佐賀市です。
こういった持続可能な資源の活用により、温室効果ガスの排出が抑制されて、地球温暖化の防止にも貢献することを、佐賀市では「サーキュラーバイオエコノミー(Circular Bioeconomy)」と定義づけています。この考えのもとで地域の経済性と環境性を両立しながら、人口の減少や農業の衰退といった問題の解決を目指しているのです。また、持続可能な地域に住んでいることで市民に幸福感を感じてもらい、地元への誇りを醸成することも目指しています。
CCU事業のスキーム
佐賀市では清掃工場周辺への藻類培養や高度施設園芸の誘致と、二酸化炭素および熱の供給を実践しています。最初に進出したアルビータさんは、ヘマトコッカスという抗酸化性の高いカロテノイド色素を生産する藻類を培養しています。今では国内最大級の藻類培養事業となりました。
次に参入した、ゆめファーム全農SAGAさんは、園芸施設内の気象条件などをコントロールしながら栽培する高品質多収技術によってキュウリを作っています。進出から1年目に国内最高反収(約10アール当たり)55.6トンと、一般的な施設園芸と比べて約3倍~4倍を記録しました。次に進出した佐電工さんも高品質多収技術を確立し、植物工場でイチゴを作っています。二酸化炭素は糖度や秀品率を上げるために使われています。このようなさまざまなものが市内で生産された後に市内で消費され、それらがごみとなって戻ってきたら、ごみから二酸化炭素や熱を取り出して地域に循環することに取り組んでおり、それを佐賀市では「脱炭素性能を持った資源循環」と定義づけています。
佐賀市清掃工場のCCUフロー
清掃工場で発生する排ガス中には、二酸化炭素が12%ほど含まれています。排ガスを排ガスコンディショニング装置で冷やした結果、水分や塩化水素ガスを除去し、分離回収装置にかけて二酸化炭素を選択的にアミン吸収液に吸収させます。たまった二酸化炭素を再生搭で再生すると、ほぼ100%の二酸化炭素になります。それを圧縮・冷却した後にタンクにため、配管で事業者に送っているのです。なお、分離回収に必要なエネルギーは、全てごみを焼却した時に作り出している電力や蒸気を利用しています。
広がる事業参入
二酸化炭素分離回収設備の導入により、清掃工場周辺の土地利用がどんどん変容しています。3社に加えて昨年には、花王さんや熊谷組さんが事業参入しました。花王さんはスマートガーデンで育てた花から抽出されたエキスで化粧品を作っています。また、二酸化炭素を利用した炭酸浴を広めるなど、市民の健康づくりにも一緒に取り組んでいるほか、2024年3月に循環型未来都市 「Kirei City Saga」という連携協定を結びました。
熊谷組さんは陸上養殖と水耕栽培を合わせた「アクアポニックス」で進出しています。そこに二酸化炭素を資源として活用た藻類培養を加えることで、藻類が育てた資源を陸上養殖などに活用する実験を行っています。今年の5月には非常に難しいと言われる陸上養殖でサーモンを育て、地域の総合スーパーで試験販売されました。これらの取り組みによって清掃工場のまわりは、経済発展を伴う場所として認識されるようになりました。
この事業を進める中で、二酸化炭素の農業利用を相談した施設園芸コンサルの誠和さんと佐賀市、佐賀県が協力して、値段を示すことで二酸化炭素の分離回収や熱供給を行う工業側と、二酸化炭素と熱を買いたい農家などを結び付けるソフトウェアを開発しました。二酸化炭素の削減量も可視化できるツールです。このソフトウェアは令和6年度に「気候変動アクション環境大臣表彰」を受賞しました。
一方で二酸化炭素の環境価値を示すため、サステナブル資源の国際認証標準規格である「ISCC PLUS」を2024年9月に取得しました。そのきっかけは二酸化炭素を光合成する植物に供給しているため、夜間に回収しても余ってしまう弱点があったことです。そこで液化した炭酸ガスとして供給する事業者ニーズが生まれたのですが、液化すると化石由来の二酸化炭素と見分けがつかなくなるため、清掃工場由来の二酸化炭素では世界初の「ISCC PLUS」を取得したのです。
認証取得の際、原料となるごみの調達時に発生する二酸化炭素は、役所の義務行為で実施していることもあり、二酸化炭素は発生していないと見なされました。また、ごみの中に含まれるバイオマス原料60%から作られる部分については、カーボンニュートラルな二酸化炭素というお墨付きをいただきました。
さらなるGX推進を目指して
佐賀市がバイオマス産業都市に認定されて10年ほどたちました。佐賀市は次のステップに変化するため、清掃工場周辺を脱炭素農業の拠点にしてく「グリーンアグリバレー計画」を含む佐賀市グリーン化推進戦略を掲げています。また、産業グリーン化の推進というテーマを掲げるとともに、GX環境を創出していく上で必要な制度の制定を国に提言するため「佐賀市グリーン化推進戦略」を立ち上げました。
「NIMBY」はおおよそ解消しました。今後はプラントの能力を生かし切れるまでしっかりと事業誘致を進めたいと考えています。一方でGX推進課はいろいろな方々の共感で生まれた課ですので、今後もそれらの方々と一緒に新しいアイデアなどを共有しながら、産業のグリーン化を推進していきたいと思っています。
ここからは講義中に集まった質問と回答の一部を掲載します