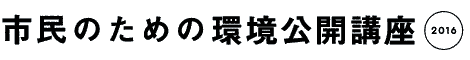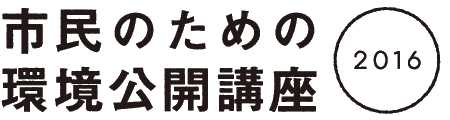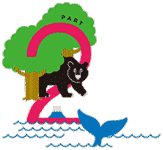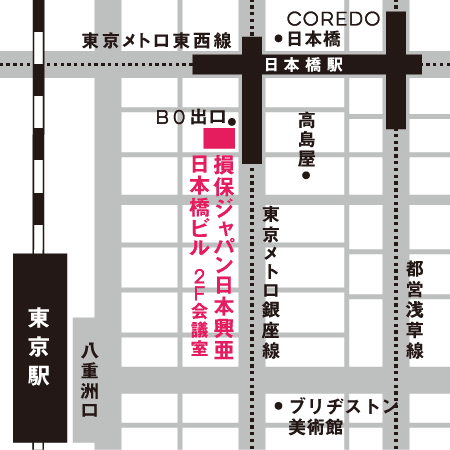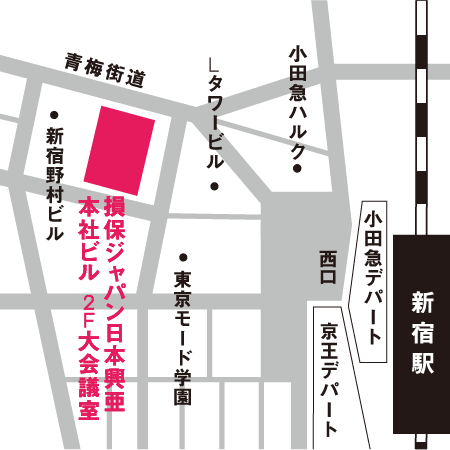講座概要
私は人類拡散のルートをたどる「グレートジャーニー」の旅など、45年間いろいろなところで、自然と共に暮らす先住民の人たちと付き合ってきました。人はどのようにして自然に適応してきたのか。また、この地球の上でどう生きて行けばよいのか。旅を通して気付いたことを話します。

探検家・医師・武蔵野美術大学教授
なぜ人類は世界へ拡散したのか?
 私たちホモサピエンスは、20万年前にアフリカで誕生しました。この日本へは、どのようにしてやって来たのでしょう。主要ルートと見られているのは、シベリア方面を回ってくる北方のルートです。恐らくマンモスなどを追いかけているうちに、かつては繋がっていたと言われている大陸・サハリン・北海道を渡って来たのでしょう。この他、朝鮮半島や台湾を通って、また海洋からも日本にやって来たと考えられています。
私たちホモサピエンスは、20万年前にアフリカで誕生しました。この日本へは、どのようにしてやって来たのでしょう。主要ルートと見られているのは、シベリア方面を回ってくる北方のルートです。恐らくマンモスなどを追いかけているうちに、かつては繋がっていたと言われている大陸・サハリン・北海道を渡って来たのでしょう。この他、朝鮮半島や台湾を通って、また海洋からも日本にやって来たと考えられています。
アフリカで誕生し世界各地に出て行った人類の中で、アフリカ発、シベリア・アラスカ経由、南米最南端へというのが、最も遠くまで出て行ったグループです。この旅路は「グレート・ジャーニー」と呼ばれていますが、それを逆ルートで辿ったのが、私の「グレート・ジャーニー」です。太古の人々とできるだけ近い形で旅をしたいという想いから、自分の腕力と脚力だけで移動するというルールを設け、10年がかりで行った旅です。
 なぜ人類は、アフリカを出て世界中に散ったのでしょうか。ほとんどの人は、「あの山を越えたら何があるだろう」という好奇心、「あの山を越えたら、もっと動物がいたり、もっと木の実があるんじゃないか」という向上心が原動力だったと考えます。だとしたら、南米最南端まで行った人類は、一番好奇心や向上心が強い人達なのでしょう。しかし、そこまで行った人類の中には、マゼラン海峡を越えて、その先の小島まで行ってしまった人もいます。実はその島は、山がちな地形で狩りをする動物もおらず、現在残されている民族も残り一人という絶滅寸前の状態です。一体なぜそんな島にまで人類は行ったのでしょう?これは、どう見ても「そこに行った」のではなく、「そこにまで追い出された」のです。そう考えると、実は「グレート・ジャーニー」ではなく、「グレート・イミグレーション(移民)」だったのではないでしょうか。
なぜ人類は、アフリカを出て世界中に散ったのでしょうか。ほとんどの人は、「あの山を越えたら何があるだろう」という好奇心、「あの山を越えたら、もっと動物がいたり、もっと木の実があるんじゃないか」という向上心が原動力だったと考えます。だとしたら、南米最南端まで行った人類は、一番好奇心や向上心が強い人達なのでしょう。しかし、そこまで行った人類の中には、マゼラン海峡を越えて、その先の小島まで行ってしまった人もいます。実はその島は、山がちな地形で狩りをする動物もおらず、現在残されている民族も残り一人という絶滅寸前の状態です。一体なぜそんな島にまで人類は行ったのでしょう?これは、どう見ても「そこに行った」のではなく、「そこにまで追い出された」のです。そう考えると、実は「グレート・ジャーニー」ではなく、「グレート・イミグレーション(移民)」だったのではないでしょうか。
明治時代の移民を考えてみて下さい。土地がある長男は村を出ませんが、土地を継げない次男以下は、長男を手伝うか、町へ出て工場で働くか、或いは、南米・ハワイ・満州へ行くか、要するに土地を持たない弱い人は外へ出て行きました。戦後は、逆にアジアや南米から日本に移民がやって来ました。それは果たして、母国で強かった人が来たのでしょうか?そうではありません。
豊かになった土地では、人口が増え、飽和状態になったら誰かが出ていかなければならなくなります。その時、既得権を持った強い人が出て行くことはありません。こういうことの繰り返しが、グレート・ジャーニーだったのではないでしょうか。
「多様性」を持つ人類の力
 私たち人類が、他の動物と大きく違う点の一つは、二足歩行をすることです。では、そのメリットは何でしょうか。それは、物を運べるということと、長い距離をゆっくり歩くのに有利だということです。だから人類は、広く世界に拡散していくことができました。
私たち人類が、他の動物と大きく違う点の一つは、二足歩行をすることです。では、そのメリットは何でしょうか。それは、物を運べるということと、長い距離をゆっくり歩くのに有利だということです。だから人類は、広く世界に拡散していくことができました。
もう一つの違いは、人類は一人で行きていくことができないということです。だから、家族を作り、コミュニティーを作るようになりました。DNA上では、人間と僅か1%ちょっとしか違わないチンパンジーですら、家族は作りません。つまり人類は家族やコミュニティーを作ったからこそ生き残ったとも言えるのです。野生の動物は弱い者を襲います。しかし、立って歩き、群れをなす人類は、群れの真ん中で子供を守ろうとするコミュニティーの力も併せ持ったのです。
ところで、チンパンジーは獲物を仕留めた時、その場で食べます。その方が、他のチンパンジーに奪われないからです。しかし人類は、仲間のところへ持ち帰ります。そこでは家族やコミュニティーとシェアしなければなりません。こうしてコミュニティーは広がりを持ち始め、多様性が生まれます。多様性を持ったコミュニティーは、何かが起きた時に、どれかは生き残るという強さがあります。文化についても同じことが言えて、色々なものの見方が共存していれば、何かがあった時、最もいい策を探し出すことができるのです。
 近頃感じるのは、これとは逆の均一性に繋がるような社会現象が見受けられることです。例えばヘイトスピーチのように人を敵視する行為であったり、異なる存在を差別する風潮が広がっています。その結果、職を奪われたり、社会からはじき出される人が増えています。
近頃感じるのは、これとは逆の均一性に繋がるような社会現象が見受けられることです。例えばヘイトスピーチのように人を敵視する行為であったり、異なる存在を差別する風潮が広がっています。その結果、職を奪われたり、社会からはじき出される人が増えています。
「成果主義」が人類を滅ぼす
 今、このような袋小路に日本社会が陥っている原因は、成果主義です。私が大学で教鞭をとっている10年間でも学生たちは変わってきています。「これやると、就職に役立ちますか?」「この授業を取ると、何かいいことありますか?」・・・そんな言葉をよく耳にします。しかし、いけないのは大人たちです。大人自身が一年単位、半年単位で評価されてしまうので、その期間内に成果を出すことを若者にも求めるからです。失敗を繰り返しても、10年20年先に大きな成功があればいいと言われれば、人はチャレンジできます。しかし、1年で確実にやってこいと言われたら、そつなくやるしかありません。チャレンジはしないでしょう。だから人は育ちません。大人が育てようとしていないからです。1年先を見ることも大切ですが、10年先も見なければいけないのです。
今、このような袋小路に日本社会が陥っている原因は、成果主義です。私が大学で教鞭をとっている10年間でも学生たちは変わってきています。「これやると、就職に役立ちますか?」「この授業を取ると、何かいいことありますか?」・・・そんな言葉をよく耳にします。しかし、いけないのは大人たちです。大人自身が一年単位、半年単位で評価されてしまうので、その期間内に成果を出すことを若者にも求めるからです。失敗を繰り返しても、10年20年先に大きな成功があればいいと言われれば、人はチャレンジできます。しかし、1年で確実にやってこいと言われたら、そつなくやるしかありません。チャレンジはしないでしょう。だから人は育ちません。大人が育てようとしていないからです。1年先を見ることも大切ですが、10年先も見なければいけないのです。
私達は、地球を大切にとか、地球に優しくと言っていますが、どんなに環境破壊が続いても、地球は地球であり続けます。私達は自分達を守るためにそう言っているに過ぎません。1000年先のことまで考えることはできませんが、せめて、自分たちの孫や曾孫に文句を言われないような地球を残さなければいけないのではないでしょうか。
構成・文:宮崎伸勝/写真:廣瀬真也(spread)