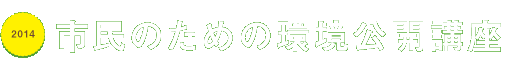日本の観光資源は世界の憧れ
 観光業は、少し前まで見下された産業だった。日本でもかつては、「モノづくりこそが産業であって、観光を推進する国は貧しく時代遅れな国」という印象が強かったのではないだろうか。しかしいま、観光は世界一の産業へと成長している。石油産業、自動車産業、IT産業を凌ぐ規模だ。時代遅れの小さな国はおろか、ニューヨーク、ロンドン、パリ、上海、香港など世界の大都市でさえ、経済に占める観光のシェアが増大中で、日本でも今後、観光が経済発展のカギの一つになることは間違いないだろう。
観光業は、少し前まで見下された産業だった。日本でもかつては、「モノづくりこそが産業であって、観光を推進する国は貧しく時代遅れな国」という印象が強かったのではないだろうか。しかしいま、観光は世界一の産業へと成長している。石油産業、自動車産業、IT産業を凌ぐ規模だ。時代遅れの小さな国はおろか、ニューヨーク、ロンドン、パリ、上海、香港など世界の大都市でさえ、経済に占める観光のシェアが増大中で、日本でも今後、観光が経済発展のカギの一つになることは間違いないだろう。
日本には観光資源が多くある。日本の棚田は、インドネシアのそれと比べても引けを取らない。緑豊富な森林もある。人の手によって築かれた、神社・仏閣、庭園などの文化もある。そして何より、旅館や温泉などを中心に「おもてなし」の文化がきちんと残っている。こうした精神文化は世界の人々の憧れでもある。
日本人特有の「古いものは恥ずかしい」という感覚
 しかしいま、日本の観光資源は、人口減少やそれに伴う過疎によって失われつつある。この課題に対し果敢に取り組み成功している事例がいくつかある。イタリアのトスカーナ地方、フランスのプロバンス地方、日本では北海道の小樽や九州の黒川温泉などだ。
しかしいま、日本の観光資源は、人口減少やそれに伴う過疎によって失われつつある。この課題に対し果敢に取り組み成功している事例がいくつかある。イタリアのトスカーナ地方、フランスのプロバンス地方、日本では北海道の小樽や九州の黒川温泉などだ。
地域再生に関しては、社会の仕組みをそのまま維持しようと企画した地域は失敗に終わり、地域の仕組みに観光産業をプラスするなど、現状をある程度転換させてきた地域は成功を手にする傾向があるようだ。成功例を手本にしてぜひ活性化させてほしいところだが、日本には特有の2つの問題が根底にあると感じている。
ひとつは、「古いものは恥ずかしい」という価値観だ。
それが如実に現れているのが観光ホテルだろう。旅行に行くと、パリのホテルでは、フランスらしさを象徴する建築物や調度品、家具が迎えてくれる。バンコクでも、ホテルの中庭は昔の寺院を思わせる佇まいで旅情を高めてくれる。しかし京都の某ホテルでは、エントランスがまるで結婚式場のような造りで、自分がどこを訪れているのかわからなくなってしまう。これは京都に限らず日本全体で起きている現象で、最近では駅舎なども、日本らしさ、地域らしさを失っている。「古いもの」を恥と感じるあまり、文化や地域性を無視し、「近代的」で「ピカピカ」したものに置き換えてしまった結果だ。
日本の土木は「犬と鬼」
 もうひとつの問題としてあげるのは、土建国家としての方向性だ。日本は、土木や建設業が他の先進国の約10倍という桁外れのスケールで肥大している。予算ありきの公共工事が、いまでも国土にコンクリートの擁壁をつくり続ける一方で、電線埋設といった難しい課題には目をつぶってきた。
もうひとつの問題としてあげるのは、土建国家としての方向性だ。日本は、土木や建設業が他の先進国の約10倍という桁外れのスケールで肥大している。予算ありきの公共工事が、いまでも国土にコンクリートの擁壁をつくり続ける一方で、電線埋設といった難しい課題には目をつぶってきた。
私の師匠だった白州正子さんの家の玄関口には、「犬馬難 鬼魅易」という言葉が飾られている。これは、「絵を描く際、創造物で派手な鬼は描きやすいが、身近で地味な犬や馬は意外に難しい」という意味だそうだ。私はそれを捩り『犬と鬼 知られざる日本の肖像』(講談社)という書籍を上梓したが、まさに日本の公共工事は犬(コンクリートの擁壁)と鬼(電線埋設)だと感じる。しかも、日本の国民はそのことに疑問を感じることもなく、抗議の声をあげる人もほとんどいない。
日本の観光は、よさを再認識することから
最後に、私が何をしているのか、話をしよう。私は子どもの頃に日本に来て、大学生になると日本1周をしながら桃源郷を探した。そこで出会ったのが徳島県の祖谷(いや)という地区である。
 祖谷は当時からすでに過疎で、誰も住んでいない古民家がゴロゴロしていた。そのひとつ、近隣道路から歩いて1時間かかる場所にある古民家を1973年に購入・改装し、「篪庵(ちいおり)」と名付けた。篪庵にはこれまで、見学等を含め累計3万人が訪れているが、その理由は、徹底して日本らしさを残しつつも、現代人が住まえるような現代技術を融合させた点にあると考えている。この考え方は、篪庵以降、日本各地で手掛けている事業においても一貫している。
祖谷は当時からすでに過疎で、誰も住んでいない古民家がゴロゴロしていた。そのひとつ、近隣道路から歩いて1時間かかる場所にある古民家を1973年に購入・改装し、「篪庵(ちいおり)」と名付けた。篪庵にはこれまで、見学等を含め累計3万人が訪れているが、その理由は、徹底して日本らしさを残しつつも、現代人が住まえるような現代技術を融合させた点にあると考えている。この考え方は、篪庵以降、日本各地で手掛けている事業においても一貫している。
たとえば、茅葺き屋根はそのままに、見えないところにしっかりと防水シートを入れる。300年以上前から使われてきた黒光りした梁や壁板、床板の下には断熱材を入れ、あたたかさを確保する。窓は二重ガラス、冷暖房はもちろん完備だ。照明は、器具が直接見えない位置に埋め込み、特に水回りは快適さを保てるよう気を配っている。
 しかし、1軒だけが景観や文化を意識したところで、観光資源として成り立たせることは難しい。祖谷は日本三大秘境として知られる場所で、平家落人の逸話も多く残る。その風情を感じる苔むした林道も財産のひとつだ。そんな林道に、「危険だから」という理由でコンクリートの法面ができた。旅情も何もあったものではない。地域全体の景観を守っていくには行政の力も必要だ。近年は京都市で景観条例が施行された。先進国のそれに比べて未熟な内容だが、大きな一歩として期待している。
しかし、1軒だけが景観や文化を意識したところで、観光資源として成り立たせることは難しい。祖谷は日本三大秘境として知られる場所で、平家落人の逸話も多く残る。その風情を感じる苔むした林道も財産のひとつだ。そんな林道に、「危険だから」という理由でコンクリートの法面ができた。旅情も何もあったものではない。地域全体の景観を守っていくには行政の力も必要だ。近年は京都市で景観条例が施行された。先進国のそれに比べて未熟な内容だが、大きな一歩として期待している。
過疎が進む一方だった祖谷では現在、若者の移住が増えている。彼らはそこで、農業や林業ではなく、デザインや観光業などでホスピタリティービジネスを展開している。結婚して子どもをもうけた人たちもいる。
日本には本当にすばらしい観光資源が残されている。それを活かせるかどうかは、日本人が、そのよさをどれだけ再認識できるかにかかっている。
構成・文:中島まゆみ/写真:黒須一彦(エコロジーオンライン)