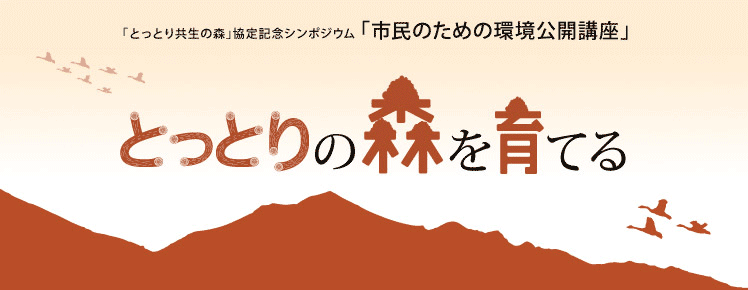13:00開会挨拶
 本日は、多数の方にご参加頂きまして誠にありがとうございます。損保ジャパンは色々なCSRに取組んでおりまして、主に美術や文化に対する活動と地球環境問題に関する取組みがあります。まず美術については、当社は古くから東郷青児画伯と縁がありまして、昭和51年に新宿の本社ビルを造る時に東郷画伯から205点の作品を寄贈頂き、42階に東郷青児美術館を設置致しました。また1989年、当社が創業100周年の時には、ゴッホの「ひまわり」をはじめとする名画を展示するなどして、以来最近では修学旅行で東京に来る小中学生などの見学も増え、年間16万人を越える方々にご来館頂く一方、毎年のイベントや東郷美術館大賞、奨励賞などを出して、美術文化活動に取組んでいます。
本日は、多数の方にご参加頂きまして誠にありがとうございます。損保ジャパンは色々なCSRに取組んでおりまして、主に美術や文化に対する活動と地球環境問題に関する取組みがあります。まず美術については、当社は古くから東郷青児画伯と縁がありまして、昭和51年に新宿の本社ビルを造る時に東郷画伯から205点の作品を寄贈頂き、42階に東郷青児美術館を設置致しました。また1989年、当社が創業100周年の時には、ゴッホの「ひまわり」をはじめとする名画を展示するなどして、以来最近では修学旅行で東京に来る小中学生などの見学も増え、年間16万人を越える方々にご来館頂く一方、毎年のイベントや東郷美術館大賞、奨励賞などを出して、美術文化活動に取組んでいます。
もうひとつの地球環境問題については、リオデジャネイロで地球環境サミットが開催された1992年に「地球環境室」を作りまして、保険・金融サービスを通じた環境問題への貢献、そして環境問題に積極的に取組める人を育てることに力を入れています。木を植えることも大切ですが、「木を植える人を育てる」ことをモットーに、日本環境教育フォーラムとの共催で「市民のための環境公開講座」を16年前からスタートしています。また一方、地域の森づくりの支援ということで当社の社員や代理店の皆さんと地域の環境保全に取組んでおり、高知県、香川県、三重県に続いて、2007年12月に鳥取県の「とっとり共生の森」に参画することになり、今年2008年11月から保全活動を始めることになりました。
当社としては鳥取県に非常に強い想いがございます。当社の前身は「東京火災」という日本で最初の火災保険会社でございますが、その土台を築いたのが、明治時代に当時の東京府知事であった松田道之さんという人物で、この方は旧鳥取藩士でありました。また、当社設立の発起人の総代になられたのが鵜殿久さんで、この方は旧鳥取藩の家老であります。なお現在においても、当社は鳥取県において損保業界で一番の支援を受けておりまして、こういったことからぜひ鳥取でシンポジウムをやりたいという想いが長くございました。
このような経緯で開かれる今回のシンポジウムが、ぜひ皆さんにとって意義あるものとなることを祈念致しまして、開催の挨拶とさせて頂きます。
県知事挨拶
 本日は、このシンポジウムに多数の方に来て頂き、誠にありがとうございました。本日のこの会は、損害保険ジャパンのご尽力により実現したものであります。関係者の方に心より感謝を申し上げたいと思います。
本日は、このシンポジウムに多数の方に来て頂き、誠にありがとうございました。本日のこの会は、損害保険ジャパンのご尽力により実現したものであります。関係者の方に心より感謝を申し上げたいと思います。
今回のシンポジウム開催に至りましたのは、先般同社が「とっとり共生の森」に参画し、鳥取県とを協定を結んだことがきっかけとなりました。今、福澤本部長のご挨拶にもありました通り、損害保険ジャパンという会社は鳥取県と浅からぬ関係がございます。旧鳥取藩士の松田道之という方は、明治元年から明治政府に執事して要職を歴任しました。大久保利通に見込まれ、鳥取から明治維新、そして日本の国を作るということに尽力した一人であります。その松田道之が東京府知事に就任したわけですが、その直後に日本橋で大火がありました。その火災を見て、「日本も、西欧でやっている火災保険というものを導入しなければならない」と、当時の大蔵省に掛け合い、実現したわけです。損害保険ジャパンの前身「東京火災」の出資者は全て旧鳥取藩士の方々で、家老家の血筋だった鵜殿久さんが総代を務め、また初代社長ももちろん旧鳥取藩士の方でした。
鳥取県は年間4000haを越える広大な森林整備を行おうとしています。CO2の削減が各方面で求められている今、鳥取県の場合にはこの森林整備が鍵になると言って差し支えないと思います。皆様のご協力を頂き、森林環境保全税を毎年頂いておりますが、これと従来からの助成なども含めて森林整備活動に役立てています。ただ難しいのは、山や水というものはそれだけでは採算がとれないものになってきております。しかし状況も変わってきており、ロシアからの輸入木材は関税がかかるようになってくるものですから、今後相場が動くようになります。私は今こそ、山がもう一度蘇るチャンスなのではないかと思います。ぜひこの機会に皆様にも森林に対する関心を深めて頂き、みんなの力で鳥取から新しい環境推進運動が始まるきっかけになればと考えております。かつて松田道之先生は、東京の火災を見るにつけこの街を守ろうとしました。今私達が守らなければならないのは、自然環境、地球であるという時代になってきたと思います。今こそ、鳥取藩士の後進者である私達が地球を守るパイオニアとしての役割を担うことができればと思います。

基調講演
 今、里山が荒れています。それに対し、里山を復元・再生しようという声が全国的に高まっています。ではなぜ里山を復元するのか?その理念をきちんと持つために、里山とは我々にとって何なのかを改めて考えてみる必要があるのではないでしょうか。
今、里山が荒れています。それに対し、里山を復元・再生しようという声が全国的に高まっています。ではなぜ里山を復元するのか?その理念をきちんと持つために、里山とは我々にとって何なのかを改めて考えてみる必要があるのではないでしょうか。
まず具体的な例で考えてみましょう。近年、野生動物による被害が全国的に非常に高まっています。私はこれを「野生の反乱」という言い方をしていますが、シカ、サル、ウマ、イノシシなどの事例がよく聞かれます。また、近年クマが里に出てくることもありますが、こんなことは以前はないことでした。因みに、一昨年は全国で約5000頭余のクマが捕獲され、そのほとんどが殺されました。なぜこういうことが起こるのでしょうか。その要因は3つ考えられます。 (1)里山が崩壊した (2)野生動物が増えた (3)野生動物の保護・管理の行政対応が貧困である ...特に日本の野生動物に対する行政の対応はマレーシア、タイ、ケニアなどの国に比べても非常に遅れていると言わざるを得ません。
ところで里山は薪炭林とも言われます。人間は火がなければ生きていけません。そのためのエネルギー源である薪などを取ってくるための場所が里山だったからです。そして田畑の肥料に使う植物もここから取りました。キノコ類や山菜など季節ごとの食料も採れました。木は建築材として使われ、また生活の様々な場面で使われていた竹も里山にありました。ところが昭和30年代半ばから石油・電気・ガスを使う生活が一般的になり、農家も化学肥料や除草剤を使い、これに少子高齢化も伴い、里山が放置されるようになってしまいました。里山は国土の約20%を占めると言われています。農地が全部で約16%ですから、それより多い土地が放置されているのです。
 その一方で、野生動物は戦争中の食べ物がなかった時代に乱獲されており、戦後これを増やそうという動きが起こり、次第に増加していきました。さらに誰も気がつかないうちに一気に野生動物が増えるきっかけとなったのが、実は「植林」です。植林には色々な方法がありますが、そのひとつに「皆伐」という方法があります。その場所に生えている植物を一度全部伐ってしまって、その後に植えていくものです。これはとても手っ取り早く、苗木を植えやすい方法でしたが、このためにとんでもないことが起こりました。シカ、サル、クマのような動物達から見れば、それは食べ物がいっぱいある牧場を作ったようなものだったのです。こんな環境の下で動物達が激増していきました。しかし、その後弱い木を間引いて、日光を中に入れ、生えてくる下草を刈るなどの手入れが行われず、多くの森が薄暗く下草も生えない状態となり、動物達の棲めない場所になってしまいました。
その一方で、野生動物は戦争中の食べ物がなかった時代に乱獲されており、戦後これを増やそうという動きが起こり、次第に増加していきました。さらに誰も気がつかないうちに一気に野生動物が増えるきっかけとなったのが、実は「植林」です。植林には色々な方法がありますが、そのひとつに「皆伐」という方法があります。その場所に生えている植物を一度全部伐ってしまって、その後に植えていくものです。これはとても手っ取り早く、苗木を植えやすい方法でしたが、このためにとんでもないことが起こりました。シカ、サル、クマのような動物達から見れば、それは食べ物がいっぱいある牧場を作ったようなものだったのです。こんな環境の下で動物達が激増していきました。しかし、その後弱い木を間引いて、日光を中に入れ、生えてくる下草を刈るなどの手入れが行われず、多くの森が薄暗く下草も生えない状態となり、動物達の棲めない場所になってしまいました。
すると動物達は棲める所へと移動をします。通常サルは群れを作って、一定期間そこに留まる「行動域」を持つというのが定説です。ですから、食べられる場所に移動しないと意味がありません。そこで次第に山から人里へと近づくようになります。そこで人間の作ったサツマイモにすっかり味をしめ、それを狙うようになります。驚いたのは、宮城県で30km移動したサルの群れがいたことです。一般的にこんなことは考えられず、いかにサルが切羽詰まっているかが分かります。
 またクマは奥山に住み、本来は人間が恐いものだということを知っているため、人間の姿が見える里山からは距離をおいて暮らす動物でした。ところが人間が里山から撤退したため、クマが里山に近づくようになり、そこで子供を産生みます。するとその子供は人間が恐いということを知らないまま育ち、行動するようになります。最近捕まっているのが大体は若いクマだというのは、こういう理由ではないでしょうか。里山は人間と動物の入会地であったのが、今は動物の領地になってしまった、というのが現状なのです。
またクマは奥山に住み、本来は人間が恐いものだということを知っているため、人間の姿が見える里山からは距離をおいて暮らす動物でした。ところが人間が里山から撤退したため、クマが里山に近づくようになり、そこで子供を産生みます。するとその子供は人間が恐いということを知らないまま育ち、行動するようになります。最近捕まっているのが大体は若いクマだというのは、こういう理由ではないでしょうか。里山は人間と動物の入会地であったのが、今は動物の領地になってしまった、というのが現状なのです。
里山に関して言うと、先程もお話しした通り国土の20%が遊んでいる状態となっており、これは国家として大変な損失です。では、里山とはどのような役目を持っているものなのでしょうか。ひとつは「生産資源」としての役割です。薪炭林であり、建築材や食料などの供給源でもあります。また「環境資源」としての側面もあります。保水、防風、空気浄化などの作用を持ち、CO2の重要な吸収源であり、生物多様性を維持していくための場でもあります。そしてもうひとつの重要な役割が、「文化資源」としての側面です。
これを日本人は長い間活用してきませんでした。この3つの観点から「21世紀の里山」を再生することが必要です。里山とは、人間にとって役立つように維持管理する低い山のことですが、特に、文化林としての新たな設計が必要な時代になっているのです。
林学者・北村昌美氏の「日本とヨーロッパの森林観の違い」という調査によると、『深い森に遊びに行くかどうか』という問いに対して、ドイツ人の60%近くが『行きたい』と答え、日本人は2%以下でした。「森へ遊びに行く」という風習が日本にはないのです。そこで私は「森遊び」を提唱しています。この「森遊び」とは何か?
 「川遊び」は比較的一般的で、日本では川という自然を利用して、社会システムから水泳や屋形船といった娯楽まで非常に多くの文化を作り上げました。これと同じように森という自然を舞台にして、カルチャー、レクリエーション、スポーツ、エデュケーションの4つの軸を発達させていこうというのが「森遊び」の考え方です。世界的に有名なウィーンの森は1250km2もの広さがあり、その中に大きな湖、集落、畑、教会などが点在しています。そんな場所に設置された林道を実にたくさんの人が歩いています。ドイツのシュヴァルツバルトの森でも、多くの人々がリュックを背負い、自転車などを持ち込んで森の散策を楽しんでおり、また多数のご老人が歩いているのも見受けられました。
「川遊び」は比較的一般的で、日本では川という自然を利用して、社会システムから水泳や屋形船といった娯楽まで非常に多くの文化を作り上げました。これと同じように森という自然を舞台にして、カルチャー、レクリエーション、スポーツ、エデュケーションの4つの軸を発達させていこうというのが「森遊び」の考え方です。世界的に有名なウィーンの森は1250km2もの広さがあり、その中に大きな湖、集落、畑、教会などが点在しています。そんな場所に設置された林道を実にたくさんの人が歩いています。ドイツのシュヴァルツバルトの森でも、多くの人々がリュックを背負い、自転車などを持ち込んで森の散策を楽しんでおり、また多数のご老人が歩いているのも見受けられました。
日本は世界に誇る自然の美しい国ですが、ある意味自然が豊かすぎるのかもしれません。ドイツ人やフランス人があれだけ森が好きだというのは、実は昔からそうだった訳ではありません。かつてヨーロッパでは耕作地や牧地の開拓で、多くの平地の森がなくなり、17世紀の終わりには本当に少なかったそうです。このために洪水などの災害が頻発し、そうしたことから自然保護の思想が生まれたのです。
日本人と自然の付合いは、盆栽や庭、生け花などを見てもわかる通り、自然から色々な実を取ってくることにより繊細で鋭敏な、新たな美の世界を造形する文化をもたらしました。私はその感性をぜひ大自然の中でも解き放ってほしいと願っています。森は植物の塊だというのが日本人のイメージですが、ヨーロッパでは、森の中にも美術館があり、小鳥がさえずる場所となっています。このように、多くの人々が楽しめる森が我が国でもどんどん積極的につくられ、森で遊ぶ人が増えていくことを期待しています。

14:20パネルディスカッション
 私は東京都あきるの市で代々林業を営む家に生まれ、父の後を継いで30年間林業を手掛けてきました。180haという決して大きくない林地です。林業は今とても「業」として立ち行かない状況ですけれども、経済的なことを考えなければ私は林業ぐらい面白い仕事はないと思っています。
私は東京都あきるの市で代々林業を営む家に生まれ、父の後を継いで30年間林業を手掛けてきました。180haという決して大きくない林地です。林業は今とても「業」として立ち行かない状況ですけれども、経済的なことを考えなければ私は林業ぐらい面白い仕事はないと思っています。
東京の林業について少しお話ししますと、東京の森林面積は全面積の1/3もあります。江戸に材を出すという便利な面もあった一方、急峻で岩山が多く、何よりも所有が細分化されているため林道が作りにくいという難しい面もあります。そして交通が発達したため、仕事を求めて東京に出て行けるようになり、作業員も激減し、林業不況が一番先にやってきた地域ではないかと思っています。多くの人が山に背を向け、街を向いているため、街道沿いや林道沿いの森林はまだ少しは手が入っても、奥の方は全く手が入らず、人も動物も入りたくないような薄暗いゴースト森林になってしまいました。
15年前、そんな森林に3人のボランティアグループがきてくれるようになったのを皮切りにずっと活動が続き、現在ではいくつかのグループが森を育てる仕事を手伝ってくれています。具体的には、秋冬の枝打ちや夏の下草刈りなどの作業をして頂いています。
ボランティアの方達がどうしてこのように継続的にお手伝いしてくれるのかと思うのですが、お話を聞くところによると、枝打ちなどをした後に木漏れ日が差し込むのを見ると仕事の達成感があるとか、街から離れて山に入ると異次元の世界で心が開放されて癒されるといったことが魅力となっているようです。
 ボランティアの方々に森林整備に参加してもらうことの利点は、何と言っても無償で大変な量の仕事をこなしてくれることに尽きますが、他にも、若い女性に道具の使い方などを尋ねられながら一緒に作業をすることで作業員のおじさんが元気を取り戻したり、色々な所で見聞を広めてきたボランティアの方に私自身も却って教えられたり、励まされてきました。また、このように無償で働く人々を見て、地域の中にも、「私も自分の山があるんだから、ちょっと入ってみよう」と心を動かされ、放置していた自分の森林を手入れする人も出てきました。さらに、ボランティアの中には林業家としてプロ化・セミプロ化した人や、最も突出した例としては「東京の木で家を作る会」を立ち上げた人も現れました。数え切れないほどの森林ボランティア存在効果がありました。また、このような動きは、全国的に同様の活動が広まってきた先駆けともなりました。
ボランティアの方々に森林整備に参加してもらうことの利点は、何と言っても無償で大変な量の仕事をこなしてくれることに尽きますが、他にも、若い女性に道具の使い方などを尋ねられながら一緒に作業をすることで作業員のおじさんが元気を取り戻したり、色々な所で見聞を広めてきたボランティアの方に私自身も却って教えられたり、励まされてきました。また、このように無償で働く人々を見て、地域の中にも、「私も自分の山があるんだから、ちょっと入ってみよう」と心を動かされ、放置していた自分の森林を手入れする人も出てきました。さらに、ボランティアの中には林業家としてプロ化・セミプロ化した人や、最も突出した例としては「東京の木で家を作る会」を立ち上げた人も現れました。数え切れないほどの森林ボランティア存在効果がありました。また、このような動きは、全国的に同様の活動が広まってきた先駆けともなりました。
 昭和43年に広島で高校総体がありました。その時、山岳競技は大山でやってほしいという要請があり、1年前からコース整備に入りました。ところが頂上はゴミの山と化していました。そこで、頂上のゴミ籠をすべて撤去し、「ゴミの持ち帰り運動」を実施し、広く登山者一人一人に呼びかけ、協力してもらいました。これらの活動により、大会自体は無事に終わりましたが、こんな状態では折角の大山がだめになってしまうと思い、44〜46年に県内高校の山岳部の生徒達と夏休みの間1週間ずつ交替で合宿をし、ゴミの除去作業に取組んだ他、登山人口とゴミの関係について調査をしました。同時に農業高校の生徒と一緒に大山の植生調査も行い、植物分布図を作成しました。そして、これをきっかけに45年に「大山の自然を守る会」を結成し、運動を進めていきました。
昭和43年に広島で高校総体がありました。その時、山岳競技は大山でやってほしいという要請があり、1年前からコース整備に入りました。ところが頂上はゴミの山と化していました。そこで、頂上のゴミ籠をすべて撤去し、「ゴミの持ち帰り運動」を実施し、広く登山者一人一人に呼びかけ、協力してもらいました。これらの活動により、大会自体は無事に終わりましたが、こんな状態では折角の大山がだめになってしまうと思い、44〜46年に県内高校の山岳部の生徒達と夏休みの間1週間ずつ交替で合宿をし、ゴミの除去作業に取組んだ他、登山人口とゴミの関係について調査をしました。同時に農業高校の生徒と一緒に大山の植生調査も行い、植物分布図を作成しました。そして、これをきっかけに45年に「大山の自然を守る会」を結成し、運動を進めていきました。
昭和38年に大山には有料観光道路が完成し、別荘地も開発されたため、登山人口が急増しました。毎日数百人が登るようになると、あっという間に山の植物が踏み荒らされてしまいました。生命力の強いオオバコだけが残り、オオバコの群落が頂上一面にできましたが、最終的にはそのオオバコも絶やされてしまいました。
 ハゲ山のむき出しになった土は大雨が降ると流れ出し、その土は下の溝口町の方まで流れて行くようになり、ようやく当時の環境庁が頂上の保全に乗り出しました。その頃私達も、侵食溝をつくらないよう、等高線に数段の丸太筋工法を実施し、降雨水を均等に分散させる基盤工事を行いました。また、関係機関の許認可を受けて大山に圃場を作り、株分けによる栽培実験を始めました。木本ではダイセンキャラボクとヤマヤナギ、草本ではヒトツバヨモギとヒゲノガリヤスの4種類に限定し栽培を始め、2年ほどでこれらが100%活着したのです。ここまで達成するためには多くの難問を切り抜けてきました。
ハゲ山のむき出しになった土は大雨が降ると流れ出し、その土は下の溝口町の方まで流れて行くようになり、ようやく当時の環境庁が頂上の保全に乗り出しました。その頃私達も、侵食溝をつくらないよう、等高線に数段の丸太筋工法を実施し、降雨水を均等に分散させる基盤工事を行いました。また、関係機関の許認可を受けて大山に圃場を作り、株分けによる栽培実験を始めました。木本ではダイセンキャラボクとヤマヤナギ、草本ではヒトツバヨモギとヒゲノガリヤスの4種類に限定し栽培を始め、2年ほどでこれらが100%活着したのです。ここまで達成するためには多くの難問を切り抜けてきました。
台風や突風、霜などに度々見舞われる気象条件の厳しい頂上での活動は、無に帰せられることの繰り返しで、それを少しでも改良するために新しい工法を次々に発案して実証を続けてきました。また、頂上にヘリコプター空輸した土砂の量は4年間に土嚢5080袋、101.6トンに及ぶ大変な作業でした。
このような経験を経て大山には緑が戻ってきた訳ですが、これは人工的に植えた緑であって、決して昔の大山の植生ではありません。これからいかにして昔の植生に戻すかという課題に向けて、体が続く限り取組んでいきたいと思っています。
 アファンの森は、長野県の北部、野尻湖の近くある17.7haの森です。C.W.ニコルは、なぜアファンの森をつくったのかという問いに対して必ずこう答えています。「僕は日本の豊かな森に救われたんだよ。だから恩返しをしているのです」。
アファンの森は、長野県の北部、野尻湖の近くある17.7haの森です。C.W.ニコルは、なぜアファンの森をつくったのかという問いに対して必ずこう答えています。「僕は日本の豊かな森に救われたんだよ。だから恩返しをしているのです」。
きっかけは彼の故郷・ウェールズの森が再生したことからでした。ウェールズは、石炭で富を得た国だったのですが、その代わりに山という山は全部伐られてしまい、石炭のカスがそこら中にまき散らされたハゲ山になっていました。ある時、石炭が掘られた後のハゲ山に大雨が降って鉄砲水が起こり、下流にある小学校を丸呑みしたという大事件が起こりました。それ受けて3人の小学校の先生が、「子供達の未来を教えるために」を合言葉に、バケツ一杯の土と苗木1本を持って山に植えようという運動を始めたそうです。後に、ウェールズは豊かな森林を取り戻しました。ニコルはその現場を見て、自分もやろうと思い立ったのが「アファンの森」でした。
現在アファンの森がある場所は、元々は国有林でしたが、戦後に開拓地として民間林となりました。一時期はいわゆる薪炭林として地域で活用されていたのですが、やがて放置され、荒れた林となってしまい、人はおろか動物も寄り付かない「幽霊森」となってしまいました。そこに青い目をした大柄な男が出入りをし始めたので、当初は何をしているのかと地元の人々に相当怪しまれたそうですが、ニコルは「それでも豊かな森が必要なのだ」と言ってその放置林の中に入り続けました。
 私達はもともと、人のためではなく生き物のために森づくりをしてきました。森づくりの基本方針として掲げているのは、「生物の多様性(DIVERSITY)」、そして色々な恵みを森から貰おうという「森の生産性(PRODUCTIVITY)」、さらに「生きものたちの共生(BALANCE)」という3つです。これを1986年から現在まで意識して取組んできた結果、植物・約483種、菌類・約343種、哺乳類・約15種、鳥類・約70種、両生類・7種が現在までに確認されるようになりました。この森に手を入れたのは私達ですが、森をつくっているのはこれらの生き物全てだと考えています。
私達はもともと、人のためではなく生き物のために森づくりをしてきました。森づくりの基本方針として掲げているのは、「生物の多様性(DIVERSITY)」、そして色々な恵みを森から貰おうという「森の生産性(PRODUCTIVITY)」、さらに「生きものたちの共生(BALANCE)」という3つです。これを1986年から現在まで意識して取組んできた結果、植物・約483種、菌類・約343種、哺乳類・約15種、鳥類・約70種、両生類・7種が現在までに確認されるようになりました。この森に手を入れたのは私達ですが、森をつくっているのはこれらの生き物全てだと考えています。
そんなアファンの森では現在、「森の再生」「心の再生」「普及交流」という3つの柱で活動をしています。トラスト活動で土地を広げて、整備をし、生物調査により評価をする...という森の再生事業に加え、児童養護施設の子供達や盲学校に通う子供達を森に招いて、彼らの心を育む活動をしています。森で遊ぶ彼らの表情、彼らが森について描く絵には、いつも感動させられています。
豊かな森で豊かな心が育まれ、その子供達が将来豊かな社会を築き、そんな豊かな社会にはきっと豊かな森が溶け込んでいるだろうということを思い描きながら、私達はアファンの森での活動を続けています。
 今、森林の価値が盛んに問われています。例えば、これまで森林というと林業という木材の「生産」の場として考えられてきましたが、現代の我々にとっては、そのこと以上に色々な形で森林が生活に関わっていることが指摘されるようになってきました。
今、森林の価値が盛んに問われています。例えば、これまで森林というと林業という木材の「生産」の場として考えられてきましたが、現代の我々にとっては、そのこと以上に色々な形で森林が生活に関わっていることが指摘されるようになってきました。
皆様もご存知のように、日本でもかなり気候変動が起こり始めており、気象庁の観測箇所の平均値がこの100年で1.1℃上昇しています。これに対して、今後許容可能な温度上昇は2 ℃が限度だと言われています。つまり、気温上昇を最低限に抑えるためには、CO2の濃度を475ppmに抑える必要があると言われており、それを実現するためには2050年までに今の状態から50%削減しなければならないことになります。これに対して森林は重要な役割を担っているのです。
地球上の炭素がどのように循環しているかを解析してみると、化石燃料を使うことで発生する炭素は、大気中に貯まり、その一部分は陸地つまり森林と海が吸収します。極端に単純化すれば、炭素の総排出量を「4」としたら、大気中に「2」貯まり、陸と海にそれぞれ「1」ずつ吸収されると考えられています。現在分かっているデータでは、大気に貯まっているCO2濃度が約380ppmで、1年間に大体1.5〜1.6ppmの増加を示しています。これだけ見ても、475ppmという数値目標も大変差し迫ったものと言えるのではないでしょうか。
 ところで、植物のCO2吸収量を測定する場合、植物が実際に吸収している量と、同時に植物自体が排出しているCO2と土壌が排出しているCO2を差し引きします。この方法で国立環境研究所地球環境研究センターが2001〜2003年に北海道・苫小牧のカラマツ林で観測したところ、大体1年間で1ha当たり炭素量として2t前後が吸収されていることが分かりました。このことからもCO2吸収における森林の働きが大きいことがわかります。
ところで、植物のCO2吸収量を測定する場合、植物が実際に吸収している量と、同時に植物自体が排出しているCO2と土壌が排出しているCO2を差し引きします。この方法で国立環境研究所地球環境研究センターが2001〜2003年に北海道・苫小牧のカラマツ林で観測したところ、大体1年間で1ha当たり炭素量として2t前後が吸収されていることが分かりました。このことからもCO2吸収における森林の働きが大きいことがわかります。
しかし、森林と言っても世界中に様々な種類の森林があり、点でデータをとっているだけではあまり意味がありません。色々な地域の繋がりで面としてのデータに統合することによって、地球全体におけるCO2吸収量を評価することができるのです。他の分野でも全て同じことですが、やはり地球環境を考える場合には国際的な連携を進めていかなければいけないと思います。
森林の機能というのはまだまだ分かっていないことが多く、それを解析することが我々の使命であり、それによって本日発表された他のパネリストの皆様のような活動に科学的に貢献できたらと考えております。
パネルディスカッション
- 池谷 キワ子氏林業家、NPO法人森づくりフォーラム理事
- 乾 刻弘氏大山の頂上を保護する会副会長
- 河西 恒氏(財)C.W.ニコル・アファンの森財団事務局)
- 藤沼 康実氏鳥取環境大学研究交流センター教授
- コーディネーター岡島 成行(社)日本環境教育フォーラム理事長
 岡島 まず、皆さんの活動の中で困った事や問題点などをお聞きしたいと思います。
岡島 まず、皆さんの活動の中で困った事や問題点などをお聞きしたいと思います。
池谷 市民ボランティアの人数が中々増えないことですね。林野庁などから補助金も頂くのですが、やはりそれだけで賄うことは難しいです。森を作るためには、装備や道具など色々とお金がかかります。また安全面において思いがけないことが起こります。できるだけ事故が起きないよう充分な準備ができる予算は欲しいと思っています。また、真夏に作業を手伝ってもらった時にシャワーも浴びずに汗だくで電車に乗って帰って頂かなくてはならないことや、山にトイレがないなどの問題も、ボランティアを迎える場合には解決していかなくてはならないことだと思います。
乾 大山の場合は、活動するために頂上まで登ってもらわなくてはならず、それがまず大変です。また、ボランティア指導もあまり丁寧にやっていては却って仕事にならず、後継者の育成なども大きな問題として考えています。
 河西 最も大きな問題はニコルのパートナーで、森の管理を一手に引き受けている松木の後継者がいないということです。あれだけ森の手入れができて、且つ生き物の知識に明るいという人物はなかなかいません。また、「豊かな森だからこそ豊かな心が育まれる」という考えの元、子供達を森に招いていますが、彼らの心が豊かになったということをどう評価するかというのが難しい部分です。それから会員を集めるための広報についても、一般企業に比べると知識が少ないので、企業と人材やノウハウの交換が出来たらいいですね。
河西 最も大きな問題はニコルのパートナーで、森の管理を一手に引き受けている松木の後継者がいないということです。あれだけ森の手入れができて、且つ生き物の知識に明るいという人物はなかなかいません。また、「豊かな森だからこそ豊かな心が育まれる」という考えの元、子供達を森に招いていますが、彼らの心が豊かになったということをどう評価するかというのが難しい部分です。それから会員を集めるための広報についても、一般企業に比べると知識が少ないので、企業と人材やノウハウの交換が出来たらいいですね。
 藤沼 私は1週間前に茨城から鳥取に移ってきたばかりですが、茨城には日本で2番目に大きな霞ヶ浦という湖があります。しかし、意外に地元の人はあまり行ったことがなく、その現状を知らないのです。ですから森も、もっと人々が入っていくチャンスをつくれば、森を見直すきっかけになるのではないでしょうか。
藤沼 私は1週間前に茨城から鳥取に移ってきたばかりですが、茨城には日本で2番目に大きな霞ヶ浦という湖があります。しかし、意外に地元の人はあまり行ったことがなく、その現状を知らないのです。ですから森も、もっと人々が入っていくチャンスをつくれば、森を見直すきっかけになるのではないでしょうか。
岡島 「人を呼び込む」という点に関して意見が揃って出ましたが、それぞれ工夫している点はありますか?

池谷 ボランティアを指導するリーダー的なボランティアが育っていかないという問題点があります。そこで私達「NPO法人森づくりフォーラム」は「森林施業ガイドライン」を作成し、ボランティアが作業をする時の指針や基準を示しました。また、森づくりの技術を平準化して技能を客観的にマスターできる「技術習得制度」を立ち上げました。これらの仕組みによってボランティアの技術を上げ、安全性を高めていきたいと考えています。
岡島 鳥取で活動する場合も、鳥取に即したガイドラインを作るといいかも知れないですね。
河西 私達が行っている児童養護施設や盲学校の子供達を招待する取組みは、環境教育に福祉の視点を加えるというのが始まりでした。最近森林療法が全国に広まっていますが、森を保養地とも捉えて、車椅子の方も森の中で動けるように整備するなど、福祉の要素を加えたら、双方の道が繋がりやすくなるのではないでしょうか。
岡島 先程の発表の中で言い足りないことがあればどうぞ。
 池谷 私は、山の位置関係や植生などを示した手書きの地図を作り、来てくれた人への案内や、昔の人がどのように森の恵みとともに生活していたかを説明する資料として使っています。これからは林業家も、森を「木材生産」だけなく、遊んだり学習する場として認識し、一般の人々への見せ方を工夫していくことが大切だと思います。プロの林業家も、プロの林業家や作業員はそういう感覚を持って山を管理することが必要です。単にいい木材が採れればいいということではなく、森林という数少ない日本の資源を有効に活用し、広い意味での林業に取組んで、税金をあまり使わずに、自力で山からお金を生み出す仕組みをつくることが、いい山を将来に残すことに繋がるのではないかと考えています。
池谷 私は、山の位置関係や植生などを示した手書きの地図を作り、来てくれた人への案内や、昔の人がどのように森の恵みとともに生活していたかを説明する資料として使っています。これからは林業家も、森を「木材生産」だけなく、遊んだり学習する場として認識し、一般の人々への見せ方を工夫していくことが大切だと思います。プロの林業家も、プロの林業家や作業員はそういう感覚を持って山を管理することが必要です。単にいい木材が採れればいいということではなく、森林という数少ない日本の資源を有効に活用し、広い意味での林業に取組んで、税金をあまり使わずに、自力で山からお金を生み出す仕組みをつくることが、いい山を将来に残すことに繋がるのではないかと考えています。
 乾 大山の作業は、頂上に登ること自体が大変なので、3班のグループ編成で取組んできました。1班は前日に登って準備をします。2班は朝から登って11時半くらいに頂上に着くので、食事をしてから午後3時までの3時間位しか作業ができません。3班は、他の班が下山した後の午後4時から8時までの4時間と翌朝6時から10時までの合計8時間仕事をするという方式です。その他にも、霜柱で栽培した植物が枯れてしまうこともしばしばで、その度にコモ伏せなど様々な工夫をしてきました。このように苦労話は山ほどあります。
乾 大山の作業は、頂上に登ること自体が大変なので、3班のグループ編成で取組んできました。1班は前日に登って準備をします。2班は朝から登って11時半くらいに頂上に着くので、食事をしてから午後3時までの3時間位しか作業ができません。3班は、他の班が下山した後の午後4時から8時までの4時間と翌朝6時から10時までの合計8時間仕事をするという方式です。その他にも、霜柱で栽培した植物が枯れてしまうこともしばしばで、その度にコモ伏せなど様々な工夫をしてきました。このように苦労話は山ほどあります。
藤沼 文部科学省が、子供達の科学への興味を増進することを目的とし、サイエンスキャンプという合宿を実施しているのですが、私どもが森林をフィールドとして開催したところ、森林自体に入ったことのない子供達もたくさんいました。やはり今後は色々な形で森林を体験してもらうことが重要だと思います。
岡島 ご来場の皆さんの中で質問がある方はいますか?来場者 ボランティアを集めて作業する上で、万が一のケガにはどういう備えをしていますか?
池谷 私どもの山でボランティアに来て下さる方には全員、社会福祉協議会のボランティア保険に加入してもらっています。どんなに用心してもやはりケガはあるので保険は絶対に必要です。電動工具も最近は色々と発達して効率もいいのですが、事故がおきる危険性を考えると、ボランティアの人は使わない方がいいのではないかと思っています。
 岡島 自然の中で遊ぶことには必ず危険が伴い、指導者の責任が問われます。日本の場合、自己責任の概念がまだまだ徹底していないので、裁判沙汰になればほとんどの場合負けてしまいます。ですから、そのようなことまで考慮して、様々な事態に耐え得るような指導体制の確立、事前のマニュアルづくり、事故の発生状況をキチンと世間に説明できる体制などが必要になってきます。日本人は、まだ他人の指導のもと自然体験をするようなことに馴れていないので、何かおこるとすぐ人にせいにしたがる風潮があります。そのような風土も併せて築いていくことも今後の課題であろうかと思います。また、指導者育成などのソフト面の充実をさせることが、森づくりに取組むNGO・NPOにとっても重要です。鳥取でも、本日話題に上った様々な視点から森づくりに取組み、地元の森をいい森に変えていっていただきたいと思います。
岡島 自然の中で遊ぶことには必ず危険が伴い、指導者の責任が問われます。日本の場合、自己責任の概念がまだまだ徹底していないので、裁判沙汰になればほとんどの場合負けてしまいます。ですから、そのようなことまで考慮して、様々な事態に耐え得るような指導体制の確立、事前のマニュアルづくり、事故の発生状況をキチンと世間に説明できる体制などが必要になってきます。日本人は、まだ他人の指導のもと自然体験をするようなことに馴れていないので、何かおこるとすぐ人にせいにしたがる風潮があります。そのような風土も併せて築いていくことも今後の課題であろうかと思います。また、指導者育成などのソフト面の充実をさせることが、森づくりに取組むNGO・NPOにとっても重要です。鳥取でも、本日話題に上った様々な視点から森づくりに取組み、地元の森をいい森に変えていっていただきたいと思います。
構成・文:宮崎伸勝/写真:黒須一彦(エコロジーオンライン)