

 本シンポジウムは、損害保険ジャパンが「札幌コールセンター」、通称「札幌どさんコールセンター」開設を記念して開催をさせて頂くものです。札幌コールセンターは、損保ジャパンの全国の代理店さんからの問い合わせ事項にかかる対応を行っており、地域とのつながりとお客様サービスの充実につなげたいと考えています。損害保険ジャパンは、東京で15年前から一般市民の方々に向けた環境講座を、日本環境教育フォーラムと共同で実施しております。これには毎回150〜200名を越える参加者がおり、累計で1万人を越える方々にご参加頂いております。そして東京を離れての開催は、昨年の佐賀、今年2月の高知に続いて3回目となります。当社は、国内の金融機関としては最初に環境専門部署を設立し、早くから環境問題に取り組んできました。今後もこのような形を含めて、微力ながら地域密着、或いは地域の皆様とのパートナーシップの中で、社員参加の形で地域貢献と環境問題への取り組みを進めて行きたいと考えております。「北の大地での自然との共生」というテーマで行なうこのシンポジウムが、北海道の豊かな自然の素晴らしさを改めてご認識頂く機会になればと願っております。 本シンポジウムは、損害保険ジャパンが「札幌コールセンター」、通称「札幌どさんコールセンター」開設を記念して開催をさせて頂くものです。札幌コールセンターは、損保ジャパンの全国の代理店さんからの問い合わせ事項にかかる対応を行っており、地域とのつながりとお客様サービスの充実につなげたいと考えています。損害保険ジャパンは、東京で15年前から一般市民の方々に向けた環境講座を、日本環境教育フォーラムと共同で実施しております。これには毎回150〜200名を越える参加者がおり、累計で1万人を越える方々にご参加頂いております。そして東京を離れての開催は、昨年の佐賀、今年2月の高知に続いて3回目となります。当社は、国内の金融機関としては最初に環境専門部署を設立し、早くから環境問題に取り組んできました。今後もこのような形を含めて、微力ながら地域密着、或いは地域の皆様とのパートナーシップの中で、社員参加の形で地域貢献と環境問題への取り組みを進めて行きたいと考えております。「北の大地での自然との共生」というテーマで行なうこのシンポジウムが、北海道の豊かな自然の素晴らしさを改めてご認識頂く機会になればと願っております。
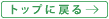


13:40 |

基調講演 |

「直線から曲線へ:自然再生時代」
月尾 嘉男 氏 (東京大学名誉教授)
|

 ブノワ・マンデルブロ(1924〜)という数学者の代表的な業績に「フラクタル理論」の発明があります。これは「自然は自己相似である」という理論で、自然は複雑な曲線で構成されているように見えるけれども、実際は単純な規則からできているということを解明したものです。その理論を応用すれば、単純な図形を自己相似させ、一見、本物の自然のように見える山や森の画像もコンピュータで真似ることができます。 ブノワ・マンデルブロ(1924〜)という数学者の代表的な業績に「フラクタル理論」の発明があります。これは「自然は自己相似である」という理論で、自然は複雑な曲線で構成されているように見えるけれども、実際は単純な規則からできているということを解明したものです。その理論を応用すれば、単純な図形を自己相似させ、一見、本物の自然のように見える山や森の画像もコンピュータで真似ることができます。
人間の歴史の中で行ってきた「開発」とは一体どういうことなのかというと、自然の曲線を直線に変えてきたことなのです。その実例を紹介します。松浦武四郎(1818〜1888)が1859年に作った「東西蝦夷山川地理取調図」という開拓前の北海道を克明に記した地図があります。これと現在の地図とを比べてみると、前者では河川の著しい蛇行が随所に見られますが、後者ではその多くが直線に変わっています。また道路や鉄道という人間が加えた直線の施設もあり、直線の数が大幅に増えてしまいました。これが開発という名の下で人間が行なってきたことなのです。
その代表的な例が石狩川です。この川の名前はアイヌ語の「イ・シカラ・ペツ(=非常にたくさん蛇行する川)」からきていますが、1898年に大洪水で多数の犠牲者が出たことを契機に大規模な治水工事が始まり、多くのダムや捷水路(蛇行部分を真っ直ぐに繋ぐ水路)が作られました。その結果、明治初期には全長365kmと日本一長い川だった石狩川は150年間で約100km短くなってしまい、全長268kmの日本第3位の川になってしまったのです。これと同様、各地で湿地帯を埋立て、森林を伐採し、農地に変えるという、曲線を直線に変える開発が続けられてきました。
北海道はこの150年間で人口が35倍に増えており、このような開発がなければ現在のような発展はなかった訳ですから、これまでの開発を批判することは適切なことではなく、これからどうするのかを考えていくことが重要です。
その根拠となるのが、現代が方向転換のための条件が整いつつある時代だということです。今後人口が減り、開発のための資金が減り、国民所得が減っていきます。そして人々の意識も仕事優先から生活優先へと転換し始めています。そういう中で開発は「建設」ではなく「維持補修」、つまり過去に作ったものを手直しすることに重点が置かれる時代に変化してきているのです。もう1つの根拠は「生きる」ということは、多かれ少なかれ「自然から収奪」することですが、これが限界に近づいているということです。最初に限界に近づくのが鉱物資源です。地球46億年の歴史の中で作られてきたこれらの資源を、人類はあと数百年で使い尽くそうとしているのです。また水産資源も1995年を頂点に天然の漁獲量が減少に転じており、森林資源は単純計算すると400年後に消滅します。ただし、そのような事を続ければ、その前に人類が絶滅するのでこの計算は現実にはあり得ません。さらに様々な生物の絶滅が危惧され、生命にとって最も大切な淡水も不足が指摘されています。
 そのような現状を理解するために、エコロジカルフットプリント(生態足跡面積=食糧生産面積+資源生産面積+社会基盤面積)という概念があります。これによると、日本人が現在の生活水準を維持する場合、必要な土地や水面の面積は1人当たり4.3haとなるのですが、日本国が持っている領土・領海の合計を総人口で割ると0.7haにしかなりません。1人当たり3.6haの面積が不足しているのですが、これを外国の土地を借りる事で補填し成り立っているのが日本の現状なのです。つまり外国の鉱物資源、エネルギー資源、農水産物を輸入しているという事です。エコロジカルフットプリントを地球全体で見ると、1人当たり2.2haが必要なのに対して、提供できる面積は1.8haしかなく、0.4ha足りませんが、この不足分は飢餓に苦しみ、汚れた水を飲んでいる何千万人の犠牲によって埋め合わせられているのです。 そのような現状を理解するために、エコロジカルフットプリント(生態足跡面積=食糧生産面積+資源生産面積+社会基盤面積)という概念があります。これによると、日本人が現在の生活水準を維持する場合、必要な土地や水面の面積は1人当たり4.3haとなるのですが、日本国が持っている領土・領海の合計を総人口で割ると0.7haにしかなりません。1人当たり3.6haの面積が不足しているのですが、これを外国の土地を借りる事で補填し成り立っているのが日本の現状なのです。つまり外国の鉱物資源、エネルギー資源、農水産物を輸入しているという事です。エコロジカルフットプリントを地球全体で見ると、1人当たり2.2haが必要なのに対して、提供できる面積は1.8haしかなく、0.4ha足りませんが、この不足分は飢餓に苦しみ、汚れた水を飲んでいる何千万人の犠牲によって埋め合わせられているのです。
私達はこの状況を何とかしなければなりません。そのためには現在の生活から削減できる物は削減していかなければならないのです。第一に、伝統を見直す事が必要です。江戸時代はリニューアルな素材を使った生活をしていました。リニューアルとは太陽・水・土があれば再生可能ということです。都市や住宅は木材で建設し、照明は菜種油や蝋燭を使用し、生薬で病を治した生活を見直すべきです。第二は地産地消です。50年前に80%だった我が国のエネルギー自給率は現在では4%。45年前に80%だった食糧自給率は40%まで下がってしまいました。穀物に至っては28%しか自給しておらず、世界で124位です。地産地消と反対のことをしているのが日本なのです。そのためフードマイレージも世界で圧倒的に大きく、大量の化石燃料を使って食糧を輸入しているのが日本であり、ウッドマイレージ、ウォーターマイレージという観点でも同様です。江戸時代には「江戸前」という言葉があったように、数百万人の江戸の人々は江戸湾で獲れた魚を食べ、瓦の生産も町の中で行なわれ、炭も関東平野にある森林から作られ、土木工事も周辺にある木や石を使って行なわれていました。また、川の流れを制御する工事も、川のすぐ横にある木や竹、足下に転がっている石を利用して行なっていました。つまり資材の輸送距離はせいぜい数百mだったわけです。現在、国土交通省が以前の工法を復活させる研究を始めています。
都市を再生して利用するという取り組みも始まっています。例えば函館では金森倉庫や郵便局の再生が有名ですし、古くなった洋館を若い人達がボランティアでペンキ塗って再生しています。小樽運河沿いの倉庫、滋賀県長浜の黒壁の建物も再生されて観光客を呼ぶ名所になっています。韓国では、かつて清渓川(チョンゲチョン)を地下に埋め上部に高速道路を通したのですが、2003年にそれを取り壊して川を復活させ、人々の憩いの場所にしました。
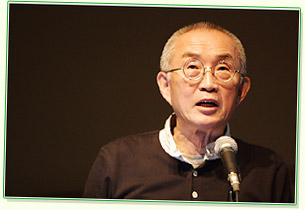 自然再生も世界各地で始まっています。かつては全体が湿地帯だったフロリダ半島は、この100年間で人口が急増し、そのため干拓が進んできました。しかし1990年代中頃から、以前の湿地に復元する工事が進み、多種類の生物が戻ってきました。この計画は2030年まで8000億円の予算を計上して進められています。こういった自然再生は日本でも始まっています。 自然再生も世界各地で始まっています。かつては全体が湿地帯だったフロリダ半島は、この100年間で人口が急増し、そのため干拓が進んできました。しかし1990年代中頃から、以前の湿地に復元する工事が進み、多種類の生物が戻ってきました。この計画は2030年まで8000億円の予算を計上して進められています。こういった自然再生は日本でも始まっています。
大金を投じて開発してきた場所を元に戻すような動きに対して異を唱える人々もいますが、それによって得られる利益の方が遥かに大きいという試算もなされています。「エコノミー」、経済は社会が発展するための活動です。それに対して、自然の再生や保全は「エコロジー」という言葉で象徴されますが、この2つはギリシア語の同じ言葉から派生した概念です。
OIKOS(生物の住処)+NOMOS(管理の制度)=ECONOMY
OIKOS(生物の住処)+LOGOS(研究の手法)=ECOLOGY
私達が住んでいる場所を上手く管理して発展していこうというのが「エコノミー」であり、その場所を研究して守っていこうというのが「エコロジー」です。しかし、いずれも生命の住処をいかに維持していくかということなのです。私達は、もう一度この原点に戻って考える事が必要です。
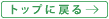


14:45 |

パネルディスカッション |

中村 太士 氏 (北海道大学大学院教授)
竹田津 実 氏 (獣医、写真家、エッセイスト)
住田 和子 氏 (北海道教育大学札幌校教授)
浅野 能昭 氏 (環境省北海道地方環境事務所長)

コーディネーター
瀬田 信哉 氏 (日本環境教育フォーラム理事) |

 瀬田:まずは、パネラーの皆様にそれぞれ専門分野の取り組みのお話をして頂きましょう。 瀬田:まずは、パネラーの皆様にそれぞれ専門分野の取り組みのお話をして頂きましょう。
中村:私は北海道大学の森林科学科に所属して、流域の森が川にどんな影響を与えるかとか、川の周りになぜ森が必要なのかという研究をしていました。先程月尾先生から「直線から曲線へ」というお話がありましたが、私自身も標津川などで数年前に「曲げる実験」をしました。川を直線化したために、人為的に三日月湖状に作られた河跡湖の部分を、試験的に半蛇行させる状態に再生したのです。私も当初は「半蛇行じゃ、どうしようもならんでしょう」と思っていたのですが、それでも自然は変わるのだという事をこの実験で知りました。ダイバーが潜って調べると、曲げた部分の川岸が、えぐられて木が倒れ込んだようになり、そこにたくさん魚がいるのです。自然は、もし我々が作った半蛇行の形が好きでなければ、自らそれを直すことができるのです。このケースで言えば、周りの木々が川の中に倒れ込んでいくのが、それに当たります。倒木の存在は川の中に渦を作り、殆ど流速ゼロになる場所ができ、魚達に快適なスペースを提供します。一方人間が作った川は、流速ゼロの場所が存在しません。となれば、私達はその真似をすればいいわけです。自然再生とは、自然がやることを真似ることなのです。もっと言うならば、私達は舞台装置を作るだけで、仕上げを自然に任せれば、自然はそれを安定したシステムに移行させていくのです。
 竹田津:私は道東の小清水という町で40年間暮らしています。1万haの耕地を持つ純農村です。そこで野生動物の診療をしており、野生の動物がなぜこの診察台の上にいるのか、その答えを出すのが私の仕事なのですが、やはり多いのは交通事故と農薬中毒です。ただ、農村で農薬のことを語るのはタブーな雰囲気があり、とても微妙な問題をはらんでいるのです。例えば、野外からやってきた動物は野外にある物で育てるという原則があるので、私はカワセミがやって来るとカワセミが食べる魚を獲ってくることになるのですが、例えば患者のために畑で虫を探していると「先生、うちの畑には虫はいないですよ」と言われてしまいます。しかし、食べ物を作る所に生き物が全然いないというのは凄い現実ではないでしょうか。生き物が生存できない所で食べ物が生産されているのはおかしいだろうということから、これに対する私達の活動が始まりました。しかし農村の青年達といくら語り合っても、言われてしまうのは「正義は関係ない。食っていくことができなければ意味がない」という言葉です。そこで農薬がなくても、或いは農薬が少なくても野菜作りがやれるという「代替の技術」が必要になります。その時に注目したのが、北海道では年間2000万t以上の牛と豚の糞が捨てられていたというデータでした。この糞を様々な改良や工夫を経て再利用化に成功し、現在に至っています。 竹田津:私は道東の小清水という町で40年間暮らしています。1万haの耕地を持つ純農村です。そこで野生動物の診療をしており、野生の動物がなぜこの診察台の上にいるのか、その答えを出すのが私の仕事なのですが、やはり多いのは交通事故と農薬中毒です。ただ、農村で農薬のことを語るのはタブーな雰囲気があり、とても微妙な問題をはらんでいるのです。例えば、野外からやってきた動物は野外にある物で育てるという原則があるので、私はカワセミがやって来るとカワセミが食べる魚を獲ってくることになるのですが、例えば患者のために畑で虫を探していると「先生、うちの畑には虫はいないですよ」と言われてしまいます。しかし、食べ物を作る所に生き物が全然いないというのは凄い現実ではないでしょうか。生き物が生存できない所で食べ物が生産されているのはおかしいだろうということから、これに対する私達の活動が始まりました。しかし農村の青年達といくら語り合っても、言われてしまうのは「正義は関係ない。食っていくことができなければ意味がない」という言葉です。そこで農薬がなくても、或いは農薬が少なくても野菜作りがやれるという「代替の技術」が必要になります。その時に注目したのが、北海道では年間2000万t以上の牛と豚の糞が捨てられていたというデータでした。この糞を様々な改良や工夫を経て再利用化に成功し、現在に至っています。
浅野:4年前、環境保全活動・環境教育推進法が議員立法で出来ました。環境問題は、かつて企業が排出する汚染物質や観光開発がその原因だったのですが、現在では、地球温暖化や身近な自然の喪失など一人一人の個人が原因となる問題が多くなりました。このため自発的な環境保全活動をもっと活発にしていこうという主旨の下に生まれたのがこの法律で、これは非常に画期的なことです。
北海道には6つの国立公園、5つの国定公園をはじめ道立自然公園、自然環境保全地域、鳥獣保護区、ラムサール条約登録湿地などがあり、今でも豊かな自然に恵まれていますが、これら保護地域の割合は全国平均よりもかなり小さくなっています。法律で守られていない身近な自然をどう守っていくのか、そして外来生物による生物相の変化をどう防止していくのかが、現在の自然環境行政で大きな問題になっています。日本最大の高層湿原を有するサロベツ原野は、昭和49年に国立公園に指定されました。しかし、かつては約15000haの湿原が広がっていたサロベツ原野ですが、農地としての開発が進み、国立公園指定時には湿原は約6700haになっていました。サロベツ原野の自然再生事業のポイントは、この残った湿原と農地開発の境目をどうしていくかです。農地開発の際には排水溝を入れて農地の地下水位を下げているのですが、湿原の地下水位も下がってしまい、保全されたはずの湿原側にも小さな水路が入っていて、湿原の乾燥化が進んでいることが問題になっています。上サロベツ地区では、「上サロベツ自然再生協議会」が設立され、行政だけでなく地域のあらゆる方々に参加してもらって計画を決め、その上で湿原の地下水位の保全などの具体的な事業を実行していきましょうという住民参加方式をとっています。残された湿原を環境教育などに利用し、これらを保全する事で地域の利益に結びつけていく「ワイズ・ユース」という取り組みを進めています。
 住田:私は、自分自身の子育てを通して、命を守り育てるという生活への関心が一層強くなりました。言い換えますと、子育てと日常の生活環境との繋がりが私に環境問題を考えさせるようになりました。自然環境というよりも生活環境というレベルです。 住田:私は、自分自身の子育てを通して、命を守り育てるという生活への関心が一層強くなりました。言い換えますと、子育てと日常の生活環境との繋がりが私に環境問題を考えさせるようになりました。自然環境というよりも生活環境というレベルです。
物質的環境は、子育てのプロセスの中で身体のみならず心の発達とも関わっています。生態系が抱えている病と社会問題としての教育が抱えている病の根は一つなのではないかという考えに至りました。モノを大切に出来なくて、どうして健やかな心が育まれるのでしょうか、その過程の中で、豊かな人間性に行き着くのではないかと思います。結局、物的関わりの問題とは消費の問題です。このように考えますと、環境の汚染源は人間であり、教育を通して人間を最良の資源に変える事ができるのです。
先程の月尾先生の講演にもありましたが、1892年にアメリカの女性化学者・リチャーズ夫人(1842〜1911)は、ギリシア語の「OIKOS(家)」が語源である「エコロジー」という概念を提唱しました。彼女は、後に「沈黙の春」で環境問題に警鐘を鳴らしたレイチェル・カーソンに科学への道を開いた人物でもあります。その彼女が、「環境とは、人間の行動を含めて1つの総体として把握しなければならない」という考えを提示しました。
私の大学での意識調査でも、「環境教育=自然教育・理科教育」という意見が9割を占めていましたが、エコロジカルとエコノミカルは表裏一体であり、物質的環境は、消費のあり方や家庭教育と総て繋がっているのです。「環境の汚染源は人間。しかし無限の可能性をもつ人間を、教育を通して真に豊かな人間性や社会の創造を」、というリチャーズ夫人の言葉を学生に伝えていますが、このように環境を社会的・倫理的側面から捉えた女性が既に、1世紀前に存在したことを皆さんにもお伝えしたいと思います。
瀬田:まず中村さんに質問です。「再生」事業を行われる際には、面積的な広がりと時間と参加する費用が絡んできますが、環境を内科的にやらないといけない時に、これらが難しいということがあります。「共生とは色々な価値観とぶつかることだ」とレジメにも書かれていますが、このことについてどう感じていらっしゃるのか。
続いて竹田津さんへの質問ですが、オホーツクの天然林の防風林について、私達は「原生の自然」というとすぐに知床などを思い浮かべてしまいますが、防風林が農地と接しているという自然の豊かさについてどうお考えなのかを聞かせて下さい。
 中村:こういうシンポジウムをやると「なぜ釧路からやるんですか?」とか、「標津川の取り組みをなぜ下流からやるのですか?問題は上流にあるのではないですか?」と聞かれることがあります。そこで考えたのですが、北海道の森や川として、まず保全すべき場所がどこかを記したものが地図としてあるのだろうか…ということです。これ無くして取り組みを起こすという事は、北海道全体のカルテも知らずに手術をするようなもので、まず大事なのは、森や川、湿地の健康診断をして、どこがどうおかしいのか、健全な残すべき自然はどこなのかを地図として残すことなのだと思います。そうすれば、総論賛成・各論反対という事態に直面した時でも、色々な繋がりを残す事ができるのです。私は釧路でもそうしてきましたが、地域で地図を作るという事は、同じ情報を共有するという事です。価値観をお互い認め合いながら、情報共有しながら臨めば、そんなにズレることはないはずです。またもう一つ大切な事は、どこかで日常性に入らなければいけないということです。議論が隔離された空間の中だけで行なわれていてもそれはだめで、エコロジーという枠だけで考えるとそれは隔離された話でしかありません。自然再生のゴールに社会経済性のゴールも組込むと、その取り組みは盛り上がるのです。 中村:こういうシンポジウムをやると「なぜ釧路からやるんですか?」とか、「標津川の取り組みをなぜ下流からやるのですか?問題は上流にあるのではないですか?」と聞かれることがあります。そこで考えたのですが、北海道の森や川として、まず保全すべき場所がどこかを記したものが地図としてあるのだろうか…ということです。これ無くして取り組みを起こすという事は、北海道全体のカルテも知らずに手術をするようなもので、まず大事なのは、森や川、湿地の健康診断をして、どこがどうおかしいのか、健全な残すべき自然はどこなのかを地図として残すことなのだと思います。そうすれば、総論賛成・各論反対という事態に直面した時でも、色々な繋がりを残す事ができるのです。私は釧路でもそうしてきましたが、地域で地図を作るという事は、同じ情報を共有するという事です。価値観をお互い認め合いながら、情報共有しながら臨めば、そんなにズレることはないはずです。またもう一つ大切な事は、どこかで日常性に入らなければいけないということです。議論が隔離された空間の中だけで行なわれていてもそれはだめで、エコロジーという枠だけで考えるとそれは隔離された話でしかありません。自然再生のゴールに社会経済性のゴールも組込むと、その取り組みは盛り上がるのです。
竹田津:オホーツク村は人工林です。隣接する天然林の防風林のデータを基にその人工林を80年かけて同じ植生にするという取り組みをしています。産業廃棄物化した糞尿を生産資材にもどす作業は、バクテリアを大地にもどす作業でもあります。その過程で私は、あれほど大量の農薬を使われながらも凄い復元力を持っている北海道の大地は、その隣接する防風林から、太古からのバクテリアという復活剤を貰っているんじゃないかという思いに至りました。それは大変な財産だと思います。このことは我々の新しい天然林作りの目的となると同時に、病んだ大地の復活のための起爆剤といえるのではないでしょうか。
 瀬田:ここから、月尾先生にも壇上にお上がり頂いて、会場の皆さんに質問・感想等を伺いたいと思います。 瀬田:ここから、月尾先生にも壇上にお上がり頂いて、会場の皆さんに質問・感想等を伺いたいと思います。
質問:食糧とエネルギーの問題についてとても関心があります。北海道でもエタノール生産をしようという動きがあるのですが、この辺はどう考えていくべきか意見を聞かせて下さい。
月尾:人間は生物界の中で異常な事をやっている種だという現実から考え始めるべきだと思います。他の生物と違って人間は何億年とか何千万年という単位で蓄積されてきた太陽エネルギーを使う技術を手に入れたということです。虫が草を食べるのは、せいぜい数年で蓄積された太陽エネルギーを消費しているに過ぎないのですが、石油や石炭はそうではなく、そこに環境問題が発生する所以がある訳です。一般にバイオマスと言われるエネルギー資源の蓄積量では、現代の人類が使う化石エネルギーを代替する事は出来ないので、例えば食糧を犠牲にして燃料を作るということになるのです。これで必要なエネルギーを賄うことは難しいけれども、部分的な補助であると認識していればいいと思っています。
質問:環境活動はアピールする必要があると思うのですが、来年のサミットに向けてアピールをしていくアイデアは何かありますか?
浅野:洞爺湖地域でのサミットは、中心テーマが環境問題となり、北海道の環境について情報発信する大きなチャンスだと考えています。各国大統領やその夫人、多くのメディアが来るというこの機会に、単に北海道の事だけではなく、北海道として、日本として、どういう環境に関する取り組みをしているかを知ってもらういい機会だと思います。ただ、北海道は涼しいということもあって地球温暖化防止への関心の高まりは小さく、エネルギー消費量も全国平均の1.4倍、クールビズも涼しいのであまり浸透していません。現在は環境保全に取り組む皆さんの意識の高さや姿勢をアピールできるための作戦を練り始めているところですので、ぜひ良いアイデアを頂ければと思っております。
 住田:ワンガリ・マータイさんの「もったいない」という言葉がありますが、「もったい」とは物の本質・本体という意味があり、具体的には消費のあり方・ゴミの問題にも関わることですが、日本が配慮していない部分も多々ございますので、省資源のスタイルを打ち出してもらえないか、と思っています。 住田:ワンガリ・マータイさんの「もったいない」という言葉がありますが、「もったい」とは物の本質・本体という意味があり、具体的には消費のあり方・ゴミの問題にも関わることですが、日本が配慮していない部分も多々ございますので、省資源のスタイルを打ち出してもらえないか、と思っています。
月尾:日本が環境の面で進んでいる数少ない分野は、エネルギー消費を減らしながら暮らしを維持する技術です。例えば10年前のテレビジョン受像機と現在の製品を比べると電力消費は1/5になっています。同様に、白熱電球と蛍光電球を比べると、電力消費は1/4です。そういう技術をODAなどで世界に普及させていくということは可能です。伝統技術や伝統生活を見習えということを基調講演で申し上げましたが、世界の先進工業国の中で伝統的思想が残っているということで言えば、日本が圧倒的です。例えば、北海道ではアイヌの人々の生活思想が残っているという事は、非常に重要なことなのです。欧米では、アイルランドにケルト文化の考え方が残っている位で、それ以外の地域では歴史的に一神教が伝統文化を駆逐してきました。日本では、多神教思想が残っていて、環境問題を考える時に必要なルーツになっていると思います。経済大国になり、先進工業国になり、なおかつ古い多神教的精神が残っている日本を世界に知ってもらうということは重要な事です。
瀬田:ケルト系の血を継ぐという作家のC.W.ニコルさんに、多神教を駆逐していったローマ帝国の西と東にアイルランドと日本のような国があり、この2国で世界を包んでいこうよと言われた事がありました。そういったことをサミットの時に表せればいいと思いますね。
質問:人口増の問題は、農産物の生産力の向上や医学の発達とも関連している訳ですが、この自己矛盾を短絡的に考えていくと、自由経済・自由社会より統制経済でないと、自然との共生を守っていくことも難しいのではないかと考えてしまうのですが、その辺について意見を聞かせて下さい。
月尾:農業も医学も、学問としてではなく、社会で実際に利用する手段と考えれば、それはエネルギーを使うものです。北海道は農業自給率180%と言われていますが、農薬を生産するエネルギーやトラクターを動かすエネルギーの自給率を計算すれば100%を切ります。最初の質問でお答えしたように、バイオマスエネルギーは部分的な代替に過ぎない物ですから、こうした社会を続けていれば人口はいずれ減っていく方向に向かいます。大事なことは、いかにして幸福な気持ちで暮らしていくかを考える事だと思います。こういう世の中で、絶望したり悲観的になったりしないで、幸せに生きていける方法を考えるべきだと思います。
 質問:「直線的に…云々」という話がありましたが、そこに投下された社会資本は莫大でありながらも、先進国では低い方だということですが、これは国家予算としてどう捉えたらいいのでしょうか。また、フードマイレージの話の中で、日本の食糧自給率は 40%と話していましたが、農産物を輸入することはバーチャルウォーターを輸入する事と同じだと思います。そして21世紀は水の戦争が来ると言われていますが、その点についての考えを聞かせて下さい。 質問:「直線的に…云々」という話がありましたが、そこに投下された社会資本は莫大でありながらも、先進国では低い方だということですが、これは国家予算としてどう捉えたらいいのでしょうか。また、フードマイレージの話の中で、日本の食糧自給率は 40%と話していましたが、農産物を輸入することはバーチャルウォーターを輸入する事と同じだと思います。そして21世紀は水の戦争が来ると言われていますが、その点についての考えを聞かせて下さい。
月尾:水についてお答えしますと、その通りだと思います。私の計算では、バーチャルウォーターの輸入は年830億tに達しており、これは日本が1年間に、農業・工業・生活に使っている量の合計とほぼ同じです。そして世界中の資本が、石油の次は水だということで動き始めています。また水をWTOのサービス品目にするという動きもあります。これが実現すると、日本が自国の水を守ることが制約されます。そのような動きが静かに始まっているのです。
中村:「直線的」の話についてですが、私は政府関係者ではないので上手く答えられないかもしれませんが、「その時代にはその時代の価値観と目的がある」ということを考えるべきなのだと思います。かつては「湿原を守ろう」などという声は殆どありませんでした。むしろ生産性が低い場所としか看做されていなかった時代がありました。しかし違う時代が来れば、違う価値観のもとで人々の動きが生まれるのです。そして過去をいくら批判しても、何も新しい物は生まれてきません。もちろん反省すべき事があれば反省すべきです。けれども、今の価値観からするとどこでどういう問題が起きていて、それを未来に対してどう変えていくのかという明確なビジョンを示すことが重要な事なのではないでしょうか。そして価値をお金に換算して評価することについては、世間で色々な計算がされていますが、これらにあまりとらわれ過ぎない事も大切です。お金に換算したり、費用対効果に注目していく考え方もあるのでしょうが、もっと重要なのは地域がどういう形で未来に向かっていくか、そこで健全な生態系が回る仕組みをどう作っていくかということで、それがクリアできれば何らかの形で歯車が回っていくのではないでしょうか。


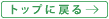

|


