
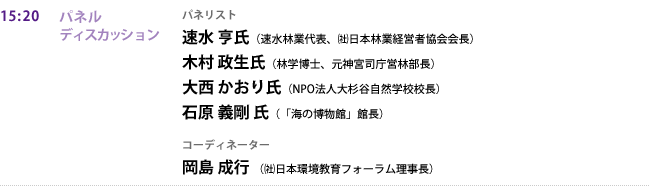
岡島 三重県内だけで、日本中に名前が知られているこれだけのメンバーが揃うというのは、さすが自然も人も豊かな三重県だと感じています。きっと楽しい話になりそうですが、まずはお一人ずつ自己紹介も兼ねて、それぞれのご専門の話をして頂けますでしょうか。
 速水 日本は木材の8割を輸入していますが、その内のかなりの割合が違法伐採だったり、森の周辺に住む人々を大切にしない伐り方をしていたりする木材です。例えばアフリカの先住民など森に依存している人々は森が全て切られてしまうという意識がそもそも無く、森を伐らせて欲しいというごく簡単な書類にすぐサインをしてしまうのです。本来彼らは船や家を作るために必要なだけの僅かな木を伐るのですが、気づくと業者によって森を一気に伐られてしまい、その結果、薪や水が無くなり、遠くからそれを運んでこなければならず、女性はヘルニアや子宮脱肛など体を壊し、子供達は教育の機会を奪われるだけでなく、女の子は売春をさせられるという事態になってしまうのです。我々が10本の外国の木を伐って使うと、その内の1か2本は、こうした人権を無視した使い方になっていると言われています。そういう意味では、日本国内で生産された木材をどう国内消費者にきっちり渡していくかが、世界の人権を守るという事に繋がります。しかしその一方で日本は林業経営が成り立たないほど木材価格が下落しています。国内林業の現状をお話しすると、この50年間で木の量は4倍に増えました。しかし値段は50年前の水準です。林家の収入は平均29万円。100〜500ha持っている人でも年間36万円しか山からお金が入ってきません。 速水 日本は木材の8割を輸入していますが、その内のかなりの割合が違法伐採だったり、森の周辺に住む人々を大切にしない伐り方をしていたりする木材です。例えばアフリカの先住民など森に依存している人々は森が全て切られてしまうという意識がそもそも無く、森を伐らせて欲しいというごく簡単な書類にすぐサインをしてしまうのです。本来彼らは船や家を作るために必要なだけの僅かな木を伐るのですが、気づくと業者によって森を一気に伐られてしまい、その結果、薪や水が無くなり、遠くからそれを運んでこなければならず、女性はヘルニアや子宮脱肛など体を壊し、子供達は教育の機会を奪われるだけでなく、女の子は売春をさせられるという事態になってしまうのです。我々が10本の外国の木を伐って使うと、その内の1か2本は、こうした人権を無視した使い方になっていると言われています。そういう意味では、日本国内で生産された木材をどう国内消費者にきっちり渡していくかが、世界の人権を守るという事に繋がります。しかしその一方で日本は林業経営が成り立たないほど木材価格が下落しています。国内林業の現状をお話しすると、この50年間で木の量は4倍に増えました。しかし値段は50年前の水準です。林家の収入は平均29万円。100〜500ha持っている人でも年間36万円しか山からお金が入ってきません。
そういった中で私達は、地域住民に理解して貰える、環境的に豊かで美しい森林、人工林の環境技術の確立、自然との共生・地域との共生を大事にしていく、という考え方に基づいた山作りに取組んでいます。森は植えてから伐るまでの間は光の管理が主な仕事になりますが、それに加えて私達の山では水の管理にも工夫を施し、人工林であっても水をきれいにし続ける機能を持たせるようにしています。その結果、人工林でも豊かな森を作れることが実証されています。我々が注意深く管理をしていけば、三重県の森は更に豊かになっていく可能性を十分に持っている事をこれからも伝えていきたいと思います。
 木村 伊勢の神宮では、20年に一回御社殿を新しく建て替える遷宮という神宮最大の行事があります。江戸時代には「おかげ参り」と言って爆発的に参拝者が増えることがありましたが、記録によると最も多かったのが文政12年にあった遷宮の翌年にあたる文政13年(1830年)のことでした。全国の人口が3000万人というこの時代の3〜9月間に457万9150人のお参りがありました。ところで、当時これだけの人がお参りする賄いのための薪を、宮川流域をはじめ一番神宮から近い現在の宮域林から伐り出していました。このために五十鈴川は度々洪水を起こしていたのです。このうち記録にある中で一番大きかったのが大正7年9月の洪水で、内宮の門前町は2m20〜30cmの床上浸水だったと記録されています。この時一日の雨量は350mm、神宮の山の中で119ヶ所の山崩れが起こり、こうした経緯から山の管理を神宮自らがやるようになり、造林事業に取組み始めました。 木村 伊勢の神宮では、20年に一回御社殿を新しく建て替える遷宮という神宮最大の行事があります。江戸時代には「おかげ参り」と言って爆発的に参拝者が増えることがありましたが、記録によると最も多かったのが文政12年にあった遷宮の翌年にあたる文政13年(1830年)のことでした。全国の人口が3000万人というこの時代の3〜9月間に457万9150人のお参りがありました。ところで、当時これだけの人がお参りする賄いのための薪を、宮川流域をはじめ一番神宮から近い現在の宮域林から伐り出していました。このために五十鈴川は度々洪水を起こしていたのです。このうち記録にある中で一番大きかったのが大正7年9月の洪水で、内宮の門前町は2m20〜30cmの床上浸水だったと記録されています。この時一日の雨量は350mm、神宮の山の中で119ヶ所の山崩れが起こり、こうした経緯から山の管理を神宮自らがやるようになり、造林事業に取組み始めました。
それから毎年60haずつヒノキを植え、その他の樹種との混交林による造林を行ってきました。60年間で3000haの森林を作ろうという計画を進めています。この植栽は、200年後に直径60cmのヒノキの御造営用材を採ることを想定しています。現在2500haほどの造林地ができており、これらは全て針葉樹であるヒノキと郷土木である広葉樹の混交林になっています。その結果、最近10年間の年間平均雨量を見ると、伊勢市では1900mm程ですが神宮の森の中では2900mmあり、ちょうど1000mmの差があります。これだけの森ができたことによって水の循環が良くなった影響であると、私達は見ています。また平成3年には、一日雨量486mm、時間雨量82mmという集中豪雨があったにも拘らず、この時洪水被害は全く発生せず、森林の貯水能力向上が証明されました。そして現在では、500mmを越える集中豪雨があっても下流で洪水被害は起こらないというのが、宮域林内の状態となっています。
 大西 私が校長を務める、大杉谷自然学校の活動報告をさせて頂きたいと思います。 大西 私が校長を務める、大杉谷自然学校の活動報告をさせて頂きたいと思います。
私達が活動している大杉谷地区とは人口343人の地域で、先程の木村さんのお話にも登場した宮川がそばを流れています。この宮川は源流部が大台ケ原で、その尾根沿いを歩くとまだ原生林が残っているような場所です。
このような地域で、私達は、歴史的背景、自然的背景、地域の問題を背景に環境教育事業を展開しています。具体的には、子供達によるキャンプや森林での活動があり、例えば、子供達に林業を1年間かけて体験してもらう授業では、子供達自らが間伐をして、その木を市場に売りに行き、いくらで売れるのかを学びました。また川での活動では、都会にいて自然と触れ合った経験のない子供達を連れていき、大きな岩の上から川に飛び込んだり、昔の子供達、つまり今の大人やお年寄りに昔の漁法を教えてもらうという活動をしました。平成16年に台風21号の被害に遭った時には、自然のありのままの姿を学んでもらうために災害を取り入れた環境教育事業を展開しました。この時、台風によって鳥羽の海は、川から流された流木でいっぱいになり船が出られなくなるなどの被害に遭いました。このことから、森と海の繋がりを強く実感する授業となりました。また、これを契機に平成16年以降、海での活動も取り入れるようになり、漁師さんにロープワークを習うなど海の方々の技術や文化を教えて頂いています。このような私達の活動の醍醐味は「自然の驚異を感じる」ということだと考えていますが、同時にその事を通して、自然とはそれぞれに繋がりがあり、長いスパンを考えながら捉えていかないといけないものであるということを実感しています。
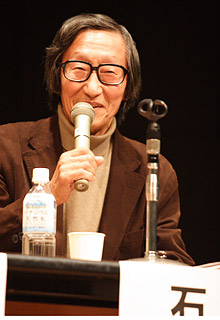 石原 私は、40年間鳥羽で漁業と海運をテーマにした博物館をやっておりますが、その一方で海の環境にも長く取組んできました。先程ニコルさんは1962年に日本にやって来たと話していらっしゃいましたが、日本の海はちょうどその頃から汚染と破壊にさらされています。40年前には、まだ三重県にも今よりもっときれいな海があり、海と森と人間がいい具合に手を繋ぎ合っていました。 石原 私は、40年間鳥羽で漁業と海運をテーマにした博物館をやっておりますが、その一方で海の環境にも長く取組んできました。先程ニコルさんは1962年に日本にやって来たと話していらっしゃいましたが、日本の海はちょうどその頃から汚染と破壊にさらされています。40年前には、まだ三重県にも今よりもっときれいな海があり、海と森と人間がいい具合に手を繋ぎ合っていました。
三重県には1000kmの海岸線があり、伊勢湾と熊野灘に大きく分けられます。伊勢湾の干潟は、今や潮干狩りだけの場所になってしまいましたが、本来は非常に有用な海の生態系の基本でした。何百種類もの生き物の子供達が暮らしていましたし、波が打ち寄せる度に酸素を供給する浄化の場所になっていたのですが、現在こういった干潟は、伊勢湾の中では7割くらい消失してしまいました。干潟と同じように生き物の子供達を育んでいたアシ原もまた、伊勢湾から姿を消してしまいました。また、多くの人が川にだけいると思い込んでいるアユは、冬の間は海の波打ち際にいて春になると遡上します。伊勢湾に注ぐ宮川は、かつてそんなアユが行き来する素晴らしい川でしたが、今はダムが出来たり、汚染で生育できない環境になってしまいました。
熊野灘も、かつてと現在ではその姿を大きく変えました。その昔は、魚付林が陸上の豊かな栄養分を海に流し込み、そこにプランクトンが発生し、更にそれを求めて魚達が集まってくるというシステムが成立していましたし、その先の海には正に海中林が広がっていたのです。一方この地域で働いていた船大工は、山で船に適した木を選ぶと、木霊に感謝して山の木にお酒を捧げ、船が完成すると船霊を船に埋め込み、安全と大漁を祈願するという風習を持っていました。一つの木が山で伐られて船になり海へ出て行く過程で、人間が感謝を捧げる姿がそこにはありました。こうした海と森と人間の繋がりも、今では消えてなくなってしまいました。
 岡島 皆さん、有難うございました。全体的に見ると、かなり昔より後退しているようですが、それを何とか盛り返すために、海と山の連携を見直していく必要があります。三重県は“美し国”ということで、まだ日本の中でも自然が豊かでいい方だと思います。そして三重県が旗を揚げれば、他の地域も追随して日本全体が良くなってくるのではないでしょうか。そこで三重県ではまずどんなことをやったらいいのか、石原さん、何かアイデアはありませんか。 岡島 皆さん、有難うございました。全体的に見ると、かなり昔より後退しているようですが、それを何とか盛り返すために、海と山の連携を見直していく必要があります。三重県は“美し国”ということで、まだ日本の中でも自然が豊かでいい方だと思います。そして三重県が旗を揚げれば、他の地域も追随して日本全体が良くなってくるのではないでしょうか。そこで三重県ではまずどんなことをやったらいいのか、石原さん、何かアイデアはありませんか。
石原 私は、大人には全く絶望していまして、本当は子供達には申し訳ないことなのですが、子供達に賭けています。子供達に海を体験してもらおうという取組みを続けています。しかし、例えば夏、小さな子供達に船漕ぎ体験をやってもらう試みをしていますが、子供達はやりたくて船の方にまっしぐらに走って来るのですが、親が危ないからやめろと止めるのです。それにもめげずに頑張ろうと思っていますが…。
大西 私達の学校では、体験しながら海と森を繋いでいこうということをしています。最近では、かつて山のプログラムによく参加して下さっていた子供達が、海のプログラムにも参加してくれるようになってきました。山のこと、海のこと、両方を総合的に理解できるという部分をこれからは強調していこうと考えています。
木村 先程の速水さんのお話にもありましたが、今日本で使われる木材の80%が海外からの輸入です。日本はいつまでも海外の木を伐っていていいのかという問題があります。日本は国土の約70%が森林ですが、スギ・ヒノキほど建築用材として優秀なものはありません。70%のうち造林に適した林地が3〜4割はあるので、それくらいの人工林を作っていいのではないかと思います。しかし、問題は森林の生態系を考えた造林方法ではないかと思います。
速水 うちの山はすぐ側に海があります。海岸から7kmで1000m上る急峻な山です。そういう場所にいると、川を汚してはいけない、土を流してはいけないという注意をはらう必要があります。日本の林業は、大きな循環を維持していこうという努力はしていますが、細かい配慮が殆ど現場でされていません。山が環境にいいとか、人工林を管理すればより良くなるということが一般的に言われていますが、山にいる者が、自分がやっていることが海にどういう影響があるのかという意識がないと、が空虚なものに聞こえてしまいます。県などが森林の環境管理指針のようなものを作る必要があるのではないでしょうか。
 岡島 一般に人々の自然に対する知識が、昔と比べると乏しくなっているのではないかという状況がありますよね。例えば木を例に取ってみると、キリの箪笥など、家具も材質によってそれぞれ違うものだということは、年配の方はもちろんご存知だと思いますが、若い人にとっては殆どどれも同じ「板」としか認識されない。それがサクラなのかスギなのか南洋材なのか分からない。当然木材をトンカチで打ったこともカンナで削ったこともない。その辺のことを、今の大人に分かってもらう方法は何かないでしょうか。 岡島 一般に人々の自然に対する知識が、昔と比べると乏しくなっているのではないかという状況がありますよね。例えば木を例に取ってみると、キリの箪笥など、家具も材質によってそれぞれ違うものだということは、年配の方はもちろんご存知だと思いますが、若い人にとっては殆どどれも同じ「板」としか認識されない。それがサクラなのかスギなのか南洋材なのか分からない。当然木材をトンカチで打ったこともカンナで削ったこともない。その辺のことを、今の大人に分かってもらう方法は何かないでしょうか。
石原 日本も豊かになって暇のあるお年寄りが増えてきましたから、経験を持ったお年寄りを繋いでいって子供達に何かを伝えるという事は、確かに機能し始めていますよね。私は、こういう伝統のようなものは隔世遺伝だと思っています。親は忙しいですから、子供に手をかけてられないですし…。
大西 私の学校でやっている「昔の子どもはすごかった」という、お年寄りから色々な技術を子供達が教わる授業でも、自分達の技術を人に喜んでもらえたり、伝えることができるということでお年寄りからも好評です。
木村 私は、この頃の木造住宅が25〜30年もてばいいという考え方が間違っていると思います。100年もつ家を考えるべきです。それと、先程石原さんが言われた通り船大工がいなくなってきていますが、日本の大工にはそれをメンテナンスできる技術があるわけですから、そういった人達がいなくなる前に、これらの技術の継承をすることは非常に重要だと思います。
速水 家を建てる時、まるで自動車をカタログを見て買うようにして購入し、買った瞬間が最高で後は年々古くなっていくというような捉え方が今の世の中で一般的です。でも本当は建てる前に、あの大工は上手いとか、あの親父さんが作った木彫りは凄かったとかそういう知識が必要で、もちろん女性がそれでもいいのですが、男なら家の建て方くらい大体分かっているべきだと思います。そういう意味で今の男性はだらしなくなりましたよね。建て方なんてわからないまま、カタログを奥さんに渡して決めて貰う…なんて、一生に一度の楽しみを全部捨て去っているような感じがします。家を建てたら、自分の生き方とともに家を磨いていく、変えていく…そんな家とともに家族が成長していくというリズムが全く無くなってしまったような気がします。それがもしあれば、木の素晴らしさをもっと感じて貰える機会になるのではないかと思います。
岡島 子供の自然体験についてはどのようにお考えでしょうか。
石原 3〜4年前から漂着物で作るアート作品の募集を始めました。子供達は、海に流れ着いたゴミをゴミと感じられないほど、とても素晴らしい作品を作っています。そしてこの企画がいいのは、親が子供達にくっついてくるので、海の話を子供達とすると、その話が親に繋がっていきます。私はこれを暫く続けていこうと思っています。
大西 最近自然体験活動をしている子供達の年齢層が下がってきており、全国的に森の幼稚園というような活動が盛んです。小さい頃に自然体験が豊かだと、身体能力や判断力が高くなります。そういう子供を増やすことで社会が変わってくるのではないかと感じています。
 木村 最近はそれほどでも無くなってきましたが、人々の間に宗教アレルギーがあって神社への参拝が嫌われる傾向があるのですが、全国的にあちこちの森林を見せてもらっている立場から申し上げますと、神宮ほど立派な森林が残っている場所はありませんので、ぜひ森林浴のつもりで子供を神宮へ連れていって頂いたり、昔の子供が鎮守の森で遊んだような感覚で捉えて頂けるといいのではないかと思います。 木村 最近はそれほどでも無くなってきましたが、人々の間に宗教アレルギーがあって神社への参拝が嫌われる傾向があるのですが、全国的にあちこちの森林を見せてもらっている立場から申し上げますと、神宮ほど立派な森林が残っている場所はありませんので、ぜひ森林浴のつもりで子供を神宮へ連れていって頂いたり、昔の子供が鎮守の森で遊んだような感覚で捉えて頂けるといいのではないかと思います。
速水 山の中に入ると、一歩の靴の下に、大体数千から一万くらいの微生物の命がいます。子供達が山に入って生き生きと楽しくなってくるというのは、もしかするとそういった息吹とのやりとりを感じ取っているのではないかと私は思います。そこで土を掘り返して、見たこともないような白いムニュムニュしたものが動いているのを見せると、子供達は「エッ!」とは言うけれども「気持ち悪い!」とは言いません。普通の場所で見たら絶対に「気持ち悪い!」になるはずなのです。場所の違いで子供の感性がこれだけ豊かになっていくということは、自然とはそこに抱かれている命の素晴らしさを感じ取れる空間であり、海でも山でも子供達を自然の中にどう導くかが、これからの社会にとって大事なことだと思います。
|
