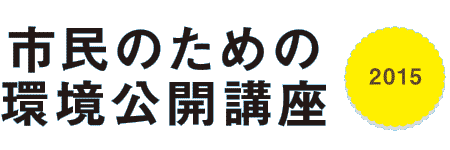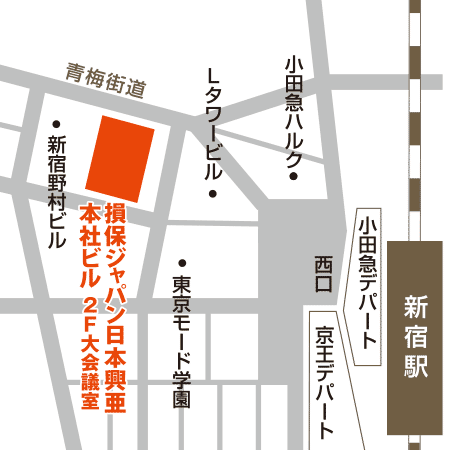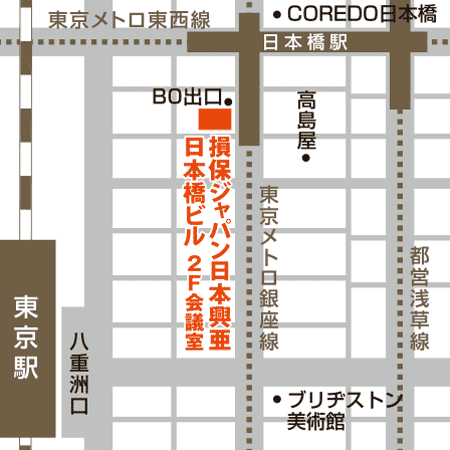講座概要
高度経済成長期以降、日本の自然環境は劣化し野生生物たちの生息生育環境が奪われてきました。初来日から52年を迎えるC.W.ニコルは、日本の自然を愛するが故に移り住みましたが、その後の森の状況を嘆き悲しみ、長野県黒姫の荒廃していた森を自ら買い取り、生物多様性溢れる本来の森に再生する活動をはじめました。
森を甦らせるということは、どういうことか。日本の森の現状をお伝えしながら、伝統的な馬搬の技術の再生も交えて、日本の将来について森の視点でお話させていただきます。

伝統文化を守り伝える人
野口 理佐子 氏
(一財)C.W.ニコル・アファンの森財団 事務局長
森に関する「日本の2つの罪」
 C.W.ニコルは、51年前の東京オリンピック以前の自然(または「高度経済成長前の日本の自然」)は素晴らしいものだったと言います。当時の日本は、自然と人々の暮らしが融合していました。燃料は薪を使い、衣食住は山の恵みから、そして動力は牛や馬。「山があれば生きていける」というのが日本人の暮らしでした。それが、ガスや石油を燃料とし、化学製品や輸入した食材・木材に依存する暮らし、言い換えると「お金があれば生きていける」というライフスタイルへ変化してしまったのです。日本人が、自然なんてどうでもいいと思い始めたのは、この頃からではないでしょうか。
C.W.ニコルは、51年前の東京オリンピック以前の自然(または「高度経済成長前の日本の自然」)は素晴らしいものだったと言います。当時の日本は、自然と人々の暮らしが融合していました。燃料は薪を使い、衣食住は山の恵みから、そして動力は牛や馬。「山があれば生きていける」というのが日本人の暮らしでした。それが、ガスや石油を燃料とし、化学製品や輸入した食材・木材に依存する暮らし、言い換えると「お金があれば生きていける」というライフスタイルへ変化してしまったのです。日本人が、自然なんてどうでもいいと思い始めたのは、この頃からではないでしょうか。
C.W.ニコルは、故郷・ウェールズで、石炭採掘のため一旦は荒れ果ててしまったものの、人々の手で再生を果たしたアファンに習い、1986年、長野県黒姫で荒廃した森を買い取り、整備を始めました。これがアファンの森です。この森は、2013年現在305,572㎡にまで広がり、長野県レッドリスト掲載種のうち58種の希少生物や、生態系の豊かさの指標となるフクロウやツキノワグマも確認されるなど、生物多様性豊かな自然の森になりました。
 隣接する国有林とは、航空写真で見るとその境目が一目瞭然です。「人間のためだけの木の畑」と呼ばれるスギやヒノキの人工林は、自然の乏しさが上空からでも色となって表れ、森の中へ入れば、間伐が行き届いていないために荒れて死んだ森になっています。その森を「維持するため」と称して私たちの税金が使われているわけですが、それでいて日本人は木材自由化以来、外材に頼った生活をしています。また、スギは成長が速く、栄養分を土壌から大量に吸収する一方で、落ちた葉が分解されにくいため土地が痩せていきます。さらに、スギだけを植えている森は、その環境が好きな生き物しか生きられないため、生態系も貧弱になります。こうした人工林が森林の41%も占めている国を、皆さんはどう思いますか?森林に関する日本の2つの罪は、世界中の木を切り続けていることと、日本の森をほったらかしにしていることなのです。
隣接する国有林とは、航空写真で見るとその境目が一目瞭然です。「人間のためだけの木の畑」と呼ばれるスギやヒノキの人工林は、自然の乏しさが上空からでも色となって表れ、森の中へ入れば、間伐が行き届いていないために荒れて死んだ森になっています。その森を「維持するため」と称して私たちの税金が使われているわけですが、それでいて日本人は木材自由化以来、外材に頼った生活をしています。また、スギは成長が速く、栄養分を土壌から大量に吸収する一方で、落ちた葉が分解されにくいため土地が痩せていきます。さらに、スギだけを植えている森は、その環境が好きな生き物しか生きられないため、生態系も貧弱になります。こうした人工林が森林の41%も占めている国を、皆さんはどう思いますか?森林に関する日本の2つの罪は、世界中の木を切り続けていることと、日本の森をほったらかしにしていることなのです。
間違いだらけの林野行政
 森の再生活動を始めて29年。アファンの森は、様々な生物の棲みかとなり、命の環が戻ってきました。そして今後、日本の伝統的な里山文化が甦る未来を作っていくため、馬による地域社会と森との繋がりを取り戻そうとしています。馬は、古くから人とパートナーシップを築いてきた動物です。ところが高度経済成長以降、里山資源が見放されたのと同時に、馬や牛などの活用も日本の風景から姿を消してしまいました。
森の再生活動を始めて29年。アファンの森は、様々な生物の棲みかとなり、命の環が戻ってきました。そして今後、日本の伝統的な里山文化が甦る未来を作っていくため、馬による地域社会と森との繋がりを取り戻そうとしています。馬は、古くから人とパートナーシップを築いてきた動物です。ところが高度経済成長以降、里山資源が見放されたのと同時に、馬や牛などの活用も日本の風景から姿を消してしまいました。
 馬搬への取り組みのキッカケとなったのは、隣接する国有林をアファンの森が整備することになったことです。間伐期を過ぎても放置され続けている国有林について林野庁に質問すると、その答えは「伐り出す道がないから」というものでした。彼らにとって重要なのは、良い木を残すことではなく、高性能林業機械を入れるために林道を造ることなのです。必要なのは、間伐選定できる林業家ではなく、重機を扱えるオペレーターなのです。私たちが納めている森林環境税も、良い森林を育成するために使われているわけではなく、林道造成のため土木業者に流れているということをご存知でしょうか。そして、間伐が行われるにしても、全体を適正間隔で間伐をする定性間伐ではなく、あるエリアをごっそり刈り取る列状間伐や60%間伐と言われるものなのです。
馬搬への取り組みのキッカケとなったのは、隣接する国有林をアファンの森が整備することになったことです。間伐期を過ぎても放置され続けている国有林について林野庁に質問すると、その答えは「伐り出す道がないから」というものでした。彼らにとって重要なのは、良い木を残すことではなく、高性能林業機械を入れるために林道を造ることなのです。必要なのは、間伐選定できる林業家ではなく、重機を扱えるオペレーターなのです。私たちが納めている森林環境税も、良い森林を育成するために使われているわけではなく、林道造成のため土木業者に流れているということをご存知でしょうか。そして、間伐が行われるにしても、全体を適正間隔で間伐をする定性間伐ではなく、あるエリアをごっそり刈り取る列状間伐や60%間伐と言われるものなのです。
 因みに、農水省の圃場整備事業も同じような発想です。機械が入りやすいように田んぼをコンクリート化したため、田んぼの生態系が失われ、農薬が不可欠、また水を引くためのポンプが必要となり、石油がないとお米が作れません。効率化ばかりを追い求め、生物の多様性、伝統的技術、人と人の絆を失ってしまったのが、現在の林業や農業の姿なのです。そこで私たちは、国有林の整備に取り組むに当たって、運び出せないなら馬を使おうという結論に至りました。
因みに、農水省の圃場整備事業も同じような発想です。機械が入りやすいように田んぼをコンクリート化したため、田んぼの生態系が失われ、農薬が不可欠、また水を引くためのポンプが必要となり、石油がないとお米が作れません。効率化ばかりを追い求め、生物の多様性、伝統的技術、人と人の絆を失ってしまったのが、現在の林業や農業の姿なのです。そこで私たちは、国有林の整備に取り組むに当たって、運び出せないなら馬を使おうという結論に至りました。
馬が連れてくる“懐かしい未来”
 現在日本では、馬によって木を運ぶ馬搬を現役で行っているのは、岩手県遠野の5名のみです。一方イギリスでは、近年ホースロギングが見直され、環境配慮型の小規模林業やエコツーリズムの手法として活躍の場を広げています。このため、アファンの森では2012年から3年に亘って、岩手から馬を調達して馬搬に取り組んでいます。
現在日本では、馬によって木を運ぶ馬搬を現役で行っているのは、岩手県遠野の5名のみです。一方イギリスでは、近年ホースロギングが見直され、環境配慮型の小規模林業やエコツーリズムの手法として活躍の場を広げています。このため、アファンの森では2012年から3年に亘って、岩手から馬を調達して馬搬に取り組んでいます。
馬は、本来小規模型を目指すべき日本の林業の問題を解決し得る手法だと私たちは考えています。まず、草食動物である馬は、草を食べて動力源となるばかりでなく、その排泄物は土地を肥沃にします。また、林道がなくても搬出作業が可能で、馬が通ることで自然に道も出来ていきます。更に、重機が入ると土地は圧縮され、周囲の木を傷つける可能性もありますが、馬が歩けば土壌はほぐされ、木を傷めることもありません。そして何より、働く馬がいる風景は美しく、人々へのセラピー効果、子供達への教育効果、観光資源など、地域の活性化に繋がる要素を数多く持っています。
 林業というと、重くて、キツくて・・・と若い人が敬遠しがちなところもありましたが、「馬」という要素が加わる、その大変な部分は馬が請け負ってくれるわけですし、「馬ならば・・・」と若い女性が興味を示してくれるようにもなりました。また私たちは、馬搬によって伐り出した木材で製作した家具を、「ホースロギングファニュチャー」というブランディングをして販売するなど付加価値化の試みも始めています。
林業というと、重くて、キツくて・・・と若い人が敬遠しがちなところもありましたが、「馬」という要素が加わる、その大変な部分は馬が請け負ってくれるわけですし、「馬ならば・・・」と若い女性が興味を示してくれるようにもなりました。また私たちは、馬搬によって伐り出した木材で製作した家具を、「ホースロギングファニュチャー」というブランディングをして販売するなど付加価値化の試みも始めています。
この挑戦の先には、きっと“懐かしい未来”があると信じて、人と馬が共生し、地域を再生することを本気で目指しているのです。
構成・文:宮崎伸勝/写真:黒須一彦