損保ジャバンは、埼玉県、嵐山町と森林づくり協定を締結しました。植樹、森林整備、生態系保全活動などを行い、地域の皆様と交流を図って参ります。これを記念し、揖保ジャパンと日本環境教育フォーラムが17年間共催してきました「市民のための環境公開講座」をシンポジウム形式で開催しました。森林は、CO2を吸収するとともに、清らかな水やきれいな空気を生み出し、生物の多様性を保全するなど、私たちに様々な恵をもたらしてくれます。荒廃した森のチカラを甦らせ、森と共生していくにはどうしたらよいのか考えていきます。
開会挨拶
 地球温暖化は、今や人類の緊急の課題となっています。この温暖化による降雨、あるいは集中豪雨、干ばつ、食糧生産への影響、伝染性の病気の蔓延、こういったことが現実のものになってきています。特に損害保険業界は、地球温暖化の経済的影響を最も受けている業界の一つであると言えます。損害保険業界にとっては、地球温暖化の影響は将来の話ではなく既に何年も前から現実の問題となっており、こうした背景もあり、損保ジャパンを含む損害保険業界は金融機関のなかで早くから地球温暖化問題に取り組んできております。
地球温暖化は、今や人類の緊急の課題となっています。この温暖化による降雨、あるいは集中豪雨、干ばつ、食糧生産への影響、伝染性の病気の蔓延、こういったことが現実のものになってきています。特に損害保険業界は、地球温暖化の経済的影響を最も受けている業界の一つであると言えます。損害保険業界にとっては、地球温暖化の影響は将来の話ではなく既に何年も前から現実の問題となっており、こうした背景もあり、損保ジャパンを含む損害保険業界は金融機関のなかで早くから地球温暖化問題に取り組んできております。
一方、地球温暖化に並んで重要なのが生物多様性の問題です。2010年10月に名古屋で生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が開催されますが、人類がこの生物多様性から受けている恩恵は非常に大きなものです。これが失われると、我々の文化、あるいは生命が喪失してしまう恐れもあります。私たちの企業の事業活動は生物多様性に負荷を与えているという認識を持ち、経済界としても生物多様性に対応しなければならないと考えています。私が副会長を務める日本経済団体連合会自然保護協議会では、2009年3月に、生物多様性に関する企業としての行動指針を定めた生物多様性宣言を発表いたしました。
また、損保ジャパンとしてもこうした地球環境問題に対応するため、1990年に国内の金融機関として初めて環境の専門部署を作り、さまざまな環境問題に取り組んでまいりました。その一環として、1993年から「市民のための環境公開講座」を社団法人日本環境教育フォーラムの皆さまと一緒に開催しております。また、国内6か所の自治体と森林協定を締結し、森づくりを進めてまいりました。そして2009年3月に、首都圏では初めて、埼玉県嵐山町と協定を締結し、嵐山町内の「損保ジャパン・首都圏ふれあいの森」の整備活動に、特定非営利活動法人樹木・環境ネットワーク協会の皆さまと共に取り組み始めました。今回のシンポジウムは、その活動のスタートを記念して開催させていただくものです。今後5年間、植樹・間伐などの森林整備活動や、同地に生息する国蝶で絶滅が危惧されているオオムラサキなどの保全活動に、損保ジャパンの社員、家族、代理店の皆さまなど多くの関係者の力を合わせて取り組んでいきたいと考えています。
ショートレクチャー「森林の価値」
我が国の森林面積は、昭和41年から平成19年までほとんど変わっていません。そのうち人工林は、戦後すぐの約500万haから56年までに約1000万haまで増加しています。森林蓄積(森林を構成する木の体積)も増加し続けており、昭和41年には18億m3だったのが平成19年には44億m3となりました。これをみれば伐採されて尚かつ残っている数字で、最近では毎年約8000万m3/年が増加しています。このように数量的みれば日本の森林は充実してきているのですが、実質は間伐されずに荒れた森が多く、鹿が若芽を食べてしまうなどの獣害、そしてナラ枯れの被害なども著しく、決して楽観視できるものではありません。
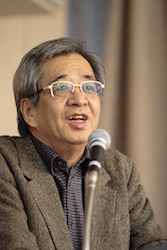 また、我が国の林業の状況は厳しくなっています。林業が経済的に成り立たない状況は、昭和40年代から始まりました。まだその頃は、木材価格は上がっていましたが、同時に労賃も猛烈なスピードで上がっていました。林業にかかるコストは、その殆どが人件費で、労賃自体が採算性に響きます。昭和35年頃と現在とを比べると、労賃が20倍になっているのに対して、木材価格は当時の価格にまで下落しているのです。
また、我が国の林業の状況は厳しくなっています。林業が経済的に成り立たない状況は、昭和40年代から始まりました。まだその頃は、木材価格は上がっていましたが、同時に労賃も猛烈なスピードで上がっていました。林業にかかるコストは、その殆どが人件費で、労賃自体が採算性に響きます。昭和35年頃と現在とを比べると、労賃が20倍になっているのに対して、木材価格は当時の価格にまで下落しているのです。
昭和40年代後半というのは、ちょうど公害問題や環境保全問題が取り沙汰された時代で、森林についても木材生産という役割だけでなく、森林の持つ公益的機能も発揮するべきだと言われるようになりました。そのために、経済的の仕組みの外側にある森林の公益的機能を内部化し、経済的価値を付与することができないかという議論が持ち上がります。そして、昭和47年に森林の公益的機能に対する評価額として、林野庁では年間12兆8000億円という金額が発表しました。さらに、最近の日本学術会議の発表では、75兆円と算出しています。一方で、森林の持つ機能の全てを計算することはできないので、こうした評価額を算出すべきでないという議論もあります。例えば、土砂災害防止機能や水源涵養機能など物理的計算が可能な点については計算されていますが、生物多様性の保全や、快適環境の形成の機能など、計算不可能なものがたくさんあり、それらはこの評価額に含まれていないのです。ですから、私たちが森林の価値を考える場合、次の3つのポイントに留意する必要があります。
- 1. 経済的価値だけでは森林の価値の全てを捉えることはできない
- 2. 経済的価値で評価しきれない部分をどう認識するのか
- 3. 森林の機能は重層的であるが、それぞれの森林において少しずつ求められる役割が異なる
森林は手入れをすれば、その価値を高めていくことができます。冒頭にお話しした通り、日本の森林は数量的には上がってきているので、あとは私たちが適切な管理をすればその機能はさらに高まっていきます。そのための重要なときを迎えています。
パネリスト活動紹介
 嵐山町は、国蝶・オオムラサキが生息する自然の宝庫で、畠山重忠や木曽義仲など坂東武者ゆかりの地として知られています。埼玉県のほぼ中央に位置しており、都心から60km圏にあります。人口は19,093人(平成21年11月1日現在)。まとまった市街地の周囲に農地や山林がある、住みよい街です。
嵐山町は、国蝶・オオムラサキが生息する自然の宝庫で、畠山重忠や木曽義仲など坂東武者ゆかりの地として知られています。埼玉県のほぼ中央に位置しており、都心から60km圏にあります。人口は19,093人(平成21年11月1日現在)。まとまった市街地の周囲に農地や山林がある、住みよい街です。
またこの街は、平成8年に「さいたま緑のトラスト保全第3号地(武蔵嵐山渓谷周辺樹林地)」に指定されました。嵐山町という地名は、このトラスト地の下流域が発祥です。日比谷公園設計者でもある日本初の林学博士・本多静六氏が、昭和の初めにこの渓谷地を訪れた際、京都の嵐山に似ていると思われ、「武蔵嵐山」と話されたのがはじまりとされています。現在は、比企里やまの会や財団法人さいたま緑のトラスト協会嵐山支部によって、毎週火曜日に下草刈りや樹木の間伐、毎月第一日曜日に観察会が行われています。
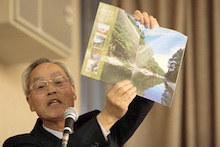 嵐山町の森づくりには長い歴史があり、昭和56年から開始しています。そして現在、嵐山町の森林面積の約5%にあたる45haを公有地化して、将来に残していこうと取り組んでいます。平成19年には、嵐山町里地里山づくり条例を制定し、活動地域を定め、子供達との交流活動や間伐などの活動を行っています。また、公有地化した千手堂小千代山の約3.7haの里山では、嵐山モウモウ緑の少年団が、間伐、椎茸の駒打ちなどの整備活動に取り組んでおり、東京・板橋区にある環境学習施設エコポリスセンターとの交流の場にもなっています。この他、森林伐採され、産業廃棄物が持ち込まれた疑いがあった将軍澤地域も、競売にかかった際に参加し、約4000万円かけて公有地化を実現しました。現在は町民の皆様によって広葉樹の植樹が行われ、保全活動が進んでいます。
嵐山町の森づくりには長い歴史があり、昭和56年から開始しています。そして現在、嵐山町の森林面積の約5%にあたる45haを公有地化して、将来に残していこうと取り組んでいます。平成19年には、嵐山町里地里山づくり条例を制定し、活動地域を定め、子供達との交流活動や間伐などの活動を行っています。また、公有地化した千手堂小千代山の約3.7haの里山では、嵐山モウモウ緑の少年団が、間伐、椎茸の駒打ちなどの整備活動に取り組んでおり、東京・板橋区にある環境学習施設エコポリスセンターとの交流の場にもなっています。この他、森林伐採され、産業廃棄物が持ち込まれた疑いがあった将軍澤地域も、競売にかかった際に参加し、約4000万円かけて公有地化を実現しました。現在は町民の皆様によって広葉樹の植樹が行われ、保全活動が進んでいます。
そしてこの度、埼玉県森林づくり協定により、花見台にある約8.29haという広大な森林を、損保ジャパンさんが維持管理してくださることが決まりました。この協定は5年間ですが、その後を町としてしっかりと受け継ぎ、将来のために森を育てていきたいと思っています。
 私は東京・あきる野市で林業を営んでいます。我が家は6代前から専業林家で、林地はあちこちに点在していますが、合計すると180haくらいになります。そのうち人口林率は約80%で、樹齢平均は40年あまり、スギとヒノキが半々の比率であります。先ほど加藤さんのお話にもありましたが、父の相続発生の18年前にすでに木材価格は年々下落しており、その4年前の大きな雪害の復旧もまだできておらず、さらには、都市近郊林はバブルの影響から土地の評価額も高いため、相続税の支払にも頭が痛い日々でした。
私は東京・あきる野市で林業を営んでいます。我が家は6代前から専業林家で、林地はあちこちに点在していますが、合計すると180haくらいになります。そのうち人口林率は約80%で、樹齢平均は40年あまり、スギとヒノキが半々の比率であります。先ほど加藤さんのお話にもありましたが、父の相続発生の18年前にすでに木材価格は年々下落しており、その4年前の大きな雪害の復旧もまだできておらず、さらには、都市近郊林はバブルの影響から土地の評価額も高いため、相続税の支払にも頭が痛い日々でした。
そんな状況ではありますが、16年前に「林土戸(りんどこ)」という森林ボランティアを受け入れ、以後、途切れること無く森林ボランティアがやってきてくれています。また、4人のミセスによってスタートした「そらあけの会」は今年で11年目になり、その他にもいくつかのグループがやってきて、月に3〜4回は、山に入って整備作業をして頂いています。山に入ってスギヒノキの生命を育むことや、それを見守ることが楽しい、自分自身が癒されるといいという声を聞いたり、これらのボランティア仲間の間で結婚することがあったりします。彼らの存在は私自身にとって大きなプレゼントです。
 しかし現在、林業は第一次産業として成り立ちません。伐った木を搬出する経費の方が売る値段より高く、赤字になってしまうような状況です。また、広葉樹林はかつて薪炭林として重用されていましたが、今では薪や炭を使う生活は無くなってしまいました。もはや木が使われない社会になったのならば、それならそれで仕方がないですが、現実には大量の木材を使用し、その80%近くを外材に頼っているのが今の日本なのです。ですからやはり、日本の木を使って頂きたいと私たちは思っています。林野庁や自治体が公的資金を導入して力を入れてくれていますが、それが長続きするのか、そして税金を使うことの是非も問われるところです。やはり林業が一本立ちしてやっていけるような新しい形を作っていかなければならないと思います。
しかし現在、林業は第一次産業として成り立ちません。伐った木を搬出する経費の方が売る値段より高く、赤字になってしまうような状況です。また、広葉樹林はかつて薪炭林として重用されていましたが、今では薪や炭を使う生活は無くなってしまいました。もはや木が使われない社会になったのならば、それならそれで仕方がないですが、現実には大量の木材を使用し、その80%近くを外材に頼っているのが今の日本なのです。ですからやはり、日本の木を使って頂きたいと私たちは思っています。林野庁や自治体が公的資金を導入して力を入れてくれていますが、それが長続きするのか、そして税金を使うことの是非も問われるところです。やはり林業が一本立ちしてやっていけるような新しい形を作っていかなければならないと思います。
東京の多摩地域は林業特区だと私は思っています。山を持っている者が、人工林がどうして大切なのかということを市民の皆さんにPRしていく必要があります。山で収益を得て、手入れの費用を捻出するためでもあり、国産材を使っていただくことで環境への多大な効果があるのです。そこで私たちは、「屋根の無い博物館」を目指し、地元製材所もみてもらう「東京・森の学校」を2009年春にスタートさせました。より多くの市民の皆さんに山に入って頂き、林業や山の恵み、そして生物多様性などについて自然の中で知って頂く機会にして欲しいと思っています。
 私の所属するキープ協会は、山梨県の八ヶ岳山麓地域にあります。KEEPとは、“Kiyosato Educational Experiment Project=清里教育実験計画”の略称で、「教育」「環境」「実験」というキーワードで活動しています。東京ドーム45個分という広大なフィールドに、豊かな森と牧草地を有し、様々な森林管理プログラムを実施し、近年では食育にも取り組んでいます。
私の所属するキープ協会は、山梨県の八ヶ岳山麓地域にあります。KEEPとは、“Kiyosato Educational Experiment Project=清里教育実験計画”の略称で、「教育」「環境」「実験」というキーワードで活動しています。東京ドーム45個分という広大なフィールドに、豊かな森と牧草地を有し、様々な森林管理プログラムを実施し、近年では食育にも取り組んでいます。
私たちは、成長段階ごとの環境教育の狙いを次のように定めています。まず、小学校に入る前の幼年期の子供達は、「Nature(自然)」「Human(人間、文化、社会)」の中で(in)、直接体験や感性に訴えかけるプログラムを通して、思い切り遊ぶことが大切だと思っています。またこれは、経験の薄い大人の方に対しても有効です。
続いて、小中学校の学齢期の子供達には、「about」というステップで、「自然」「文化」について知識や技術を学び、興味があることをとことん調べてみることを促します。
そして、最終段階が「for」です。「自然のために」「人のために」行動できる人を育成するということが目標となります。大きなことではなく、小さなことからでも何か行動をおこしてみることを喚起します。
 また、「健康」というキーワードで、2005年度から「森療時間(しんりょうじかん)」という森林療法・森林セラピーなどのプログラムも行っています。我々環境教育関係者と、医療機関がそれぞれの得意分野を発揮し、協働で実施しています。例えば森の中を歩くと気持ちいいものですが、それによって血圧がどう変化するのかなどもチェックします。このように感性と科学両方からのアプローチするのがこのプログラムの特徴です。
また、「健康」というキーワードで、2005年度から「森療時間(しんりょうじかん)」という森林療法・森林セラピーなどのプログラムも行っています。我々環境教育関係者と、医療機関がそれぞれの得意分野を発揮し、協働で実施しています。例えば森の中を歩くと気持ちいいものですが、それによって血圧がどう変化するのかなどもチェックします。このように感性と科学両方からのアプローチするのがこのプログラムの特徴です。
森は学びの場であり、健康づくりの場でもあります。私たちは、そんな森に恩返しをしたいという気持ちで、「森も元気に、人も元気に!」を合言葉に、環境教育に取り組んでいます。
パネルディスカッション
- 加藤 鐵夫氏社団法人日本森林技術協会 専務理事
- 高橋 兼次氏埼玉県嵐山町 副町長
- 池谷 キワ子氏林業家、NPO法人森づくりフォーラム 理事
- 増田 直広氏財団法人キープ協会 環境教育事業部
- コーディネーター瀬田 信哉(社)日本環境教育フォーラム 理事
 瀬田 私は三浦しをんさんの「神去なあなあ日常」を読みましたが、この他にも「ゴチソウ山」など森と地域住民の関わりをテーマにした本が増えたように思います。森が語られるようになったということは、木が語り出した、とも言えるかもしれません。まず、加藤さんに伺いたいのは、森を手入れし、育てていくためには林道が必要ですが、その現状はどうなっているのでしょうか。
瀬田 私は三浦しをんさんの「神去なあなあ日常」を読みましたが、この他にも「ゴチソウ山」など森と地域住民の関わりをテーマにした本が増えたように思います。森が語られるようになったということは、木が語り出した、とも言えるかもしれません。まず、加藤さんに伺いたいのは、森を手入れし、育てていくためには林道が必要ですが、その現状はどうなっているのでしょうか。
 加藤 林道は、路網密度、つまりヘクタール当たり何メートルの道路がついているのかという指標で議論されます。この路網密度が、日本はヨーロッパと比較して極めて低く、ドイツが118m、オーストリア87mなのに対して、日本は16mです。日本は急峻な地形で、地質的にも崩れやすいため、林道を作るのにお金がかかるのです。ドイツだと1mあたり数百〜数千円でできるのが、日本では数万円〜十数万円単位になります。日本でも低コストで林道ができないかということが、大きな課題となっています。しかも効率的な運搬のためには、作業道だけでなく、大型トラックが通れる広い道も必要です。幹となる林道、枝となる作業道の両方を合わせてもっと作っていかなければならなりません。これが日本の林道を巡る現状です。
加藤 林道は、路網密度、つまりヘクタール当たり何メートルの道路がついているのかという指標で議論されます。この路網密度が、日本はヨーロッパと比較して極めて低く、ドイツが118m、オーストリア87mなのに対して、日本は16mです。日本は急峻な地形で、地質的にも崩れやすいため、林道を作るのにお金がかかるのです。ドイツだと1mあたり数百〜数千円でできるのが、日本では数万円〜十数万円単位になります。日本でも低コストで林道ができないかということが、大きな課題となっています。しかも効率的な運搬のためには、作業道だけでなく、大型トラックが通れる広い道も必要です。幹となる林道、枝となる作業道の両方を合わせてもっと作っていかなければならなりません。これが日本の林道を巡る現状です。
瀬田 池谷さんに質問致しますが、林業のサイクルに関する問題点をもう少し詳しく教えて下さい。
 池谷 まず、今お話に出た林道のことですが、東京の場合は、小規模林業家が多く、例えばたった1haの森林に林道を造れば、返って森林が無くなってしまうとか、地形が険峻のため、東京の林道密度はとても低いという現状があります。また、林業のサイクルは50〜60年ですが、それだけの年月が経ったら、材木価格が大きく下落し、時代が急変して今や伐ってもほとんどお金が手に入らない時代になってしまいました。そこで、70〜 100年までも待ちたいのですが、その間には相続税の問題もあり、なかなか待ちきれない状況です。また、折角伐らずにおいても、災害が起きる可能性もあります。このように林業のサイクルは様々な難しい判断があるのです。
池谷 まず、今お話に出た林道のことですが、東京の場合は、小規模林業家が多く、例えばたった1haの森林に林道を造れば、返って森林が無くなってしまうとか、地形が険峻のため、東京の林道密度はとても低いという現状があります。また、林業のサイクルは50〜60年ですが、それだけの年月が経ったら、材木価格が大きく下落し、時代が急変して今や伐ってもほとんどお金が手に入らない時代になってしまいました。そこで、70〜 100年までも待ちたいのですが、その間には相続税の問題もあり、なかなか待ちきれない状況です。また、折角伐らずにおいても、災害が起きる可能性もあります。このように林業のサイクルは様々な難しい判断があるのです。
瀬田 高橋さんに質問致しますが、嵐山町のシンボルでもあるオオムラサキの里近くには、先般事業仕分けで話題になった国立女性教育会館がありますが、ここを訪れる方々も、周囲にある嵐山の自然の中に入っていくようなケースがあるのでしょうか。
高橋 年間たくさんの人達がこの会館を訪れますが、それらの皆さんからこの地域の自然に案内して欲しいという要望もあるようです。特にオオムラサキが羽化をする場面は非常に感動的ですばらしい体験になると思いますので、このような時期に合わせて会館を訪れた方を嵐山町の自然に案内できるようにしていきたいと考えております。
年間たくさんの人達がこの会館を訪れますが、それらの皆さんからこの地域の自然に案内して欲しいという要望もあるようです。特にオオムラサキが羽化をする場面は非常に感動的ですばらしい体験になると思いますので、このような時期に合わせて会館を訪れた方を嵐山町の自然に案内できるようにしていきたいと考えております。
瀬田 増田さんへの質問ですが、先ほど映写していた、キープ協会の環境教育活動を紹介するスライドの中で、小さな子供達が自分達で木を伐っている写真がありましたが、これはどのようなプログラムなのでしょうか。
 増田 自然の中で幼児教育を行う「森のようちえん」という活動が全国的に展開されています。キープ協会でも「キープ森のようちえん」「清里子ども自然クラブ」というプログラムを実施しており、子供達から木に触れてみたい、伐ってみたいという声が挙がれば、きちんと安全を確保しつつ、自分達で体験してもらうこともあります。
増田 自然の中で幼児教育を行う「森のようちえん」という活動が全国的に展開されています。キープ協会でも「キープ森のようちえん」「清里子ども自然クラブ」というプログラムを実施しており、子供達から木に触れてみたい、伐ってみたいという声が挙がれば、きちんと安全を確保しつつ、自分達で体験してもらうこともあります。
瀬田 加藤さんの発表で、獣害についてのお話が出ましたが、これは農業においても、林業においても深刻な問題です。この問題について詳しくお聞かせください。
 加藤 森林は多面的機能を持っており、野生生物と共存していける仕組みをどう作っていくのかというのも、森林のことを考える上で大変重要な課題です。ですから、シカによる被害についてだけを論じるのは単眼的です。ただし、林業では、近年シカが増え、被害が増大してその対策が重大な問題となっています。シカが増えてきている原因の一つには、雪が積もらなくなってきたことがあります。雪が積もると、6〜7月頃に生まれた子供が育ちきらないうちに雪の中で動けなくなるので、生存率が低下するそうです。また、狩猟者が減ってきたということや、森林管理がなされていないため、シカの領域が広がっていることなど色々な理由が考えられます。まずは、シカと森林がどのように共存していけるのかを考えることが第一ですが、現状をみるとシカの捕獲についても考慮せざるを得ません。シカ避けの網を張って対策を講じていますが、これには莫大なお金がかかります。これを漁網で代用すると、漁網には塩分が含まれているのでシカが食べてしまうというような話を聞いたこともあります。ステンレスの網なら大丈夫だそうですが、シカに対してそこまでコストをかけるとなると、もはや林業者が対応できるレベルを越えてしまいます。現状を把握し、管理保全計画を立て個体数管理を行っていくことが必要だと思います。
加藤 森林は多面的機能を持っており、野生生物と共存していける仕組みをどう作っていくのかというのも、森林のことを考える上で大変重要な課題です。ですから、シカによる被害についてだけを論じるのは単眼的です。ただし、林業では、近年シカが増え、被害が増大してその対策が重大な問題となっています。シカが増えてきている原因の一つには、雪が積もらなくなってきたことがあります。雪が積もると、6〜7月頃に生まれた子供が育ちきらないうちに雪の中で動けなくなるので、生存率が低下するそうです。また、狩猟者が減ってきたということや、森林管理がなされていないため、シカの領域が広がっていることなど色々な理由が考えられます。まずは、シカと森林がどのように共存していけるのかを考えることが第一ですが、現状をみるとシカの捕獲についても考慮せざるを得ません。シカ避けの網を張って対策を講じていますが、これには莫大なお金がかかります。これを漁網で代用すると、漁網には塩分が含まれているのでシカが食べてしまうというような話を聞いたこともあります。ステンレスの網なら大丈夫だそうですが、シカに対してそこまでコストをかけるとなると、もはや林業者が対応できるレベルを越えてしまいます。現状を把握し、管理保全計画を立て個体数管理を行っていくことが必要だと思います。
 瀬田 ここで、会場の皆さんから何か質問があればお伺いしたいと思います。
瀬田 ここで、会場の皆さんから何か質問があればお伺いしたいと思います。
質問 今、あきる野や西多摩地域で、どの程度森林ボランティアが必要とされているのでしょうか。私たちは都内の森林整備にどれくらい役に立つことができるのでしょうか。池谷さんにお答え頂けますでしょうか。
 池谷 我が家の森林整備に関してはかなりの成果で、ボランティアの皆さんに心から感謝をしていますが、一般的には、ボランティアだけでは森林整備はほとんど進みません。ボランティアの皆さんには、参加してもらって森の現状を周りの人々にPRして頂いたり、ご自身の健康やスポーツとしてやって頂くのがいいと思います。山は急峻で危険な場所も多いので、安全に森を整備するためには絶対にプロが必要です。その裾野にボランティアがいて、近くの森や街の人々との橋渡し役になって頂きたいと思います。
池谷 我が家の森林整備に関してはかなりの成果で、ボランティアの皆さんに心から感謝をしていますが、一般的には、ボランティアだけでは森林整備はほとんど進みません。ボランティアの皆さんには、参加してもらって森の現状を周りの人々にPRして頂いたり、ご自身の健康やスポーツとしてやって頂くのがいいと思います。山は急峻で危険な場所も多いので、安全に森を整備するためには絶対にプロが必要です。その裾野にボランティアがいて、近くの森や街の人々との橋渡し役になって頂きたいと思います。
質問 増田さんが紹介された「森療時間」ですが、参加された人々に、どの程度の自律神経への効果があったのか紹介して頂けないでしょうか。
 増田 血圧測定やストレスチェック機による測定では、ほとんどの方がプログラム後に数値が低くなっている、あるいは安定しているという結果が出ています。自律神経の測定では、非常にたくさんの種類の数値が出るので、それらを読み解くことが必要になります。そこで、先ほどご紹介したように、医療機関からのサポートを受けてプログラムを実施しています。
増田 血圧測定やストレスチェック機による測定では、ほとんどの方がプログラム後に数値が低くなっている、あるいは安定しているという結果が出ています。自律神経の測定では、非常にたくさんの種類の数値が出るので、それらを読み解くことが必要になります。そこで、先ほどご紹介したように、医療機関からのサポートを受けてプログラムを実施しています。
質問 放牧を間伐に活用しているという林業の事例を見たのですが、この方法は実際に有効なのでしょうか。
池谷 それは林内放牧による下刈りの省力化のことだと思います。理論的には私もいい方法だと思うのですが、私の大先輩で女性林業家の草分けと言われている大橋和子さんによれば、試みてみたものの結局収益が上がらず撤退したと自著に書いていらっしゃいました。結局、酪農家の方が森林に放牧をすることはあっても、林業家が家畜を飼うということはよほど本腰をいれてやらないと理だと思います。
 瀬田 今日は皆さんから色々なお話を伺うことができましたが、最後にまとめさせて頂きます。私の家では以前、障子紙が破れたら和紙を木の葉状にちぎり貼って補修していました。同様のことをしているお宅もあるのではないでしょうか。我々日本人は、このように木と紙の文化の中で暮らしてきたと言えます。我々は日々の生活のどこかで木と接点を持って暮らしているはずです。機械文明が発達し、工業製品が頑丈なものを作り出し、障子紙のように壊れやすいものは良くないという風潮になっています。部分品の修理より全体を取り替える方が安いという時代です。そのことがモノを乱暴に扱うことに繋がっているような気がしてなりません。木の文化の中で生きてきた私たちは、モノを大切に使うことを知っています。それは作法という形に結実し、一つひとつの作法が生活の中で文化になっています。ものに対する作法とは、則ち優しさとも言えると思います。日常の中に私たちが優しさを取り入れるためにも、もっと木を使うことが必要なのではないでしょうか。これも、今回のテーマである「森のチカラ」の一つではないかと思います。
瀬田 今日は皆さんから色々なお話を伺うことができましたが、最後にまとめさせて頂きます。私の家では以前、障子紙が破れたら和紙を木の葉状にちぎり貼って補修していました。同様のことをしているお宅もあるのではないでしょうか。我々日本人は、このように木と紙の文化の中で暮らしてきたと言えます。我々は日々の生活のどこかで木と接点を持って暮らしているはずです。機械文明が発達し、工業製品が頑丈なものを作り出し、障子紙のように壊れやすいものは良くないという風潮になっています。部分品の修理より全体を取り替える方が安いという時代です。そのことがモノを乱暴に扱うことに繋がっているような気がしてなりません。木の文化の中で生きてきた私たちは、モノを大切に使うことを知っています。それは作法という形に結実し、一つひとつの作法が生活の中で文化になっています。ものに対する作法とは、則ち優しさとも言えると思います。日常の中に私たちが優しさを取り入れるためにも、もっと木を使うことが必要なのではないでしょうか。これも、今回のテーマである「森のチカラ」の一つではないかと思います。
講演「森から未来を見る」
 私は、今までどんな国よりも長く日本に住んでいます。日本が大好きです。その理由は数えればきりがありません。日本には自由があります。宗教の自由もあり、またこれはとてもすごいことですが、宗教からの自由もあります。そして安全です。また、47年前に私が初めて日本の山を歩いた時、クマにあいました。これは驚くべきことです。カナダやアラスカに野性のクマがいるのは当たり前ですが、この人口密度の高い島国にまでいるということはショックですらありました。イギリスでは970年位前にクマが絶滅しました。また、ケルト人にとって一番のごちそうだったイノシシが絶滅したのは400年以上前のことです。近年になりようやく森を復活させ、場所によってはイノシシが見られるようになったという状況です。つまり、日本はとても自然豊かな国なのです。
私は、今までどんな国よりも長く日本に住んでいます。日本が大好きです。その理由は数えればきりがありません。日本には自由があります。宗教の自由もあり、またこれはとてもすごいことですが、宗教からの自由もあります。そして安全です。また、47年前に私が初めて日本の山を歩いた時、クマにあいました。これは驚くべきことです。カナダやアラスカに野性のクマがいるのは当たり前ですが、この人口密度の高い島国にまでいるということはショックですらありました。イギリスでは970年位前にクマが絶滅しました。また、ケルト人にとって一番のごちそうだったイノシシが絶滅したのは400年以上前のことです。近年になりようやく森を復活させ、場所によってはイノシシが見られるようになったという状況です。つまり、日本はとても自然豊かな国なのです。
 私が昔、カナダ政府の環境庁に勤めていた時、あるお年寄りから、森はサケが作ったのだという話を聞きました。皆さんも、クマが川でサケを食べている映像を観たことがあるのではないでしょうか。しかし実際は、クマは川で食べるよりも、大抵の場合、獲ったサケを森の中に持ち込んで食べます。しかもクマが食べる部位は決まっていて、かなりの食べ残しがあります。ですから、クマがサケを食べる森はとても生臭くなると言われています。ある研究者によると、一頭のクマは一年でおよそ700匹のサケを獲り、その食べ残しを森の中に捨てているそうです。木の年輪は、森とサケの関係をよりはっきりと表します。木の年輪には、どの年にどれくらい雨が降ったか、どんな病気に罹ったのかが残ります。サケの遡上する森の樹木の年輪からは、海にあって陸にはない安定元素である窒素が発見されます。そして、サケが遡上する森の木は、遡上しない森の木よりも、2倍半も太く育ちます。サケは森を元気にするのです。
私が昔、カナダ政府の環境庁に勤めていた時、あるお年寄りから、森はサケが作ったのだという話を聞きました。皆さんも、クマが川でサケを食べている映像を観たことがあるのではないでしょうか。しかし実際は、クマは川で食べるよりも、大抵の場合、獲ったサケを森の中に持ち込んで食べます。しかもクマが食べる部位は決まっていて、かなりの食べ残しがあります。ですから、クマがサケを食べる森はとても生臭くなると言われています。ある研究者によると、一頭のクマは一年でおよそ700匹のサケを獲り、その食べ残しを森の中に捨てているそうです。木の年輪は、森とサケの関係をよりはっきりと表します。木の年輪には、どの年にどれくらい雨が降ったか、どんな病気に罹ったのかが残ります。サケの遡上する森の樹木の年輪からは、海にあって陸にはない安定元素である窒素が発見されます。そして、サケが遡上する森の木は、遡上しない森の木よりも、2倍半も太く育ちます。サケは森を元気にするのです。
 私は子供の頃ロンドンの学校に通っていましたが、その頃のロンドンの川は臭くて、生き物は何もいませんでした。しかし今、ロンドンの川にはサケが戻ってきています。そして郊外の川にはカワウソがやってきています。私がなぜ今のような荒れた森を生態系が豊かな森へ復活させる活動をしているかというと、47年前に日本にやってきた時、クマやイノシシが生きることが出来る森を残してくれていたこの国に感謝する気持ちがあったからです。私が生まれた南ウェールズは、私が子供の頃、森林面積がたったの5%でした。人口が増え、産業が発展すれば、自然は消えるものだと思っていました。しかし今、南ウェールズの森林面積は60%にまで増えました。川もきれいになって、サケやイワナが戻ってきました。今、私は人間の努力と愛情があれば自然は復活すると信じています。但し、自然保護と放置は違います。原生林は守らなければ残していくことはできません。豊かな自然が残る日本で、これからもちゃんと「森人」を育てられれば、日本は新たなエデンの園になると思います。
私は子供の頃ロンドンの学校に通っていましたが、その頃のロンドンの川は臭くて、生き物は何もいませんでした。しかし今、ロンドンの川にはサケが戻ってきています。そして郊外の川にはカワウソがやってきています。私がなぜ今のような荒れた森を生態系が豊かな森へ復活させる活動をしているかというと、47年前に日本にやってきた時、クマやイノシシが生きることが出来る森を残してくれていたこの国に感謝する気持ちがあったからです。私が生まれた南ウェールズは、私が子供の頃、森林面積がたったの5%でした。人口が増え、産業が発展すれば、自然は消えるものだと思っていました。しかし今、南ウェールズの森林面積は60%にまで増えました。川もきれいになって、サケやイワナが戻ってきました。今、私は人間の努力と愛情があれば自然は復活すると信じています。但し、自然保護と放置は違います。原生林は守らなければ残していくことはできません。豊かな自然が残る日本で、これからもちゃんと「森人」を育てられれば、日本は新たなエデンの園になると思います。
 私は、47年前に日本に来た時、日記にこう書きました。「日本は子供の天国だ。これほど子供にいい国はない」。しかし今、日本の子供は減っているのに、施設に入れられる子供は増えています。その70%は、親から虐待を受けたか、育児放棄されたかです。そうした子供達を、私たちの財団が持つ森に招待し、森の中で楽しい時間を過ごしてもらうプログラムを行っています。色々なトラウマを抱えた子供達が、森で遊ぶ時の輝く瞳を見ていると、やはり森と人間との関わりの重要性を感じずにはいられません。日本では毎年約3万人もの自殺者がいます。そして虐待を受ける子供達も増えています。日本人はちょっと淋しくなっているのではないでしょうか。一体何が必要なのでしょう。私の答えは単純です。日本の自然を回復して、もっと元気な日本人になることです。人間の遺伝子、つまり子供の90何%はチンパンジーと同じようなものです。やはり猿には森が必要なのです。森は心の故郷だと私は思っています。この「故郷」を元気な状態にして未来に返しましょう。
私は、47年前に日本に来た時、日記にこう書きました。「日本は子供の天国だ。これほど子供にいい国はない」。しかし今、日本の子供は減っているのに、施設に入れられる子供は増えています。その70%は、親から虐待を受けたか、育児放棄されたかです。そうした子供達を、私たちの財団が持つ森に招待し、森の中で楽しい時間を過ごしてもらうプログラムを行っています。色々なトラウマを抱えた子供達が、森で遊ぶ時の輝く瞳を見ていると、やはり森と人間との関わりの重要性を感じずにはいられません。日本では毎年約3万人もの自殺者がいます。そして虐待を受ける子供達も増えています。日本人はちょっと淋しくなっているのではないでしょうか。一体何が必要なのでしょう。私の答えは単純です。日本の自然を回復して、もっと元気な日本人になることです。人間の遺伝子、つまり子供の90何%はチンパンジーと同じようなものです。やはり猿には森が必要なのです。森は心の故郷だと私は思っています。この「故郷」を元気な状態にして未来に返しましょう。
閉会挨拶
 本日は、ご登壇頂いた皆様には専門的かつ心に残るお話をいただき、心より感謝申し上げます。「森にチカラはあるのか?」というテーマで進めてきたわけですが、実は私自身も、C.W.ニコルさんが運営されているアファンの森へ7〜8年通っておりますが、20haもある土地を、足を踏み入れられないような状態から、25年かけてたった一人で、奥行きのある森にしたことに大変な感動を覚えました。しかも、このような偉業を成し遂げた方が、70歳を数年前に迎えられた方であることは、さらなる驚きであります。皆さんにもぜひ、この「理想的な森」を一度体験して頂きたいと思います。そしてまた、埼玉県嵐山町も東京から近い場所にありますので、ぜひ足をお運びになり、このような森が日本にあることを知って頂き、一緒に森づくりに協力頂ければと思います。本日は、ご参加ありがとうございました。
本日は、ご登壇頂いた皆様には専門的かつ心に残るお話をいただき、心より感謝申し上げます。「森にチカラはあるのか?」というテーマで進めてきたわけですが、実は私自身も、C.W.ニコルさんが運営されているアファンの森へ7〜8年通っておりますが、20haもある土地を、足を踏み入れられないような状態から、25年かけてたった一人で、奥行きのある森にしたことに大変な感動を覚えました。しかも、このような偉業を成し遂げた方が、70歳を数年前に迎えられた方であることは、さらなる驚きであります。皆さんにもぜひ、この「理想的な森」を一度体験して頂きたいと思います。そしてまた、埼玉県嵐山町も東京から近い場所にありますので、ぜひ足をお運びになり、このような森が日本にあることを知って頂き、一緒に森づくりに協力頂ければと思います。本日は、ご参加ありがとうございました。
構成・文:宮崎伸勝/写真:黒須一彦(エコロジーオンライン)