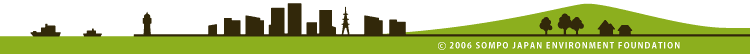私は、宮城県の気仙沼湾で牡蠣や帆立の養殖をしています。今、全国の海の環境が悪化していると言われる中で、この気仙沼湾は良くなってきています。それは20年ほど前、牡蠣の養殖業は、海に注ぎ込む川の流域の人々と価値観を共有しないと成り立たない事に気づき行動を起こしたからだと思います。 私は、宮城県の気仙沼湾で牡蠣や帆立の養殖をしています。今、全国の海の環境が悪化していると言われる中で、この気仙沼湾は良くなってきています。それは20年ほど前、牡蠣の養殖業は、海に注ぎ込む川の流域の人々と価値観を共有しないと成り立たない事に気づき行動を起こしたからだと思います。
私がこの仕事を継いだ昭和36年当時、牡蠣の養殖は「タネ」さえぶら下げておけばやれていたのですが、40年代を過ぎた頃からその成長が悪くなり、やがて赤潮が発生。赤潮は牡蠣を人間の血のような赤色に変色させてしまい、廃棄処分せざるを得ないという時代が続きました。
 気仙沼湾には、大川という二級河川が流れ込んでいます。私は「川をなんとかしなければ」という想いで、この川の上流へと上っていきました。河口には水産加工場が多く、そこから排出される廃水で石垣は油でギトギトになり異臭を放っていました。更に上がっていくと水田地帯になるのですが、本来であれば虫や蛙などで賑やかなはずの田んぼがシーンとしているのです。 気仙沼湾には、大川という二級河川が流れ込んでいます。私は「川をなんとかしなければ」という想いで、この川の上流へと上っていきました。河口には水産加工場が多く、そこから排出される廃水で石垣は油でギトギトになり異臭を放っていました。更に上がっていくと水田地帯になるのですが、本来であれば虫や蛙などで賑やかなはずの田んぼがシーンとしているのです。
農家の方に話を聞いた所、その理由は除草剤でした。しかし全ての雑草を手で抜く訳にもいかないと言うのです。私はもっと上流へと進んでみました。すると、川の幅がギュッと狭まり急峻な山が迫っているリアス式海岸地域特有の地形にぶつかりました。そこは土木工事に携わる方々にとっては、必要かどうかはともかく、思わずダムを作りたくなってしまうような格好の場所でした。実際にダムの建設計画もあり、もしそうなってしまったら森の養分が益々海に流れてこなくなり、水産資源に影響が出ることは容易に想像できました。このように川の河口から上流までを遡ると、そこにあるのは正に人間社会の縮図、つまり人間の欲の結果が残っているという状態だったのです。
 私は、何とかして流域に住んでいる人々に海の方を振り向いて貰いたいと思い、色々な行動を起こし始めました。その中で、事を動かすにはスローガンが必要だと考え、人の手も借りながら出来上がったのが『森は海の恋人』でした。そして平成元年、植樹祭やシンポジウムを行なった所、これが思いがけず大きな反響を呼び、また時代の追い風もあって、森・川・海を一つのものと捉える考え方が理解されるようになっていきました。 私は、何とかして流域に住んでいる人々に海の方を振り向いて貰いたいと思い、色々な行動を起こし始めました。その中で、事を動かすにはスローガンが必要だと考え、人の手も借りながら出来上がったのが『森は海の恋人』でした。そして平成元年、植樹祭やシンポジウムを行なった所、これが思いがけず大きな反響を呼び、また時代の追い風もあって、森・川・海を一つのものと捉える考え方が理解されるようになっていきました。
翌年には、川の流域に住む子供達を海に招待しました。船で沖まで出てそこから山を見せ、山から下りてきたものを牡蠣は食べていることを説明したり、実際に水の中にいる植物性プランクトンを試飲させたり、顕微鏡で見せたりして、いわば食物連鎖を体感して貰ったのです。その後子供達からは、「使うシャンプーの量を減らした」「お母さんに洗剤を分解しやすいものに変えてもらった」「お父さんに使う除草剤の量を減らして貰った」など様々な反応が戻ってきました。
 それ以来、これまでに8000人の子供達を招待し、今その子供達が育ってきました。そして気仙沼湾は蘇ってきたのです。きれいな水にしか棲まないとされるウナギも戻って来ました。こうした実態を目の当たりにして、関係する役所の縦割り行政も変わり、以前は「陸と海は別の研究」としていた学問の分野も変化し、京都大学では森里海連環学部が発足しました。もうひとふんばりで日本の海は蘇る…私は今、その確信に満ちています。 それ以来、これまでに8000人の子供達を招待し、今その子供達が育ってきました。そして気仙沼湾は蘇ってきたのです。きれいな水にしか棲まないとされるウナギも戻って来ました。こうした実態を目の当たりにして、関係する役所の縦割り行政も変わり、以前は「陸と海は別の研究」としていた学問の分野も変化し、京都大学では森里海連環学部が発足しました。もうひとふんばりで日本の海は蘇る…私は今、その確信に満ちています。
構成・文:宮崎伸勝/写真:黒須一彦(エコロジーオンライン)
|