
講師紹介
寄本 勝美氏
1940年和歌山県生まれ。
1964年早稲田大学第一政治経済学部卒業。法学博士。
現在、早稲田大学政治経済学部教授。環境庁中央環境審議会委員、東京都清掃審議会委員なども務める。
専攻は、地方自治・環境政策。
1.廃棄物とリサイクルをめぐる問題
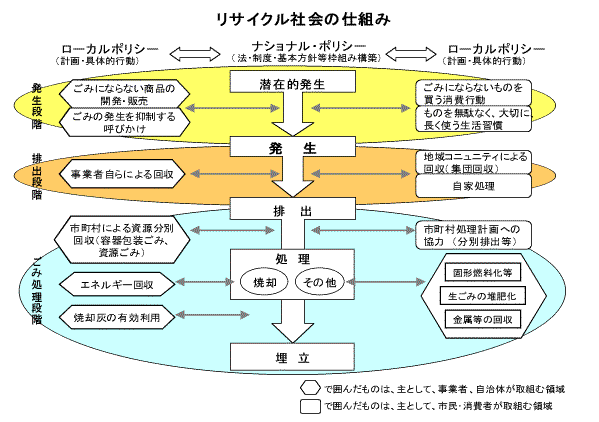
廃棄物問題を考えるとき、廃棄物をとりまく全体のしくみを押さえることが重要である。
消費者としての課題は、できるだけごみにならない物を買うように努める、ということに尽きる。
アメリカのあるコンシューマー活動家が次のように言っている。
「物を買うということは、選挙で一票を投じることである。
リサイクル型の商品を買うということは、その商品に一票をいれて、選挙でいう当選させるということである。
リサイクルやごみ処理に対して何の配慮もしていない商品は買わない。
選挙で落選させるということ。
消費者がこういう意識をもつことで、廃棄物をめぐる状況はすいぶん違ってくるはずである。」
生ごみ問題にしても、生ごみをいかに再利用するかの前に、食べ物を残さずに食べるという基本的な姿勢が当然必要なのである。
廃棄物問題の根底にあるのは、「物を無駄なく使う。長く利用する」という、我々が日常に行っている我々自身のライフスタイルについて、問われているということである。
例えば、ごみの潜在的発生を100だとすると、それに対するさまざまな取り組みによって60~70位くらいまで減らすことができれば理想であるが、現実的には100を90位までに減らすことができればよしといえるのではないか。
90のごみがいったんでることになるわけだが、しかし、発生したものがすぐにごみになるわけではない。
例えば、ビールびんに代表されるリターナブルびんのように事業者自らが回収するとか、大型家電4品目についても、新しい法律によって電気店を通じて事業者が回収する、ドイツで行われている使用済み電池の回収に対するデポジット制など、処理の方策はさまざまに考えられる。
事業者による回収のほか、地域コミュニテイでもできることはたくさんあるだろう。
リサイクルショップを設け、古着の交換をするなど、物理的にごみの減量化を推進するだけでなく、活動を通して地域のコミュニケーションが図られ、まちづくりが促進されるという効果も持つ。
2.発想の転換と新しい廃棄物管理
自治体の清掃事業も随分変化してきた。
この図に示されていることは、以下のような役割の再構築である。
廃棄物の処理作業は、もともと住民や事業者に責任があって、自治体はその代行者であるという考え方をもっと強く自覚すべきである。
要は根幹の部分は国が施策として考え、それを元に自治体は地域の実状にあったしくみを採用し、事業者、消費者は十分にこれに協力する、ということではないだろうか。
3.循環型社会の形成のための政策
有料制が消費者や住民の協力がなかなか得られないのであれば、一律に有料を強制化するのではなく、ごみ減量に努力している人が得をするようなシステム、ごみをたくさん出す人にはその量に応じて金額を負担してもらうなど、さまざまな方策が考えられるだろう。
多くの市町村でリサイクル型のごみ分別収集が行われている。
ごみ処理段階での、エネルギー回収、固形燃料化など、多くの再資源化が可能となっている。
最終的に、出てきたものが埋め立てとなるのであるが、95%が資源化され、5%が埋めたてとなれば、循環型社会も夢物語ではなくなるはずである。
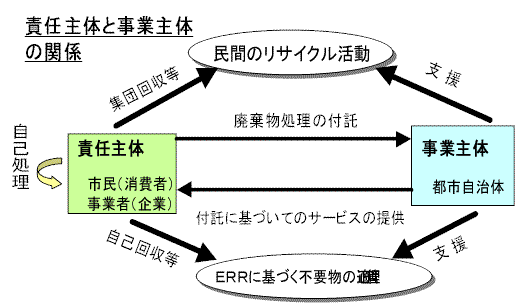
そうすれば、もともとの責任主体である住民や事業者に対し、自治体の施策への協力を義務づけることができるはずである。
![]()
つまり、ある製品が10年しか持たないものを13年まで使えるように延長させることは、質的に良い製品であるわけだから、当然価格は高くなる。
消費者は高いものを買って長く使うことになる。
さらに長く使えるよう、修理などのリフォームを行うと、修理部門、部品部門など静脈産業が活性化することになる。
静脈産業が活性化することによってあらたな雇用の需要が生まれ、あるいはあらたな経済活動が生まれる可能性がある。
高いが長く使える製品というのは、全体としては経済活動が活発化することにつながるのである。
循環型経済は、経済の活性化を弱小させるものではないのである。

沖縄では分別収集システムを進行させても、地理的条件から資源再利用するための工場がない。
分別収集した廃棄物を本州に戻すためには高いコストが必要である。
そこで本州よりも近隣である中国に注目し、中国とタイアップしてリサイクルネットワークをつくることに成功したという事例がある。
沖縄からの資源は、中国国内で需要が大きい古紙生産にも協力がなされている。
リサイクルの国際化は大変重要な取り組み課題になるはずである。
今後のために留意点として以下の3点を挙げておきたい。
ほとんどの市町村では家庭系のごみは税金で処理されているのが現状であるが、北九州市や青梅市など、有料制にきりかえたことによってごみの量が削減されている。
また、経済的なインセンティブも効果が大きい。
スーパーなどで、新しい買い物袋をもらわないことを励行するよりも、買い物袋をチップ制にした場合のほうが、実際には買い物袋を持参する比率が高くなっているようだ。
ドイツでは買い物袋を有料化しているところが多い。
また、有料制は、税の二重取りという問題がでてくるが、市町村は、有料制による収入を緑地を買収したり福祉基金を設けるなどして、住民に目に見える形で還元すればよいのではないだろうか。
4.リサイクルを支える3つの柱と3つの市民
【3つの柱】
- ①技術
- かつては乏しかったリサイクル技術であるが、現在は技術開発が進み、例えば「紙から紙をつくる」ほか、「紙から建材、燃料、炭」までをも再生品化できるほど技術は進歩している。
- ②経済
- 廃棄物処理は公共が、リサイクルは民間が、というように、いままでは分断されていたしくみを、相互乗り入れにすることによって経済的に一体化を促す。
このような構造改革を進めることにより、循環型経済を目指すことが可能になる。 - ③コミュニテイ
- リサイクルは単に物理的な効果だけではない。地域、まちづくりの形成にも重要な意義を持っている。
コミュニテイとは家庭であり、町内会、マンション、地域社会、学校、企業、自治体、ひいては国である。
リサイクルを進めることは、地球環境問題に取り組むあらたな「国」づくりになるのである。
これらの3つ柱を、3つの市民(生活者市民、企業市民、公務員市民)が共に支えあい、共に参加しあって、初めてリサイクル社会、循環型社会の実現をめざすことが可能となるのではないだろうか。
参考文献
| 書籍名 | 著者 | 出版社 |
| 「ゴミとリサイクル」 | 寄本勝美 | 岩波新書 |
| 「政策の形成と市民 ~容器包装リサイクル法の制定過程」 | 寄本勝美 | 有斐閣 |
| 「廃棄物と汚染の政治経済学」 | 吉田文和 | 岩波書店 |
| 「廃棄物概論」 | 田中勝 | 日本環境測定分析協会 |
| 「リサイクルの知恵袋」 | 石澤清人他 | 中央法規 |
| 「インターネット市民講座」の著作権は、各講師、(社)日本環境教育フォーラム、(財)損保ジャパン環境財団および(株)損保ジャパンに帰属しています。講義内容を転載される場合には事前にご連絡ください。 All rights reserved. |